『ウィニングカルチャー 勝ちぐせのある人と組織のつくり方』ではチームや企業の組織文化の変革方法についてまとめています。本書の中で組織文化を進化させる企業として紹介しているジョンソン・エンド・ジョンソン。本連載では玉井孝直社長への取材を3回に分けて紹介します。前編「J&Jの従業員が78年の間、世界中でクレドーを大切にしてきたワケ」に続き、中編では未曾有の危機でも同社の従業員が判断に迷わず迅速に動けた理由を解き明かします。(構成/新田匡央)
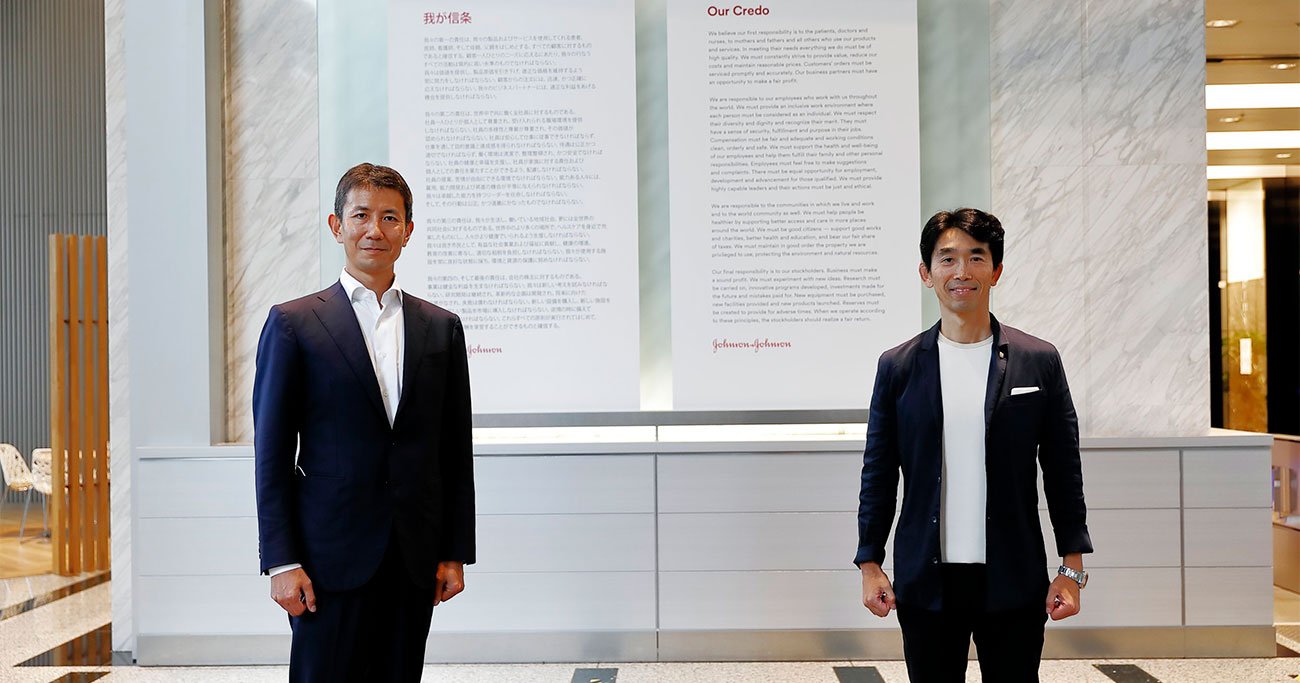 ジョンソン・エンド・ジョンソンの玉井孝直社長(写真左)と中竹竜二さん(Photo/竹井俊晴)
ジョンソン・エンド・ジョンソンの玉井孝直社長(写真左)と中竹竜二さん(Photo/竹井俊晴)
中竹竜二さん(以下、中竹):ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、組織文化がしっかりと確立されています。その状態をどのようにして衰退させずに進化し続けるか。難しいのは、いまの状態に満足しながらも、まだまだ良くすることができると考えているところにあります。
このバランスは非常に難しいところだと思いますが、それはどのようにしていますか。
玉井孝直社長(以下、玉井):まさにいま、もっとも感じているところですね。クレドーは78年も続いているので、プレッシャーのようなものはあります。クレドーに基づいても解決できない課題が生まれることもあるのかもしれません。
とはいえ、まだ起こっていないことを考えるよりも、毎年実施するサーベイの結果をしっかりと受け止め、改善する部分をみんなで継続的に対処していくしかありません。それはリーダーだけが行うものでもなければ、社員だけが対応するものでもなく、一緒にやっていかなければ、絶対にうまくいかないものだと思います。
中竹:コーチングの世界では「セルフダウト」と呼ばれますが、いい意味で自分を疑うことをしていかないと、なかなか進化はできません。
玉井:その意味で言うと、クレドーの良さには疑いがありませんが、自分も含めて組織の中にいる人間がすべて100点を取れるほどできているのかと問われたら、そんなことは決してありません。当たり前だと思ってはいけないところがあるゆえに、より現場に出る機会を持ったりして、常に確認しています。
中竹:セルフダウトという意味で、クレドーの解釈や前提をとらえ直してみることはありますか。
玉井:サーベイとは別に「クレドーチャレンジ」という仕組みがあります。サーベイのように定期的に行われるものではなく、タイミングを見てリーダーが中心になって取り組んだり、チームで取り組んだりします。
世の中に、簡単な問題はありません。さまざまなエシカルジレンマ(Ethical Dilemma)があるような実際のケースを例にとって、このような時にどんな判断を下すのがクレドーベースとして正しいのか、とディスカッションをするセッションがあります。
中竹:それは事実に基づいた事例ですか。あるいは過去のケーススタディーでしょうか。
玉井:どちらでも。グローバルで考えることもあるし、自分たちで考えてもいい。
たとえば、ジョンソン・エンド・ジョンソンは福島に工場があります。東日本大震災のとき、製品のサプライをどうするか、工場の復旧をどうするかについて、社員の安全と顧客に対する信頼を守りながら、どのようなバランスを取っていくかの判断に迫られました。
この問題には、おそらく正解はありません。そこをあえて考え、リーダーシップチームで話し合います。Aさんはこの点を重視して判断しようとしていたけれど、Bさんは別の角度から判断しようとしていた。そうした考え方の違いを互いに知ることができ、クレドーに対する解釈がさらに進む取り組みとなりました。
中竹:仕組みとしてあるのは、継続する点で大きいですね。
玉井:そうですね。ただ、サーベイのように社員全員が行っているわけではなく、リーダーシップチームがメインになってやっていくことが多いです。
中竹:企業は危機に直面したときに地金が出ます。そして、危機を乗り越えた後は、その対応がどうだったかと振り返って検証しようとしません。しかしジョンソン・エンド・ジョンソンではそれを検証しているわけですね。こうした取り組みが、クレドーを進化させるのに役立っているのでしょうか。
玉井:そうだと思います。クレドーチャレンジは節目節目でやっています。
中竹:サーベイは年1回ですか。
玉井:サーベイは毎年必ずやっています。これはどんなに忙しくてもやっているんです。
中竹:質問も少しずつ変えているんですよね。
玉井:少しずつ変えていますね。これはすべてグローバルで決めています。質問の内容が曖昧になって国ごとにバラつきが出ないように、しっかりとコントロールしているんです。
中竹:2018年にはクレドーの4回目の変更が行われたということですが、次に変える時期は決まっているのですか。
玉井:決まっていません。過去に変えたのも、たとえば「看護婦」を「看護師」に変更するような小さなものから、2018年の変更のように、ダイバーシティに関する内容や社員の健康に関する文言を拡充するなど、比較的大きな変更もあります。
中竹:時代の流れや、進むべき方向に照らし合わせて変えるということですね。コロナ禍を経て、「社員」という概念もかなり多様化していく気がします。そのあたりも次の変更に入るかもしれませんね。
玉井:そうかもしれませんね。ただ、クレドーを変更するのはかなり大変なことですし、何より基本的には普遍的な内容になっているので、毎年のように変えるということはないと思っています。
中竹:3回目にクレドーを変更したのはいつでしたか。
玉井:1987年です。そのときは、顧客の前提に「母親」だけしか入っていなかったので、「父親」を加えました。またワーク・ライフ・バランスの考え方が入ったのもこの年です。「社員が家族への責任を果たすことができるように会社として配慮しなければいけない」という言葉も加えられたのです。
中竹:早いですね。最近言われるようになったことを、すでに30年以上前に意識されていた。
玉井:そうですね。2回目にクレドーを変更した1979年には「環境と自然資源を保護する」という文言を入れています。
中竹:それも早いですね。クレドーの変更は、グローバルが考えて、各ローカルへ共有するような形なのでしょうか。
玉井:そうです。ただ変更する前にはローカルからグローバルに対して、ある程度のインプットはあると思います。2018年、4回目の変更をしたときには2000人くらいの社員から意見を聞いてグローバルが考えました。
中竹:まさに意思決定のスタイルみたいですね。
玉井:いいバランスでボトムアップとトップダウンを両方やっていると思います。外資系企業の場合、会社によっては、グローバルの指示通りに動かないとダメなケースもあります。しかしジョンソン・エンド・ジョンソンは各ローカルのオペレーションに自由度がある会社だと思います。そこが好きで働いている人も多いと思いと思いますね。
ただ、最終的な結果は求められるし、それはクレドーにも書かれています。だからこそ自由度が高くなっているんです。
(対談後編は2021年3月13日公開予定です)



