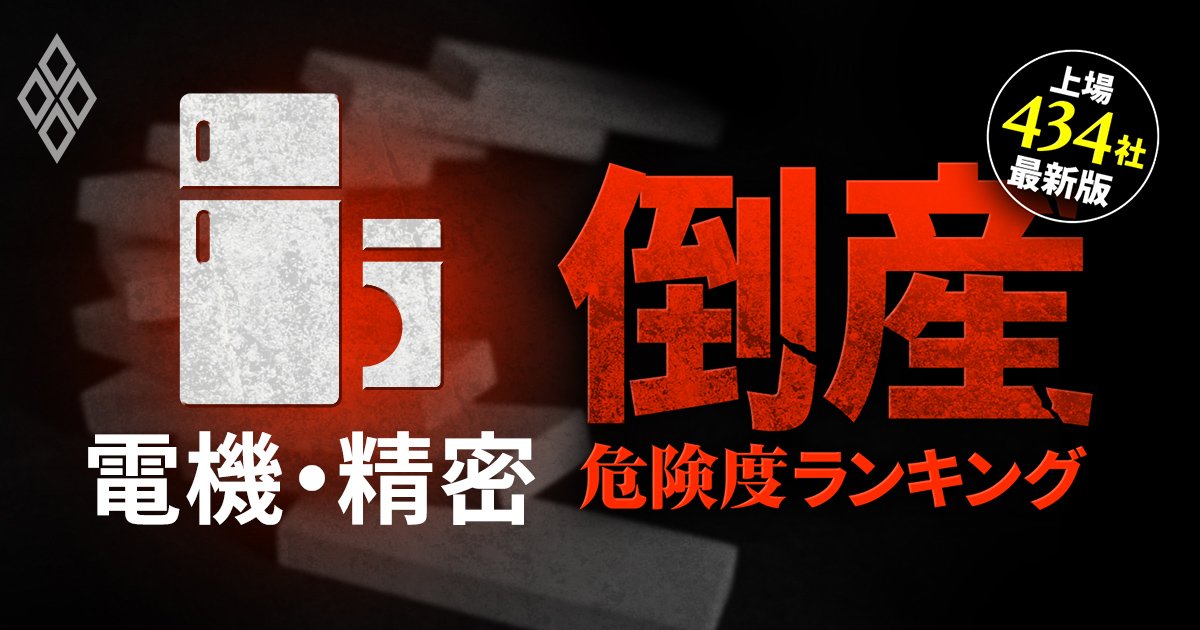日本企業の砂漠での奮闘も見逃せない
カタールだけにフォーカスしても、ありとあらゆる領域に中国が顔をのぞかせる。“国家・企業総当たり戦”で数々のプロジェクトや資源を巻き上げていく中国には、もはや太刀打ちできない。
しかし、水事業に目を転じれば、日本企業に大きな可能性が残されている。「水道水が飲める」という日本の水は、それだけで技術力の高さを反映しているからだ。
2030年、世界の水事業の市場規模は110兆円を超えるといわれている。また同年には水の需要に対し水資源が40%も不足すると懸念されており、水供給の重要性は高まるばかりだ。
それだけに日本企業の躍進が期待されるのだが、いくつかの要因が日本企業の対外進出の成功を難しくしている。ある自治体職員はこう話す。
「水の供給や水道料金の回収など、運営ノウハウは行政にあり、一括請け負いを求める発注側の意図に沿えず、チャンスを逃すことになっているのです」
日本の場合、得意分野ごとにプレーヤーが分かれて存在し、水メジャーの仏ヴェオリア、仏スエズのように一括で事業受注できるところがほぼないというのだ。近年はこうしたハンディを克服しようと、複数社が連合する動きがあるものの、日本勢全体に依然課題は残る。
長年、環境関連企業の対外進出をサポートしてきたコンサルタントは「日本企業は、相手国の要求に合わせるのがあまり得意でない」と指摘する。
「結果として相手側に“日本基準”を押し付けてしまう傾向があります。現地の風土に合わせた研究開発や技術対応が課題です」(同)
これに対して中国勢は、品質と価格を段階別に分けた“オプションの幅の広さ”と“柔軟な対応”を得意としている。
冒頭でクボタのCMについて紹介したが、カタールにおける日系企業は決して負けてはいない。同社広報部は「カタールでは海水の淡水化プラントをはじめ、水道管・ポンプ・下水処理場などにおいて、ノウハウと高い技術力を持つ多くの日系企業が奮闘中」だという。
森保ジャパンは惜しくもベスト16で敗退したが、砂漠の地で繰り広げられる“もう一つの闘い”を応援したい。