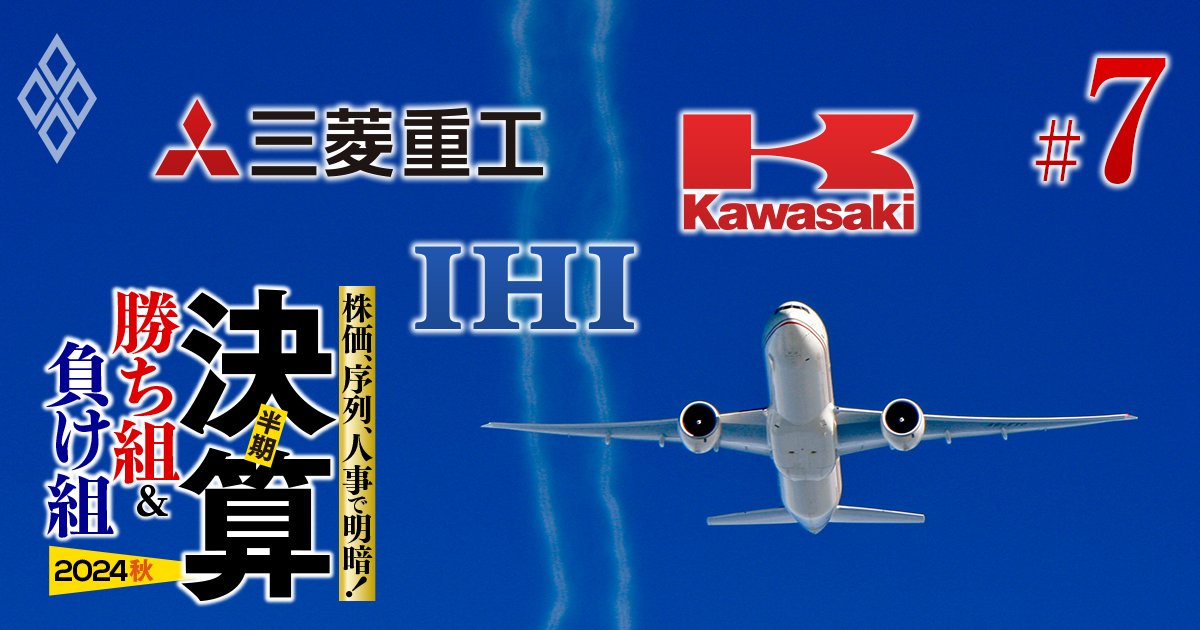デジタル変革のブースターとしてのデザイン経営
産業におけるデザインの力の源泉は、「ユーザーを理解する力」と「統合志向(統合的にプロダクトを取りまとめる力)」の二つで捉えることができる。
まず、「ユーザーを理解する力」はあらゆるデザインの起点である。家具デザイナーは美しさや使い心地を考え、UX(ユーザーエクスペリエンス)デザイナーはユーザーの感情の動きをとらえる。デザインという言葉で表現される活動はさまざまだが、いずれもユーザー理解を起点に、あの手この手で人間と人工物の間の親和性を高めていく営みなのだ。
もう一つは「統合志向」だ。デザインは、個々の機能を個別的に捉えるのではなく、それらを一つのプロダクトやサービスに統合(インテグレーション)することを志向する。全ての要素を統合した完成品が、ユーザーにどんな価値を与えるのか――。デザインはそこにこそ、強くこだわる。優れたプロダクトなりブランドなりを作り上げるためには、ユーザーの声を集めるだけでは足らず、さまざまな要素の矛盾を擦り合わせていくための「意志」や「美学」のようなものが必要となる。優れたデザインはチームに方向性を与えることができる。
そう考えれば、エンドユーザーとの接点を持つビジネスにおいてデザインが重要なのは当然であり、中でも、UI(ユーザーインターフェース)やUXが収益の根幹となるデジタル系スタートアップが真っ先にデザイン経営を導入したのも必然といえる。
逆にエンドユーザーとの接点を持たない企業の場合、つまりサプライチェーンの中間に位置する企業にとっては、提示された仕様・納期通りに製品やサービスを仕上げる力の方が重要である場合が多い。このような領域ではデザインの力よりも、技術や営業の方が経営上の優先度が高い。日本には、部品装置産業や素材産業など、このサプライチェーンの中間に位置する有力企業が多く存在している。現時点では、このような企業にとってはデザイン経営の優先度は決して高くない。しかし、時代の潮流として、デジタルシフトや自社ブランドの立ち上げなどにチャレンジする企業は増加傾向にあり、このような企業にとってはデザイン経営を導入する意義が発生し始めている。本連載の中では、このような企業の先行事例も紹介してきたい。