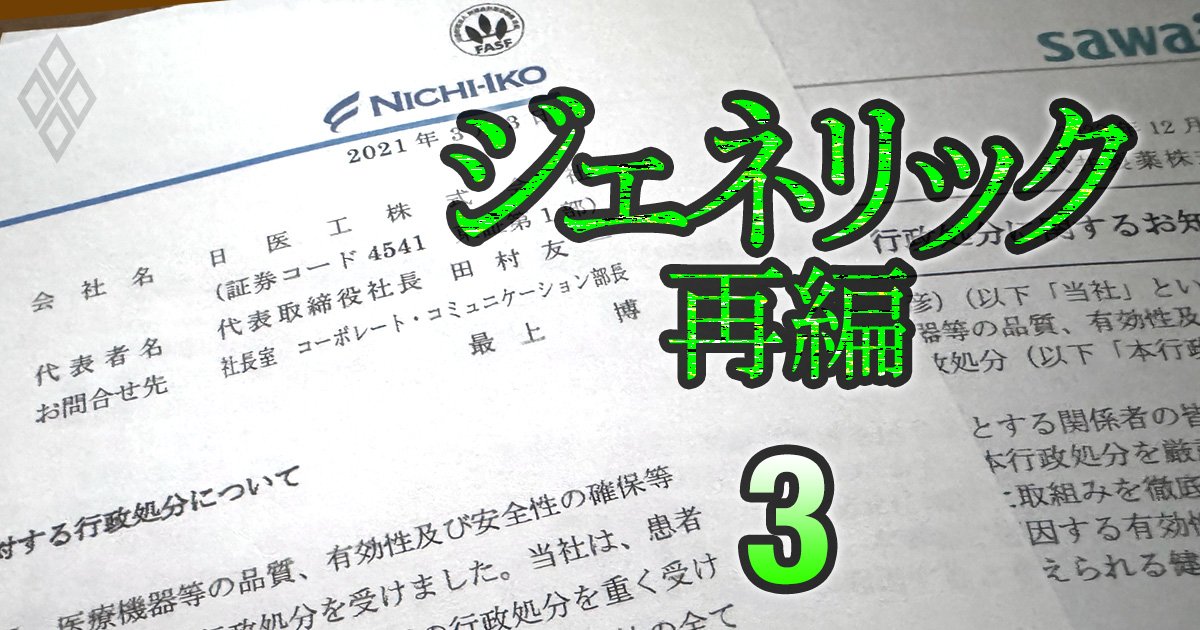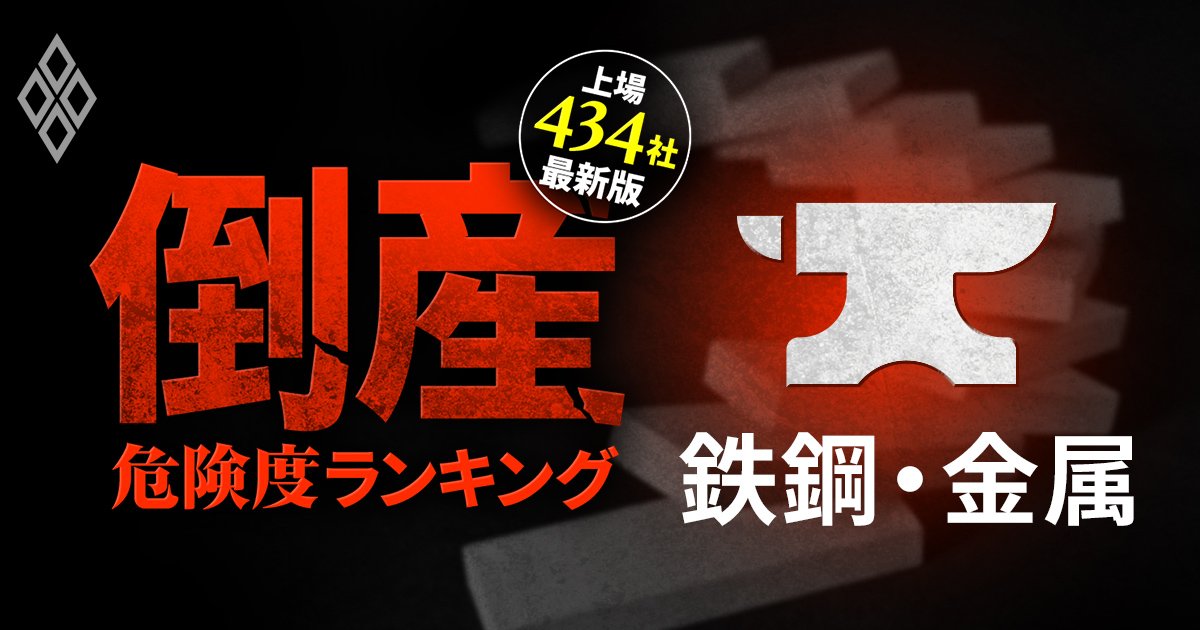ヤマト運輸とのパートナーシップはうまくいった例ですが、うまくいかなかったことも山ほどやっているんです。テレビCMも(日本では)結構大胆にやってうまくいったからと、米国でもやったんですが、何億円か使ったんですが、まったく効果がなかったんです。

ですが「やっぱりスタートアップなんだから、ダメ元でいいからとにかく大胆なことをやろう」と言ってやってみて、その中のごく一部が後の成果につながっていて──そういうことをやっていったことが、中から見ても外から見ても「大きかったよね」とその後に言われました。
だから「Go Bold(大胆にやろう)」というバリューは、自分たちにとってものすごく重要だという話は、社内でもよくしています。他の会社がやっていないことをやって、特別な成果を得る。結局、普通の会社と同じことをやっていたら普通の成長しかしません。
ジャンプする仕掛けを作るために大胆なチャレンジをして、ほとんどうまくいかないけど、それを称賛するというか「いいチャレンジだった」という話をする。そのことによって「これはうまくいかなかったけど、また次はやろう」となることが大事です。
「メルカリ アッテ」というサービス(地域ユーザー同士で情報交換できるアプリ。2018年にサービス終了)でも、(主要プロダクトの)メルカリや当時作ろうとしていたメルペイに集中した方がいいということで、「どっちがやりたいか」「どっちが可能性あると思うか」という話を松本くん(アッテを運営していたソウゾウ元代表・メルペイ元CPOの松本龍祐氏)としました。それで「メルペイやります」となりました。
(サービスが)終わった時には「こういう結果が出て閉じることになったけど、すごいグッドチャレンジだったと思う」とそれを全社でたたえました。その後、(アッテをやっていた)メンバーはメルペイやいろいろな事業に所属が分かれていきましたが、その先での仕事を続けてくれている人も多くいます。
メルカリはそういう新陳代謝というか、「ワーッと始めてワーッと引く」といったところがあります。UK(英国)もそうです(英国事業は2018年12月に撤退を発表)。
新型コロナウイルス感染拡大のときには「配送が止まったらうちのビジネスは終わる」ということで「一気に筋肉質にするぞ」と言っていたんですが、結局6月(決算)ではすごく(業績が)伸びて黒字になり、逆にちょっと絞りすぎたという感じでした。ウクライナ侵攻の2022年2月にも同じように「何が起こるかわからないから、一度、取捨選択しよう」と絞って、また6月には黒字になっているんですけれども。