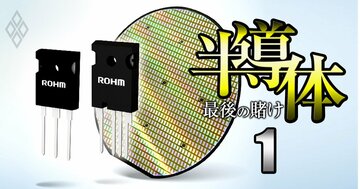業態の転換を自ら拒んだ東芝
デジタル時代の到来を、かなり早い段階から予見していた面もあった東芝。ところが、経営陣は重電・家電の両分野で、過去の発想に固執した。ある意味、業態の転換を拒んだといっても過言ではないだろう。
そして、2015年に発覚した不正会計問題は、その後の同社の運命を決定付ける一大不祥事となった。東芝は、事業環境の変化に対応するよりも、ノートパソコンなど既存事業の収益を過剰に追求したのだ。不正会計問題をきっかけに東芝の企業イメージは悪化し、顧客離れが加速、業績は低迷した。さらにとどめを刺したのが16年、米原子力大手ウエスチングハウス(2006年に約6000億円で買収)の損失発生だ。東芝は債務超過に陥った。
結果論にはなるが、東芝は、不正会計問題やウエスチングハウスに起因する1.4兆円の損失発生のタイミングで、一連の経営の失敗を認めるべきだった。総合電機メーカーとしてのビジネスモデルの限界を理解し、社会インフラや半導体、医療、量子コンピューティングなど中長期的な成長の可能性が高い分野に経営資源を再配分すべきだった。
当時の東芝は、抜本的な事業構造の改革よりも、上場維持にこだわった。17年には第三者割当増資を実施し、海外ファンドなどから6000億円を調達した。公募ではなく、第三者割当増資になったのは、多くの投資家が東芝の先行きを不安視したからだろう。
第三者割当増資により上場は維持できたものの、その後、経営の混乱に拍車がかかった。医療機器や半導体事業の売却などによって収益は減少し、リストラによって組織体制も縮小均衡に向かった。一方、出資に応じたファンドは株主への価値還元(自社株買いや増配)を要求した。業績が悪化する中での自社株買い資金の捻出は、追加的に経営体力をそいだ。
こうして東芝は事実上、アクティビスト・ファンドに翻弄された。分社化など生き残りをかけた改革案の実行も遅れた。最終的に東芝の事業運営は行き詰まった。