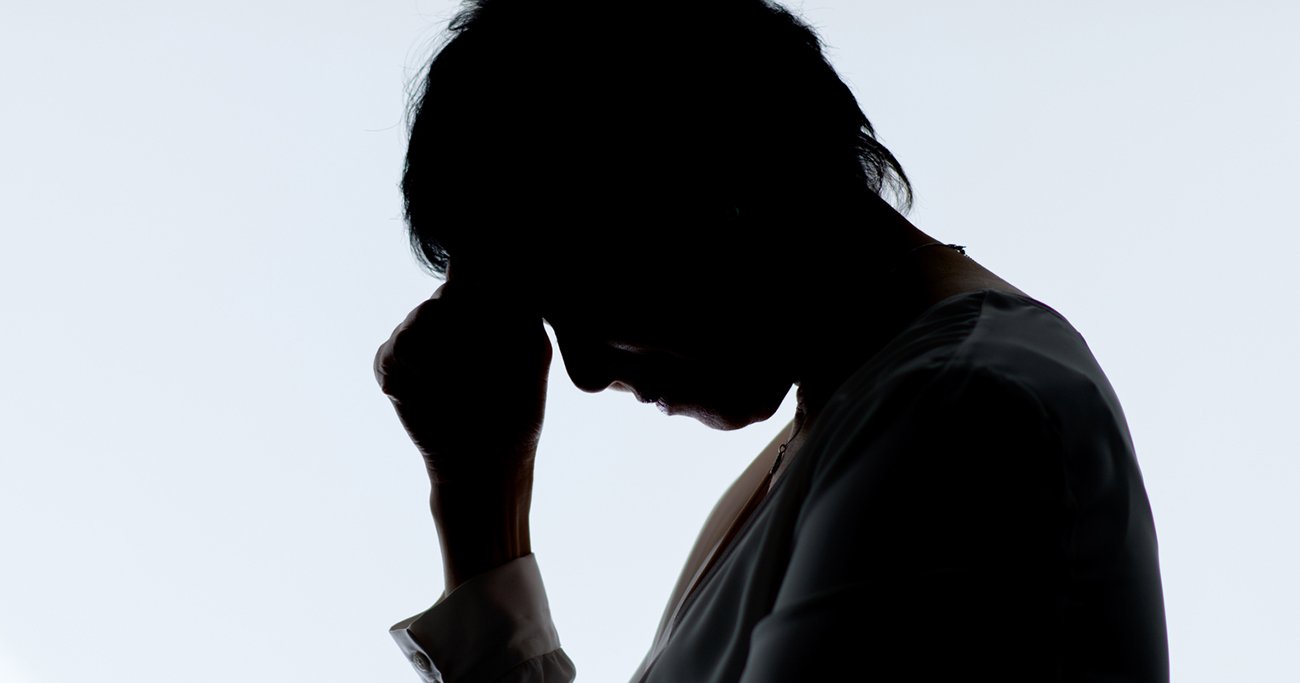 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
心配事は誰もが抱くもの。だとしたら、心配性と不安症の境目はどこにあるのだろうか。医学的には心配事の内容に正常と異常の線引きはないという。精神医学の観点から見た「不安」のメカニズムはどのようなものだろうか。本稿は、原井宏明・松浦文香『「不安症」でもだいじょうぶ ―不安にならない、なくすという目標は間違いです』(さくら舎)の一部を抜粋・編集したものです。
自己診断できる
心配性と不安症の違い
感情自体は誰もが抱くものだとしたら、病気と正常の境はどこにあるのでしょうか。
心配事は、誰もが考えうることで、逆に心配していない人のほうが病的に見えます。
医学的にも、心配事の内容に正常と異常の明確な線引きはありません。
肝心なことは、そのことを考えている時間が長く、生活に支障が出ていることです。
もし高所恐怖があったとしても、地上で生活している分には困りません。
しかし、頻繁に飛行機に乗って海外出張する必要があったとしたら話は別です。本人だけでなく、職場の人も困ってしまいます。
このように、心の病気は基本的に生活への支障の程度で判断します。検査結果だけで診断できる病気は意外と少ないのです。困っていない人はそもそも受診をしないので、診断されることもありません。
もし自分が心の病かもしれないと思ったら、ここ1週間を振り返り、とらわれている時間の長さと日常の活動への支障の程度を調べてみましょう。
この情報は、医師との診察時に自分の状態を説明するときにも役立ちます。
これって病気?
不安の診断基準
精神科医は、アメリカ精神医学会がまとめた「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」と世界保健機関(WHO)がまとめた「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」という診断基準をもとに診断します。
おもに次のポイントに注目し、それぞれの病気ごとの診断基準と照らし合わせ、見きわめます。
1 日常生活にどれくらい支障があるのか
2 家族などのまわりの人にはどれくらい支障があるのか
3 本人やまわりの人に危害を及ぼす可能性があるか
4 いつ、どこで、どのような場面で症状が生じるのか
5 いつから症状が生じたのか
6 他の病気では説明がつかない
診断をするためには、病態を引き起こすほかの要因がないかを鑑別します。血液検査などをおこなって、ほかの病気がないかも調べます。貧血や甲状腺機能の異常、薬物の影響なども考えられるためです。
また、精神疾患の一部は遺伝することがあるため、近親者に似た症状のある人がいないかについても確認をします。それらの結果を鑑みて、その病気以外では説明がつかないと判断した場合に診断します。







