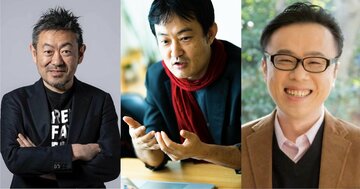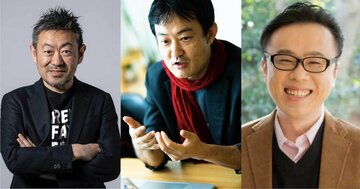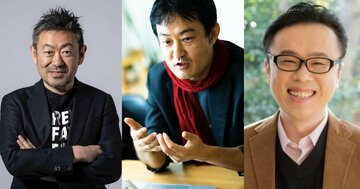グローバルでは「Sler」が通じない
尾原:澤さんは、日本マイクロソフトの業務執行役員をされていたこともあって、グローバルな観点をお持ちだと思います。先ほど、AIによる成長格差のお話がありましたが、日本の傾向として、何かありますか?
澤:ITやデジタルの文脈だと、「事業会社(買い手)側にICT人材が少ない」という問題がありますよね。
尾原:確かに。
澤:よく言われる話ですが、日本ではICT人材の多くがITベンダー(売り手)側にいます。そしてITベンダーの中に、プラットフォーマーが極端に少ない。
一方、アメリカでは約35パーセントがITベンダー側、約65パーセントが事業会社側にいます。
尾原:その65パーセントの人たちが、ITを使いこなしているんだ。
澤:そうです。アメリカは、「自分たちのビジネスをグロースさせるために、ITを使いましょう」という観点になりやすいんですよね。そして、そこで売上に貢献した人、特にCIOクラスの人たちが、別の業種や業態に転職していくわけです。
しかし日本はICT人材がITベンダー側にいて、それもSIer(システムインテグレーター)です。僕はマイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長時代、コミュニティに属していて、世界各国に仲間がいたんですけど、驚いたことに「SIer」という言葉が通じないんですよ。
伊藤:へぇー。
尾原:それも通じないんだ。
澤:通じないんですよ。感覚的にわからないんです。
尾原:「それは買い手側が考えることじゃないの?」と。
澤:そうです。「それって、Sub Contractor(サブ・コンストラクター)だろ?」と。
僕が、「違うんだよ。実はこういうところまで外部のベンダーがやってね」と説明したら、「それって事業会社としてマズくないの?」と驚かれて。
「日本の業態として、そうなっちゃっているんだよ」と答えました。
伊藤:SIer的な感覚は日本だけですか?
澤:少なくとも僕が付き合っていたG7の国は全部、感覚が違いましたね。
伊藤:「日本のITに対する考え方は、他国と違うんだよ」と。これは、めちゃくちゃ重要な示唆ですね。
尾原:そうですよね。日本は買い手側の企業にCIO(最高情報責任者)やCTO(最高技術責任者)がいない。これは統計的にも明らかな事実ですよね。
澤:そうですね。