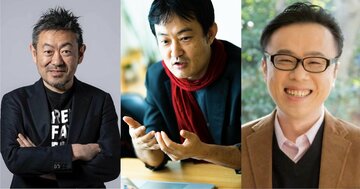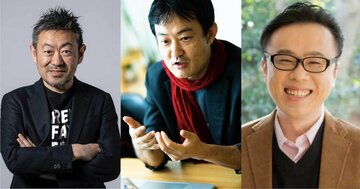「手間がかかることは美しい」日本のカルチャー
伊藤:「便利になるんだったら、使えばいいじゃん」と思うんだけど、どうしてなんですかね? 拒否反応なのか、それ以前の問題なのか。
澤:「わからないものは、とりあえず使わないでおく」というのが、安全策なのでしょうね。日本人の国民性として、「石橋を叩いて渡らない」ことが起きやすいんです。それによって治安が守られるなど、いいことがあるかもしれません。
だけど日本はG7の中で、「経済」といった観点での成長曲線が極端に低い。これは厳然たる事実なんですね。そう考えると、新しいものになかなか手を出さないことによってチャンスを逃すのは、日本の「お家芸」になってしまっているところがありますよね。
伊藤:お家芸だね。
尾原:そうですよね。澤さんがおっしゃったように、日本は「ITを仲間として使う」人材が、買い手側にほとんどいない。一方アメリカでは、3分の2くらいが買い手側にいる。そこが本質だというのは、すごくわかりやすい視点ですよね。
澤:もちろんアメリカでも、SF映画の影響を受けて、「とにかくコンピューターはおっかないものだ」「調子に乗らせるとターミネーターが襲ってくる」と思っている人がいます。
尾原:そうですね(笑)。
澤:日本人は、ラクをすることへの罪悪感がめちゃくちゃ強いところもありますよね。
僕は学生に、「手書きの履歴書を求める会社には就職するな」とよく言っています。
尾原:わかりやすい。なるほど。
澤:「会社に入ったあとも、同じことをやらされるよ」と。
「『手間がかかることは美しい』カルチャーの可能性が高いから、そういうところには行かないほうがいい」「情報がほしいのか、無駄な努力がほしいのかを測るリトマス試験紙なんじゃない?」と言っているんですよね。
尾原:そうですね。手書きよりもWordを使って書いたほうが、企業分析や自己分析に時間が使えますからね。
手書きだと、書くだけで精一杯になるから、「前の会社の履歴書をコピペしよう」となる人が増えるかもしれない。
澤:昔は、「修正液を使ってはいけない」なんてルールもあったじゃないですか。
伊藤:あった、あった。
尾原:そうですね。
澤:「字が汚いのは、やる気がないからだ」と言う人もいますが、もしかしたら、その人は突き指をしていただけかもしれないじゃないですか。
尾原:そうですよね。
澤:それが、いまだにまかり通っているみたいですからね。そういうのは、根絶していかなきゃいけないなと思うんですよね。「本気になるのはそこじゃない」と。
伊藤:(笑)。
尾原:先ほどの話に戻るんですけど、「ラクをするのはダメなことだ」と言えば言うほど、AIを壁打ち相手にして成長していく人との差が開いていきますよね。
澤:そうですね。