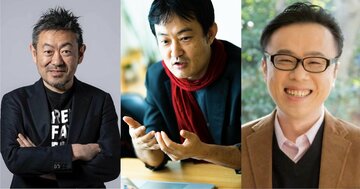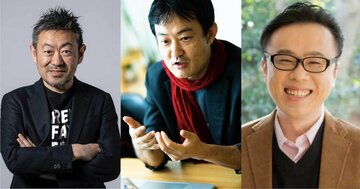ゲームチェンジに気づかなければ、生き残れない
澤:最初に入った会社の同期を想像していただきたいんですけど、我々の世代でいえば、「一度も転職していない」「海外に出たことがない」「自分でパソコンを買ったことがない」人がいるわけじゃないですか。
伊藤:いますね。
澤:あえて自分たちと比べてみた時に、体験した量に差が出ている。体験した側からはそれがわかるけど、本人たちは気づきようがないんです。
尾原:そうですね。他の体験をしていなければ、気づかないですものね。
澤:そうです。そういう人たちが、1社に長くいたことによって、ともすると発言権が強くなっているわけですよね。
伊藤:それはそうだ。
尾原:なるほど。「俺の経験ではこうだった」と言ってしまうと、会議を支配してしまう可能性があるわけですよね。
澤:そうなんですよ。日本では、さまざまなことが会議の中で「検討」されるじゃないですか。「決定」じゃなくて、「検討」されますよね。
尾原:そうですね。「熟慮の上、前向きに検討していきたいと思います」と。
澤:その中のエッセンスとして、そういった人たちの主張が入ってくると、どんどんボトルネックに引っ張られる。『ザ・ゴール』で散々語りつくされた話ですが、引っ張られて、成長が遅くなっていくことにつながるだろうなと思いますね。
『努力革命』の帯に、「このゲームチェンジに気づいていない人は、生き残れない!」と書いてあるように、そういう人たちがたくさんいる会社は、組織としても生き残れなくなるということです。
尾原:確かに。一部の部署がめちゃくちゃ部品を作れたとしても、ものすごく生産性の低い部署があれば、トータルの生産性がそこに収まりますよね。
それが、『ザ・ゴール』に書かれているTOC(制約理論)ですが、まさに企業もそうです。AIによってめちゃくちゃ生産効率がよくなる場所があったとしても、ボトルネックになる昔からのこだわりがあると、全体が発揮できない可能性が十分にあるわけですよね。
澤:そうです。僕はポンコツエンジニアだったし、社会人として卓越した何かを持っている自覚もないんですけど、いろんな会社の人たちと接点を持っていると、「ものすごくもったいないな」と思います。この人は僕よりも圧倒的に地頭がよくて才能もあるんだろうけど、ボトルネックに気づいていないことで、こんなに損してしまうんだと。
「そこで手を抜くことを覚えさえすれば、ものすごくいい世界が待っているのに」という時に、立てなくてもいい誰かを立てたり、やらなくてもいい何かの儀式を重んじたりすることで、時間がどんどん失われてしまっている。そんな事例を、本当にたくさん見てきました。
伊藤:それは一言で言うと、「目的ドリブン」じゃなくて「手段ドリブン」になっているということですよね。
澤:そうです。
伊藤:立てるとか努力するとか、手段ばかりを考えて、「結局、何をしたいんだ」というところがないんでしょうね。
澤:「手段が目的化している」のですよね。