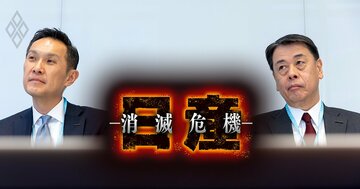三菱自としては、「集中と選択」の決断によってかつての総合自動車メーカーから大きく変身しており、アセアンとオセアニアを稼ぎ頭とする地域戦略と、ピックアップトラックとSUV(多目的スポーツ車)に特化した商品戦略を組み合わせるほか、軽バッテリーEV初の量産化(06年に発売したアイ・ミーブ)の技術力をベースにした、プラグインハイブリッド車(PHV)を得意とする経営戦略を推進する。すでに米国と中国での生産から撤退しており、アセアン重視の姿勢を鮮明にしている。
こうした戦略は、三菱商事のバックアップ体制とも緊密に連動している。インドネシアの工場は、三菱自と三菱商事と現地企業の合弁企業であるほか、昨年には三菱自と三菱商事らがEV総合サービスを共同で設立している。三菱商事の自動車事業の戦略において、三菱自が重要なキーとなっているのだ。
直近の24年度第3四半期(24年4月~12月)では、アセアン・オセアニア地域が振るわず、売上高は前年同期から3.6%減の1兆9892億円、営業利益は同34.7%減の1045億円と減収減益となった。だが、アセアン主体の戦略の中で、タイの需要減少とバーツ高(円安)に対応し、現地で早期退職を募集するなど構造改革も進めている。25年を最終年度とする現在の中期経営計画は、詰めに入っている。
すでにルノー・日産・三菱自のアライアンスがあるが、三菱自が日産との協業をそのまま続けるかどうか、注視が必要だ。例えば、三菱自と日産との協業の中では、軽自動車での連携(三菱自の水島製作所で受託生産)のウエートが大きいが、日産が予定している九州での電池工場設立と合わせて、九州工場での軽EV生産を検討しているというニュースも浮上している。現在は水島製作所で製造しているが、日産は自社生産に切り替える方針で、こうした動きとの兼ね合いも出てきている。
ただし、いずれにしても、その方向性については、三菱自単独の意向というよりも、三菱グループの自動車事業の方向という観点から判断していくことになりそうだ。
(佃モビリティ総研代表 佃 義夫)