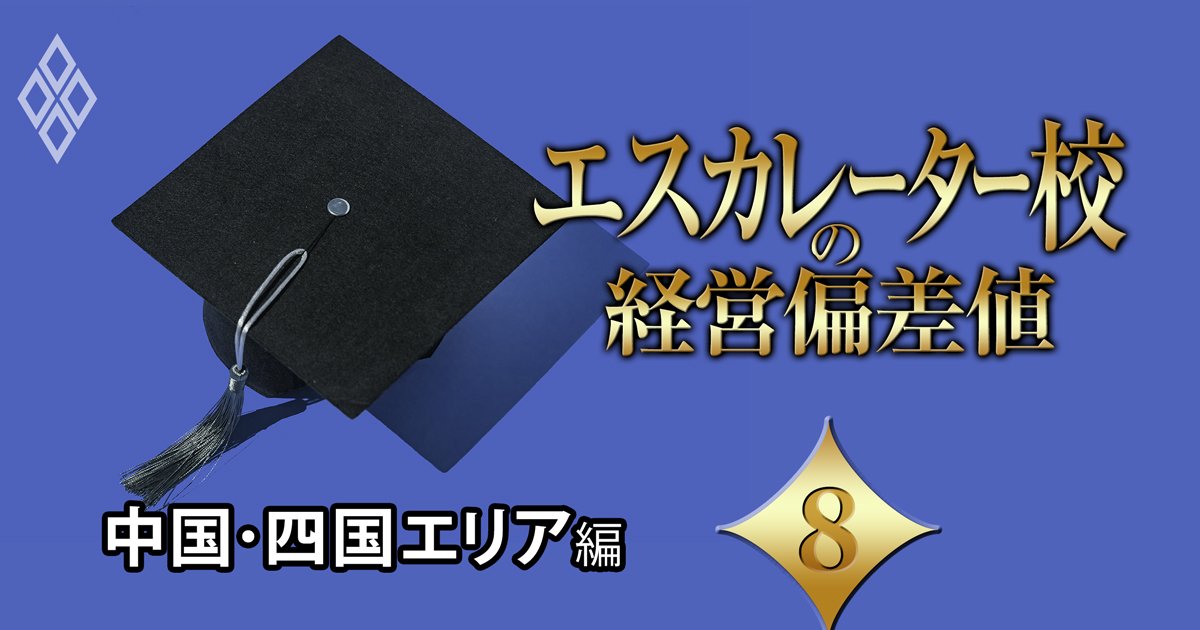スズキが今年発売するクロスオーバーSUVの電気自動車「eビターラ」は、これまでのEVと全く異なる点がある。電池の一部に「LFP」を使っているのだ。それはどんな可能性を秘めているのか。トヨタ自動車が次世代LFPに取り組むワケとは? 中国勢の狙いも含めて考察してみよう。(ジャーナリスト 井元康一郎)
スズキの「eビターラ」が
技術的に大注目なワケ
スズキが発表した新中期経営計画(2025年~30年度)の説明会で、筆者が一番注目したのは目標数値でも、鈴木俊宏社長の言葉でもなかった。会場にお目見えした、今年発売するクロスオーバーSUVのBEV(バッテリー式電気自動車)「eビターラ」である。日本ではスズキ車として、海外ではトヨタ自動車にもデザイン違いの「アーバンクルーザー」として供給する、スズキの電動化戦略の尖兵(せんぺい)を担うモデルだ。
 e VITARA Photo:SUZUKI
e VITARA Photo:SUZUKI
 アーバンクルーザー(TOYOTA C-HR+) Photo:TOYOTA
アーバンクルーザー(TOYOTA C-HR+) Photo:TOYOTA
eビターラには、これまでの日本製BEVと大きく異なる点がある。動力用主電池のセルに、「リン酸鉄リチウムイオン電池」(LFP)と呼ばれるものを使っているのだ。
トヨタはトヨタでアーバンクルーザーとは別に、26年ないし27年に自社製LFPを市販車に搭載する計画がある(23年公表)。こちらは能力を高めた次世代品であるという。
LFPとはいったい何なのか。バッテリー技術では液体電池、全固体電池、半固体電池などが話題に上るが、LFPはそういう電池の構造ではなく、電池内部のカソード(プラス極)にリン酸鉄という物質を使った電池のことを指す。
この形式にはメリットとデメリットが存在する。メリットは、(1)レアメタルを使わないためコストが安く、資源の地政学的リスクへの抵抗性も高い(2)経時劣化や急速充電への耐性に富み、ラフな充電制御も受け入れる(3)物質的に高安定性のため発火しにくく、損傷しても劇的反応に至りにくいなど。
一方、デメリットは、(1)エネルギー密度が低く、バッテリーパックが大きく、重くなりやすい(2)セルあたりの電圧が低く、高電圧を得るにはより多数のセルが必要(3)低温時に性能が落ちる傾向がある、といったところ。
商品化の世界一番乗りは日本のソニーだが、自動車業界ではデメリットの部分がBEVに合わないという見方が優勢。サイズや重量の制約が緩い定置型蓄電装置や大容量化のニーズがそれほど高くないモバイル機器用と受け取られていた。
ところがこの特性を見て“イケる”と思った国があった。