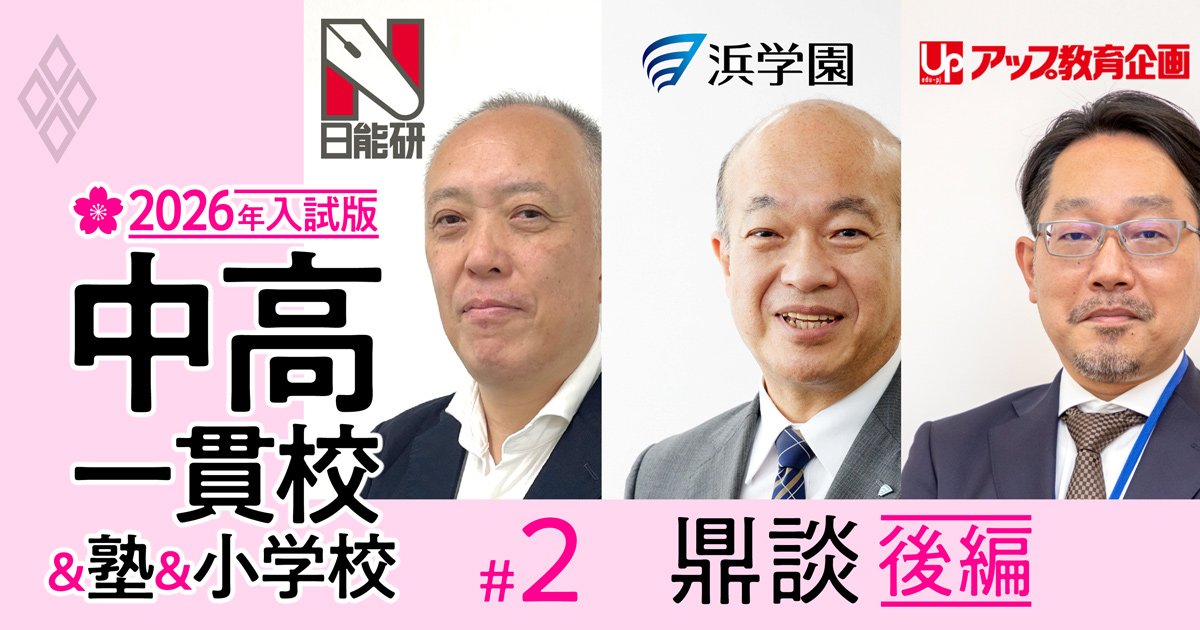残る課題は、こんな充電をやってバッテリーが本当に大丈夫かどうかだ。LFPがNCMに比べて耐久性が一桁違うというのは理論および実験上の話。リアルワールドで本当に大丈夫かは実際に長期間道路を走り回り、走行距離が10万km、20万kmと積み重なったLFP搭載のBEVが増えなければ分からない。
もし謳い文句どおりの耐久性、例えばバッテリー充電率100%換算で1000回相当分の充電を行った時点で容量が80%残存するとしたら、新品時に満充電からの走行距離が実路で航続400kmのBEVの場合、36万km程度の走行を経てなお320kmの走行レンジが維持される計算になる。リアルワールドでどのようなデータが出てくるのか、実に興味深い。
スズキが採用したのがBYD製のLFP
トヨタも自社製LFPを市販車に搭載へ
スズキに話を戻すと、eビターラに採用したのが、このBYD製のLFPなのである。一方、トヨタも自社製LFPを市販車に搭載する計画で、内部構造の技術革新によって性能向上とコストダウンを両立させようとしている。もっと高性能な全固体電池や次世代NCMもあるのに、なぜトヨタはLFPも並行して次世代品に取り組み続けているのか。
それは、かつて自動車用には向かないとされていたLFPの進化のスピードが速く、耐久性やコストを考えると長期にわたってメインストリームになる可能性が高まったとみているためだろう。
先行する中国勢もいっそうの技術革新を狙ってくる。LFPが低密度という原理的な弱点をある程度克服できたのは、ナノテクノロジーを駆使するなどして工夫を凝らしてきたためだ。LFPの進化を巡る競争は、むしろこれからが本番と言えるだろう。
現在、BEVのコストダウンは2010年代の予想よりずっと遅れていて、マスユーザーにとってBEVは依然として買いにくい。進化型LFPが、BEVの価格を引き下げるのにどのくらい貢献するか。日本勢でその嚆矢となるeビターラがいくらで販売されるのかも含め、楽しみだ。
 リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)を58.56kWhぶん搭載したBYD「ドルフィン」長距離型。多くのBEVと異なり、58.56kWhは物理容量ではなく使用可能容量だった Photo by Koichiro Imoto
リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)を58.56kWhぶん搭載したBYD「ドルフィン」長距離型。多くのBEVと異なり、58.56kWhは物理容量ではなく使用可能容量だった Photo by Koichiro Imoto
 ドルフィンのサイズはフォルクスワーゲン「ゴルフ」に近似したものだが後席は非常に広い。長距離版の天井はグラストップが標準 Photo by K.I.
ドルフィンのサイズはフォルクスワーゲン「ゴルフ」に近似したものだが後席は非常に広い。長距離版の天井はグラストップが標準 Photo by K.I.
 定格電圧390.4Vに対して残存率1桁から423Vという高電圧をかけられるBEVを見たのはこの時が初めて。ラフな充電への耐性の高さはLFPの特質のひとつ Photo by K.I.
定格電圧390.4Vに対して残存率1桁から423Vという高電圧をかけられるBEVを見たのはこの時が初めて。ラフな充電への耐性の高さはLFPの特質のひとつ Photo by K.I.
 鹿児島・薩摩半島南端付近にて開聞岳を望む。充電特性がいいと遠乗りへの抵抗感が激減する Photo by K.I.
鹿児島・薩摩半島南端付近にて開聞岳を望む。充電特性がいいと遠乗りへの抵抗感が激減する Photo by K.I.
 ドルフィン標準版。価格は長距離より44万円安い363万円 Photo by K.I.
ドルフィン標準版。価格は長距離より44万円安い363万円 Photo by K.I.
 横浜を出発後、福島・会津若松にてドルフィン標準版を充電中 Photo by K.I.
横浜を出発後、福島・会津若松にてドルフィン標準版を充電中 Photo by K.I.
 低い充電率から定格より高い電圧をかけても大丈夫というLFPの特性は長距離版と同様だった Photo by K.I.
低い充電率から定格より高い電圧をかけても大丈夫というLFPの特性は長距離版と同様だった Photo by K.I.
 低い充電率から定格より高い電圧をかけても大丈夫というLFPの特性は長距離版と同様だった Photo by K.I.
低い充電率から定格より高い電圧をかけても大丈夫というLFPの特性は長距離版と同様だった Photo by K.I.