いずれは海外の鉄道事業者が
ATACSを導入する可能性も
――最初からこうした機能を見越していたのでしょうか。
実はこれは開発当初は全く気付かなかった使い方でした。今までのシステムはバラバラに作り込みをして、全く連携していなかったのですが、技術の進歩で地上のコンピューターと列車がATACSを介して密に連携できるようになり、全体最適や最適分散したら色々なことができるよね、もっとうまくいくんじゃないかとなりました。
なお、ATACSは高性能ATOや将来のドライバレス運転に対応するため、埼京線導入後にフルモデルチェンジを行い、無線装置の伝送速度を倍にしています。
――山手線と京浜東北線の次は、どのくらいで首都圏に広がるイメージですか?
山手・京浜東北線の地上側工事、車両へのコンピューター設置などの改造に5年くらいの時間がかかるので、全線にいつまでにというのは正直、計画できていません。時間はかかるかもしれませんが、広げていきたいという考えはあります。
――地上設備のスリム化はローカル線にも効果が大きいと思います。地方への展開は検討していますか。
ローカル線向けに、ATACSのノウハウを使い、携帯電話を活用することでよりコストダウンを図った踏切制御システムを開発しています。無線式の列車制御システムは効果も大きいことが見えてきましたので幅広い線区に入れていきたいと思っています。
――近年、鉄道事業者間の技術協力が進んでいますが、ATACSも外部へ提供する考えはありますか。
ATACSはもともと国鉄から始まった純国産システムで、日本の鉄道に特化したシステムですので日本の鉄道会社は使いやすいと思います。多くの鉄道会社に使っていただいて、全体的にコストを下げるなど、メリットをみんなで享受できれば業界全体で盛り上がっていけると思います。
――純国産システムですが、海外からも反応はありますか。
そうですね。海外でも非常に高い評価をいただいており、踏切制御システムや安定稼働の実績から問い合わせは増えています。
――将来的には海外の鉄道事業者がATACSを導入する可能性もあるのですね。
もちろんそうですね。規格上は何の問題もなく使えますし、縛りもありませんので将来的には可能性は十分にあると思います。
※2007年頃にERTMS(ETCS)を国際規格化する動きがあったが、JR東日本は「事情は各国で異なるので技術は固定するのではなく発展を許容し促していくようなものにすべき」と反対した。この結果、個別のシステムの機能要求事項を規定するのではなく、システム構築に当たり、必要な無線に関する性能要求事項を決定するプロセスを明確化したアンブレラ規格(ある分野全体の基礎となる重要な規格)の作成に至ったため、ATACSは海外の鉄道にも導入可能である。
◇
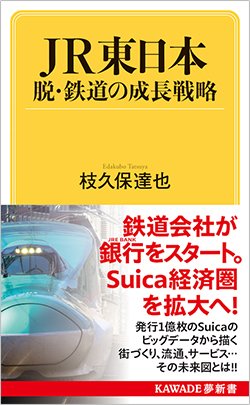 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
無線式列車制御装置を直訳すればCommunication Based Train Control(CBTC)であり、この観点でみればATACSはCBTCの一種としてみなすことができる。ただ概念としてのCBTCの中には規格としての狭義のCBTCがあり、ATACSはこれとは異なるシステムだ。
この辺りがややこしいが、馬場氏がインタビューで述べたように、同じ無線式だがそもそもの目的と成り立ちが異なるというのが分かりやすいだろう。ATACSは軌道回路レスを第一の目標に誕生したが、その拡張性からさまざまな機能を取り込んで「万能」なシステムへと成長したのである。
ATACSが将来、海外へと羽ばたくことにも期待したいが、まずは2028年以降に実用化されるフルモデルチェンジ版ATACSを楽しみに待つとしよう。







