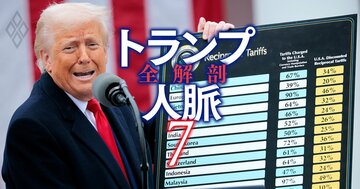立場が三者三様のため、日本側は誰に照準を合わせばいいかわからず、まとめようにもまとめられないという状態に陥っている。
だが、これは第一次トランプ政権でも使われていた戦術だ。立場の違う窓口を使って相手を翻弄して追い詰めた上で、最終的にトランプ大統領自身が出ていってアメリカ側に有利な合意を勝ち取るというやり方だ。
ただ、日本側の複雑な意思決定も大きなネックになっている。
日本側は外務省、経産省、農水省、財務省などの複数省庁が関わっており、それぞれの省庁が「省益」を主張するために意思決定に時間がかかる。窓口は赤澤大臣に一元化されているものの、決定権があるわけではないので、結局、毎回交渉課題と、それぞれの「不一致点」を確認するだけに終わってしまう。
石破首相が国会で答弁した
「安全保障を交渉から外す」の愚
再選を決めたトランプ大統領は、80年代当時のアメリカの姿勢を取り戻し、それを包括的に繰り広げている。今回の日米交渉でも、自動車、機械、サービス、農畜水産品まで広範なテーマを網羅したが、結果は「一致点がない」ことの確認にとどまった。
その原因となったのが、石破首相の国会答弁である。
2025年4月21日、参議院予算委員会において、石破首相は「在日米軍駐留経費負担などの安全保障面とは、貿易・関税の交渉は分けて議論しないとおかしくなる」と述べ、経済と安全保障をリンクさせることを否定。「安全保障の協力も提案対象ではあるが、関税協議にそれを結びつけてはいけない」と明言してしまったのである。
これは、これまでの日米交渉の蓄積を無にする発言だった。
石破首相は「早期合意を優先するあまり、国益を損なってはならない」と強調し、「粘り強く、互恵的な合意を目指す」と繰り返している。しかし、この「互恵的」や「win-win」という表現自体が、交渉の実体から乖離している。
トランプ大統領にとって、貿易交渉とは「アメリカの利益」を他国から引き出すための戦いの場である。そこに「誠意」や「対等な関係」などという耳心地がいいだけの抽象概念を持ち出しても、交渉は1ミリも動きようがない。
それが端的に表れたのが、今回の「相互関税」の仕組みだった。その算出の決め方は、次のようにきわめてシンプルなものだった。
(貿易赤字 ÷ 輸入額)÷ 2
たとえば、日本との貿易赤字が約10兆円、輸入額が21.4兆円とすると、10÷21.4=約46%。この半分である23%が、相互関税として課される。
トランプ大統領が求めているのはこの「対日赤字10兆円」の削減であり、その実現に貢献できる提案でなければ意味がない。抽象概念で美辞麗句を並べ立てたところで、また、繰り返し訪米して誠意を示したところで、ほとんど無駄でしかない。
交渉において大事なのは、相手の思考枠組みを正確に把握することである。トランプ大統領にとって「成果」とは、目に見える数字や取引であり、「友情」や「共通の価値観」ではない。ここを読み誤れば、どれほど真摯な態度を示そうとも交渉は進まない。