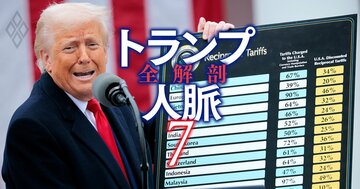4月7日、両国は電話による首脳会談を設定して、石破茂首相がトランプ大統領に撤回を要請したが、“例外的大統領”がこの例外的政策についての姿勢を崩すことはなかった。
多くの日本側関係者がアメリカ側の強硬姿勢に身を固くしたようだが、石破首相もそうだったのかどうか。
トランプ大統領の強圧的な交渉スタイルにいかに対応するかが問われている場面で、わざわざ両国首脳が話し合う貴重な機会を交渉内容の確認だけに終わらせたことは残念でならない。
5月1日から始まった閣僚級交渉には、日本側から赤澤亮正経済再生担当相、アメリカ側からUSTR(通商代表部)のジェミソン・グリア代表が出席した。
1980年代、バブル期のジャパンバッシングを経験している人たちは、このUSTRという組織に耳なじみがあるかもしれない。
バブル期の日本企業は自動車や家電などをアメリカに大量に輸出して対米貿易黒字を計上し、アメリカ製造業が空洞化する懸念から政治的圧力が高まった。アメリカは貿易のルール変更を繰り返して日本を翻弄(ほんろう)し、1989年4月18日にスーパー301条を発動して、日本の中心産業を徹底的に攻めた。
これは1985年のプラザ合意とともに、その後のバブル崩壊と「失われた30年」のきっかけとなっている。
当時のスーパー301条では、日本の衛星、半導体、木材市場などが名指しされ、USTRが一方的に制裁対象を決定できる体制がとられた。これはWTO体制の根幹である多国間ルールとは相いれない「一国覇権的」手法だったが、日本は強く抗議しつつも、いくつもの市場開放を強いられる羽目に陥った。
トランプ流交渉術に
翻弄される日本
だが、日本側はトランプ流交渉術に一方的に翻弄されるだけだった。
日本側が関税交渉を赤澤大臣に一元化しているのに対して、アメリカ側はスコット・ベッセント財務長官、ハワード・ラトニック商務長官、そして先述したグリアUSTR代表と3つの窓口がある。
当初はベッセント財務長官との交渉で、交渉はスムーズにおこなわれる空気があったが、立場の違う2人が加わったことで、日本側は翻弄されることとなった。というのは、アメリカ側の3人は明らかに考え方が違っているのである。
ベッセント財務長官は、市場へのインパクトを考慮して、貿易の公平性に比重を置いている。日本としては最も立場が近く、知日派であることから、一致点が見いだしやすいと思えた。
だが、ラトニック商務長官は、自動車や鉄鋼などの重点分野における関税引き下げを断固として拒否しており、日本バッシングの頃をほうふつとさせるような強硬さで、日本に譲歩を迫り続けている。
また、グリアUSTR代表は、広範な合意とスピード感を重視して、日本に対して早期の包括的な譲歩を迫っている。