外交・安全保障(6) サブカテゴリ
第10回
2015年を予想する上で、ポイントは何か。戦後70年の節目、増税再々延期、集団的自衛権、日中関係、原油価格の暴落……。経営者、識者の方々に、15年を読み解くための5つのポイントを挙げてもらった。第10回は軍事ジャーナリストの田岡俊次氏。

第554回
集団的自衛権の行使に反対の立場をとる元防衛官僚・内閣官房副長官補の柳澤協二氏のインタビューの(下)。柳澤氏は安倍政権の抑止力に対するシナリオは楽観的に過ぎ、集団的自衛権を強調することは日本の安全にマイナスと分析する。

第554回
昨年7月、安倍内閣は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に踏み切った。今年はその実行に向けて法整備の行われる重要な年だ。そこで意見を異にする2人の専門家に論点と賛否を聞き、4回にわたって掲載する。第1回は、元防衛官僚・内閣官房副長官補の柳澤協二氏。

第45回
今年は終戦から70年に当たる。この間、日本は戦闘で1弾も発射せず、1人の戦死者も出していない。大きな曲がり角に立つ日本にとって、平和主義がもたらした「奇跡」とも言える繁栄の歩みを振り返ることは、これからの進路を考える上で、ぜひとも必要なことだ。

第4回
2014年は日本の安全保障政策が大きく舵を切った年として記憶されるだろう。安倍政権が、「集団的自衛権行使の容認」を閣議決定したからだ。15年は国会でそれを実行するために必要な関連法が審議される。改めて集団的自衛権の論点を振り返り、整理する。

第44回
オバマ米大統領がキューバとの国交正常化交渉に入ることを発表したことは、世界を驚かせた。キューバに対するこれまでの「封じ込め政策」を失敗と断じ、「抱き込み」に転じようとするオバマ大統領は、キューバ問題をついに収束させる功績を残すことになりそうだ。

第6回
憲法改正や集団的自衛権の行使容認など、安全保障政策についてこれまでの政権とは比べ物にならぬ程のこだわりを見せた安倍政権。国際政治の専門家である添谷芳秀・慶應義塾大学法学部教授は、安倍政権の外交・安全保障政策に点数をつけるなら、39点という評価であった。

第43回
14日の総選挙では、自公合わせて3分の2を超す議席を確保する勢いだと報道されている。もし、その通りの結果になれば、次に控える2016年7月の参議院選挙は、憲法改正の発議に必要な3分の2を取れるかどうかの「天王山」となる。

第533回
シリーズ「ニッポンの安全保障を考える」の最終回では、第2回に引き続き今後の日米防衛協力のあり方を考える上での論点を整理し、最後にアジアの安定化に日本が果たすべき役割は何かを考えていく。
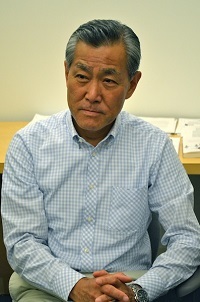
第532回
シリーズ「ニッポンの安全保障を考える」の第2回目。昨年12月に閣議決定された国家安全保障戦略と造営計画の大綱、中期防衛力整備計画に日米安全保障協議委員会での内容を踏まえ、今後の日米防衛協力のあり方を考える論点を整理していく。

第531回
米国のパワーの翳りとともに世界全体に不安定化の兆候が表れつつある。本稿を含めた「ニッポンの安全保障を考える」では、全3回にわたって日米同盟における日本の役割の変化と、今後の日米防衛協力の方向性について考えていく。
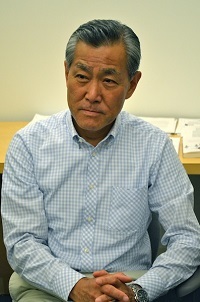
第42回
普天間の辺野古移設反対の知事が生まれても、政府は「粛々と」計画を進めるとしている。その理由は「抑止力として必要」というものだ。だが、沖縄に配備されている米軍海兵隊のあ役割をつぶさに検証すれば、抑止力論が偽りであることがわかる。

第41回
北京で行われた日中首脳会談の意味は大きい。それに先立って発表された合意文書では、巧みな外交表現で両国の妥協点を見出している。今回の首脳会談が中国との敵対関係にずるずると入り込むことを防ぐ第一歩となるなら、安全保障上の成果は極めて大、と言えよう。

第40回
米国は「イスラム国」の問題に対して、当初、不介入の方針だったが、その後、空爆に踏み切り、いまや地上部隊の派遣すら議論されている。かくのごとく戦いは始まれば大体はエスカレートするものだ、という平凡な事実を認識しておく必要がある。

第502回
長年、感染症と闘ってきた三大感染症対策基金、グローバルファンドのトップである、マーク・ダイブル事務局長に、三大感染症の現状と課題、さらに、エボラ出血熱に対する同機関のアプローチについて話を聞いた。

第39回
日米両政府は10月8日「日米防衛協力のための指針」改定の中間報告をまとめた。報告では「同盟のグローバルな性質」を強調。もしこの中間報告通りに「指針」を改定するなら、その前に安保条約の改定が必要なはずだ。

第38回
米軍は9月23日、「イスラム国」のシリア領以内の拠点に対する航空攻撃を開始した。おりしも日本政府は7月1日、集団的自衛権による自衛隊の国外での武力行使を認める閣議決定を行った。「イスラム国」との戦いに自衛隊を派遣することは可能なのか。

第37回
突如、ウクライナの停戦合意が成立しする一方、米国は中東で勢力を伸ばす「イスラム国家」のシリア領内の拠点を攻撃することを決定した。「敵の敵は味方」は戦略・国際政治の不易の原則とはいえ、この2大事件はその複雑怪奇さを我々の眼前に示した。

第68回
池上彰さんのコラムを掲載拒否した、と聞いて「なんてバカなことを……」と絶句した。なぜ、こんな愚挙を犯したのか。朝日新聞で記者教育を受け、定年まで取材現場にいた立場から、社の体質と、それを取り巻くメディアの構造問題を考えてみた。
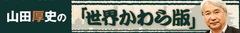
第36回
国連が日本政府に対しヘイトスピーチ(憎悪表現)に、法的規制を勧告する最終見解を発表した。だが、法律はその立法主旨と違う目的に活用されることもある。「言論の自由の確保」を両立させるために、どのような条文の法案を作るのかを考えてみたい。
