中野剛志
日本経済が成長しなくなった、あまりにも「残念」な理由
「積極財政は単なるバラマキ」「財政出動はカンフル剤に過ぎない」などの言説が、日本では主流だ。しかし、2010年代のアメリカでは経済政策の考え方に大転換が起き、これらの言説は「古い見解」と見なされるようになり、「積極財政こそが経済成長を生み出す」という「新しい見解」が主流となった。そして、バイデン政権による画期的な大規模財政出動が現実のものとなったのだ。なぜ、そのような大転換が起きたのか? なぜ、「新しい見解が正しい」と言えるのか? 最新刊『変異する資本主義』(ダイヤモンド社)で、アメリカの経済政策の最前線を分析した中野剛志氏が解説する。

中国が仕掛ける「ハイブリッド戦争」に、日本が抵抗できない理由
11月16日、米中首脳会談がオンラインで行われたが、アメリカと中国との対立が緩和へと向かう気配は未だない。むしろ、「対立が顕在化」したと見る向きが多い。戦後70年以上にわたって、我々日本人の多くは「戦争の可能性」を真剣に考えてこなかったが、いよいよそれでは済まされなくなっている。ただし、その大前提として、絶対に押さえておくべきポイントがある。それは「現代の戦争」は「20世紀型の戦争」とは根本的に異なるということだ。どういうことか? 最新刊『変異する資本主義』で「現代の戦争」を深く検証した評論家・中野剛志氏が解説する。

「所得分配」政策こそが、成長戦略である“明白な理由”
岸田首相は当初、「分配なくして成長なし」と強調していたが、その経済政策の路線を「成長なくして分配なし」へと切り替えつつあるという見方も出てきている。この転換は、重大な意味をもつ。なぜなら、近年の有力な経済研究の成果が示すとおり、「分配」こそが「成長」の礎になることは明らかだからだ。そして、「分配なき成長戦略」こそが経済低迷を生み出してきたからだ。なぜ、そう断言できるのか? 本日発売の最新刊『変異する資本主義』(ダイヤモンド社)で、世界最先端の「成長戦略」の動向を分析した中野剛志氏が解説する。

「バラマキ批判」の中身がスカスカである“根本理由”とは?
与党が経済対策の一環として現金給付を検討しているが、これを「バラマキ」と呼んで批判する声が多い。矢野・財務次官が、日本は財政破綻に向かっていると警告し、大規模な経済対策や消費減税といった与野党の政策論を「バラマキ合戦」と批判したのも、記憶に新しい。このように「バラマキ」とは、財政出動を批判する際の常套句となっているが、これは単に「バラマキ」というレッテルを貼っているだけで、驚くほど中身のないスカスカの批判にすぎない。なぜそうなってしまうのか? 最新刊『変異する資本主義』(ダイヤモンド社、11月17日発売)で、世界最先端の財政論争を分析した中野剛志氏が、日本における「バラマキ論争」が不毛に陥る理由を解説する。

日本の「財政再建」を妨げているのは、矢野財務次官である
矢野康治・財務事務次官の「バラマキ批判」論文に、多くの大手メディア、財界人、経済学者が同調している。その論調は、まるで政治家たちが、有権者の票を目当てに財政出動を約束し、国家財政を危うくしているかのような印象を与えている。しかし、実は、アメリカの有力な主流派経済学者たちの政策論は、矢野次官らが「バラマキ合戦」と嘆いた政治家たちの政策論に近いのだ。彼らの主張がいかに“時代遅れ”で、錯誤に満ちたものかを解説する。(評論家・中野剛志)
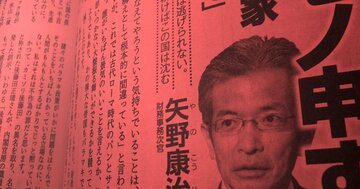
矢野康治・財務次官「論文」、誰も指摘しない“あまりにもヤバい”問題の本質
矢野康治・財務事務次官の「論文」が大きな話題となっている。官僚が政治家に対して異論を唱えたことを問題視し、更迭を求める声もある。しかし、この「論文」は、そんなことよりもはるかに重大な問題をはらんでいる。積極財政論者のみならず、健全財政論者であっても批判すべき、“あまりにもヤバい問題”とは、何か?
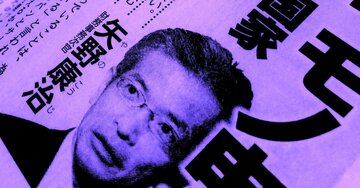
“新しい戦争”を勝ち抜くためにアメリカは「反緊縮」へと大転換した
バイデン政権が前代未聞の巨額財政出動に動いている。3月12日に200兆円規模の「大型追加経済対策」を成立させたうえに、3月31日には、さらに200兆円超を投じる「成長戦略」も発表。直近まで支配的だった緊縮財政から、一気に積極財政へと舵を切ろうとしている。そして、その論拠は、新型コロナウィルスと中国という脅威に対抗する「戦争」である。「まず戦争を戦うことを考えよ。どう戦費を調達するかを考えるのは、その次だ」と、リベラルな経済学者もそれを支持。米国では「経済政策の静かな革命」が確実に進んでいる。日本はどうするのか? 決断に残された時間は少ない。

世界は変わった!「大きな政府」へ舵を切ったアメリカ、日本はどうする?
アメリカのバイデン政権は3月12日、巨額の「財政赤字」を計上する200兆円規模の追加経済対策を成立させた。さらに、それにとどまらず、インフラ投資などに重点を置いた第二弾の経済対策によって、長期的な経済成長を目指す計画だという。この政策をめぐって、アメリカの経済学者は「何」を論じているか? それを概観すれば、アメリカが明確に「大きな政府」を志向し始めたことがわかる。アメリカはすでに、「財政赤字の拡大」を恐れて増税議論を始める経済学者すらいる日本とは、まったく違う「道」へと舵を切ったのだ。

バイデン政権が「新自由主義」を捨て、「経済ナショナリズム」へと大転換する理由
アメリカは、かつてのグローバル覇権を失い、中国の脅威に晒されている。そんななか成立したバイデン政権は、アメリカをどこに導こうとしているのか? それを探るうえで、注目されるのが、大統領補佐官(国家安全保障問題担当)に登用されたジェイク・サリバンである。彼は、「経済学」と「地政学」は本来密接な関係にあることを示したうえで、ここ何十年も支配的なイデオロギーであったいわゆる「新自由主義」を克服すべきであると主張している。そこから、何が見えてくるのか?

「尖閣」陥落は秒読み? とっくに“レッドゾーン”に突入している「日本の安全保障」
11月24日の日中外相共同記者会見における王毅外相の「尖閣諸島」に関する発言と、その場で反論しなかった茂木外相に対する強い批判が巻き起こったのは当然のことだった。しかし、問題の本質はそこにはない。直視しなければならないのは、中国が爆発的に軍事力を強化した結果、東アジアにおける軍事バランスが完全に崩壊したことだ。アメリカが、東アジアにおける軍事的プレゼンスを維持する「能力」と「意志」を失いつつある今、この10年を無策のまま過ごしてきた日本の地政学リスクは、明らかにレッドゾーンに突入した。日本は、あまりに過酷な現実に直面している。

「消費減税」で政局!? コロナ禍における「消費減税」が経済政策の常識である明白な理由
「コロナ禍」は収束の目処が立たないばかりか、戦後最悪と言われる世界的な大不況をもたらしている。恐るべき不況に陥っていることを示す経済指標は、これから次々と明らかになるだろう。そんななか、景気対策として、ドイツ、イギリス、ベルギーなどは消費税減免を実施。日本でも、「消費減税論」が、コロナ禍で動揺する政局の行く末を左右する問題となりつつあるようにも見える。一方で、減税論はポピュリズムに過ぎないという声も多い。どう考えるべきなのか、評論家の中野剛志氏に論じていただいた。

コロナの感染防止で国民の合理的判断に行動を委ね経済活動を規制しない「集団免疫」戦略は、その理論の非現実性ゆえに失敗した。それは、90年代以降、支配思想だった新自由主義の終焉を暗示する。

人為的に準備されつつある「コロナ恐慌第二波」に最大限の警戒が必要である
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は抑制されつつあり、感染第二波も見据えた慎重な「出口戦略」が模索されているが、世界恐慌以来最悪と言われる「コロナ恐慌」が本格化するのはこれからだ。しかも、「恐慌第一波」が回復したあとに襲来する「恐慌第二波」のほうが破壊的であることは、世界恐慌の歴史が証明している。ところが、現下の日本政府の動きからは、「残念ながら、『恐慌第二波』が襲来する可能性は、高いとみるべき」と中野剛志氏は危惧する。その理由を論じていただいた。

「コロナ不況を機にゾンビ企業を淘汰」という説が、日本経済を壊滅させる「危険な暴論」である理由
コロナ危機によって、多くの企業、特に中小企業が倒産や廃業の危機にさらされるなか、「これを機に、ゾンビ企業は市場から退場させ、新時代を創造する」といった声が上がり始めている。しかし、この「ゾンビ企業」論は、コロナ危機で窮地に立たされている人々を追い詰めるのみならず、「日本経済を壊滅させかねない極めて”危険な議論”である」と中野剛志氏は批判。その根拠として、「ゾンビ企業」論の6つの問題点を指摘する。

第13回
この残酷な世界を「普通の国民」が生きるために、絶対に知っておくべきこと
「国家」から目をそらすと、「資本主義」を正しく理解することができない。中野剛志氏はそう指摘する。ヨーロッパ各国が戦争を繰り返すなかで、試行錯誤をするうちに、知らず知らずのうちに、貨幣制度も中央銀行も資本主義も、そして国家すらも生み出されてきたからだ。この冷徹な現実を見据えることによってこそ、残酷な世界で「普通の国民」が生きていくための「国家戦略」が見えてくるという。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

第12回
この生きにくい「資本主義社会」を救出する唯一の方法とは?
主流派経済学は、「現実世界」とはかけ離れた理論体系をつくり上げてきたために、「現実の経済で起きている現象」を正しく説明することができなくなっている。むしろ、主流派経済学から「異端」とみなされてきた、ケインズやハイマン・ミンスキーらの経済学こそが、この生きにくい「資本主義社会」を救出する方法を提供してくれると、中野剛志氏は語る。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

第11回
なぜ、「経済政策」はいつも間違えてしまうのか?
アメリカの覇権パワーが凋落し、世界経済が縮小へと向かうなか、日本がたしかな国家戦略を立案するためには、「経済力と政治力・軍事力との間の密接不可分な関係を解明する社会科学」の確立が欠かせない……。その問題意識のもと中野剛志氏は、『富国と強兵 地政経済学序説』で地政経済学を提唱した。ただ、現在の主流派経済学では、政治学や地政学、歴史学などとの接続が不可能だという。何が問題なのか? 語っていただいた。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

第10回
世界はすでに、各国が「利己的」にならざるを得ない危険な状況に陥っている
「いま世界は極めて危険な状態にある」と中野剛志氏は指摘する。アメリカの覇権パワーが衰退するとともに、リーマンショック以降、世界経済は停滞に向かっていたうえに、コロナ禍で世界経済は大恐慌以来の景気悪化になると予測されているからだ。にもかかわらず、日本はいまだに冷戦構造下の国家政策に安住しようとしているのは危険すぎる。この問題意識から、中野氏が『富国と強兵 地政経済学序説』で提唱するのが地政経済学の確立だ。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

第9回
「コロナ禍」でさらに緊張が高まる、日本を取り巻く国際政治の“残酷な真実”
アメリカの覇権パワーが音を立てて崩れるなか、2000年代以降、日中の軍事力の格差は、飛躍的に拡大した。戦争を避けるためには、このような勢力不均衡をつくってはならなかったと中野剛志氏は指摘する。しかし、いまの日本では、財政担当は国防よりも目先の財政健全化を優先し、国防担当は「財政的に無理」と言われると反論できないのが実情。そのため、日本は非常に危険な状態にあると言わざるを得ないという。しかも、コロナ禍で各国が「自国中心主義」にならざるを得なくなっており、日本を取り巻く状況は厳しさをましていると指摘する。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)
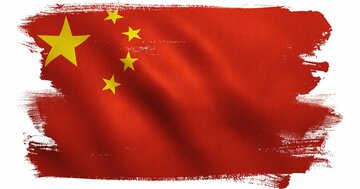
第8回
「グローバル化すべき」と言う人が、完全に“時代遅れ”である理由
「グローバル化」はとっくに終わっている――。アメリカがグローバル覇権国家でなくなった現代において、グローバル化が終焉を迎えるのは当然の帰結。「グローバル化は不可逆の流れ」などと考えるのは、むしろ危険だと中野剛志氏は話す。いま世界の底流で何が起きているのか? 中野氏に解説してもらった。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)
