浅川澄一
第77回
この4月から全国の市町村自治体で介護保険の「新総合事業」が始まった。現行の介護保険制度では、財源難と人手不足が深刻になるめ、自治体に一部サービスの運営を委ねることにしたものだ。運営基準などを個々の自治体が決める。全国一律の介護保険制度からの大転換である。
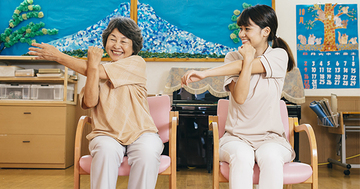
第76回
高齢化率が20.6%という上海市の状況は相当に深刻だ。「介護へのニーズがかなり広がっている」と上海市の担当者が話す。上海市内の高齢者施設は702カ所、全ベッド数は13万2000。これからは、「地域に密着した小さな規模の事業所作りに力を入れたい。住宅地の中で訪問介護を拠点とし、デイサービスやショートステイも手掛ける形にしたい」という。

第75回
高齢化が進むアジア諸国。なかでも人口規模が圧倒的に大きい中国がどのような動きをしているかは、関心事である。昨年と今年に訪れた北京と上海での高齢者ケアの現場を振り返ってみた。従来型の大規模施設だけでなく、地域住民向けの斬新な活動が少しずつ芽生えている。

第74回
介護保険制度の中で、かつて「認知症ケアの切り札」と言われ脚光を浴びていた介護サービス「グループホーム」が一向に話題にならない。かつて、介護保険のスタート時には、最も注目された認知症サービスであり、その広がりに官民挙げて力を入れてきたのに、なぜ今、後方に追いやられているのか。

第73回
財政破綻で注目された夕張市では、全国的にも「画期的」なことが起きつつある。マイナス面ばかりが強調される中で、日本の将来を先取りするような、まことに先駆的な事実が着々と広がっている。高齢者の終末期、看取りについてである。それは「生」を充足させたうえでの「死」に臨む考え方である。

第72回
介護保険のサービスと介護保険でないサービスを組み合わせて提供する「混合介護」の解禁が近づいて来た。2月21日に政府の規制改革推進会議が「公開ディスカッション」を開き、同会議委員たちが厚労省の4人の課長と審議官たちに「なぜ、認めないのか」と迫った。防戦に必死の厚労省側だったが、委員たちが提案する国のガイドライン(指針)作りには、及び腰しながらも完全な否定姿勢を採ることはできなかった。同会議は、今後、厚労省にガイドライン策定を求めていくとともに、6月にまとめる答申に盛り込む。

第71回
国が「自立支援介護」の内容を明らかにし、その方向で動き、結果を出した自治体に交付金という名のご褒美、奨励金を渡すことにした。遂に、「自立支援介護」が「錦の御旗」となって登場したと言えるだろう。要介護度の改善や給付費の削減が、本当に介護保険法の本旨であろうか。

第70回
介護事業者のアジア進出を政府が全面的に後押ししようとしている。進出国でその介護サービスへの評価が高まれば、日本に就労や研修で人材が送り込まれ、介護現場の人手不足の解消につながる。相手国には日本からの優れた介護技術が根付き、日本でのキャリア形成の道が拓け、日本では深刻な状況に陥っている介護人材の安定的な確保となる。そんな「ウイン-ウイン」構想が急ピッチで進行中だ。

第69回
外国人介護者への門戸が大きく開放されつつある。十数年前までは考えられなかった。介護現場での人員不足が深刻になり、「介護は日本人で」としていた従来の発想を一変させた。介護分野で今年最大の注目を集めそうだ。

第68回
高齢者介護を巡る家族間の殺人や心中などの事件が多発している。息子や娘が手をかけてしまうことに加え、高齢の夫婦が「老老介護」の末に無理心中の悲劇に至る例も増えてきた。介護保険制度が始まって17年近い。「介護の社会化」が浸透してきたはずなのに、介護専門職や介護事業所の目が十分に届いていない。

第67回
介護保険制度で、利用者の要介護度が軽くなると特別の奨励金を交付する自治体が増えてきた。「成果主義報酬」の導入である。同様の試みを国が新たな制度として導入しようとしている。これは本当に要介護者のためになるのか?

第66回
上映中のフランス映画「92歳のパリジェンヌ」は安楽死を選んだ老婦人の物語。老婦人の心の中に分け入り、忠実にたどった映画に感銘を受けた。これほど人生の終止符の打ち方を考えさせる映画はなかったと思う。欧米の映画では安楽死がよく出てくるが、日本ではどうなのか。

第65回
病院は暮らしの場だろうか。病院に長く滞在したいだろうか。入院期間はできるだけ短く、と言うのが普通の人の普通の思いではないのか。ところが、病院の運営者はどうも違うらしい。そんな疑問が沸いてくるような「事件」があった。

第64回
3年に一度の改訂期を再来年に迎える介護保険制度。厚労省の社会保障審議会・介護保険部会がほぼ隔週ごとに開かれ、急ピッチで委員の意見表明が成されている。2000年4月に制度が始まって以来の大幅な見直しとなると言われるが、どのような雲行きなのか。現状を点検した。

第63回
訪問介護のヘルパーが、要介護者のために夕食を作る際に、帰宅の遅い同居家族の分も同時に作れば、どんなに介護家族が助かるだろうか。誰しも思うことだろう。家族の分のサービスは介護保険外だから別途請求することになるが、現在の介護保険ではこうした臨機応変な対応は禁止されている。介護保険サービスは要介護者にしか提供してはならないからだ。

第62回
住み続けてきた住宅で最期まで暮らしたい。どんなに重度の要介護状態になっても馴染んだ生活が一番いい。医療器具に囲まれた殺風景な病室で看取られたくない。自宅が無理なら自宅と同様な生活ができるケア付き住宅で――――誰しもが願う老後のあり方だろう。

第61回
介護と保育の支援サービスは共に、共働き家族が仕事を続けるには欠かせない仕組みである。小さな核家族だけでは十分な対応は難しい。社会の手助けが必要とされる点では変わりがない。家族労働から「社会化」への道筋が必要だ。

第60回
介護職の低賃金が問題となっているなか、あらゆる職業に適用される最低賃金が新しく決まり、全国平均で前年より24円、3%引き上げられ822円になった。これまでにない最高の上げ幅だ。3%アップは安倍首相の強い要請による。自民党の首相が率先して労働者の賃金アップに乗り出すのは異例と言っていい。なぜなのか。

第59回
介護現場で見逃してはならないならい日本特有の遅れた介護手法が残っている。「抱き上げ介護」である。高齢者をベッドから車いすに移譲する時、車椅子からトイレの便座に移す時、あるいは入浴時に「せーの」「イチ、ニ、サン」「よいしょ」と声を発しながら持ち上げて下ろす力仕事だ。

第58回
米国が発祥のCCRC(Continuing Care Retirement Community)を米国東部海岸で見てきた。ボストン、その隣のケンブリッジ、そしてニューヨークの北のコネチカット州などで5つのCCRCを回った。そこで見えた、米国特有の高齢者ケアの特徴とは。
