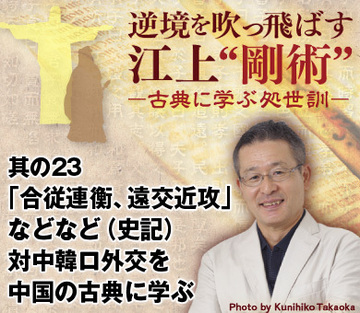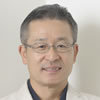
江上 剛
第42回
政治家が、その言葉で失敗したり、問題をおこすことは古今、数多い。最近の日本でも、安倍首相、猪瀬東京都知事、そして橋下大阪市長がその発言を問題にされている。政治家はどのような心構えで、「言」を発すべきかを考えてみよう。
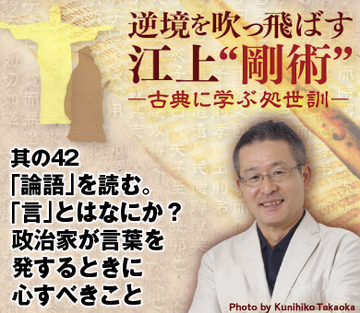
第41回
安倍首相が活発な外交を展開し、成果を収めつつあるように思える。優先順位は間違っていない。何をやってもうまくいっている時こそ、『君たること難し、臣たること易からず』という姿勢で臨んでほしい。
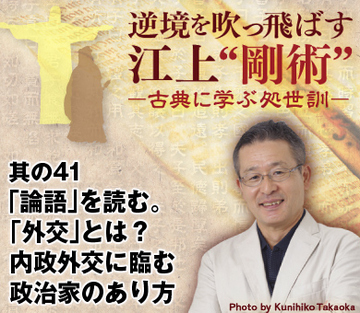
第40回
人は死ぬ。死ぬとは別れだ。残された者は、どうすればいいのか。孔子も最も期待した弟子を失い、わが身の滅亡というほど嘆き悲しんだが、その後も悲しみを乗り越えて道を求め続けた。その言葉は「新しい生を生きよ」と教えている。

第39回
北朝鮮の金正恩が暴走している。今にも核ミサイルを日米韓に発射せんばかりだ。孔子はは政治に関する言葉が多い。これはそのまま金正恩に聞かせてやりたいが、私たちの生活や企業経営にも役立つ内容だ。
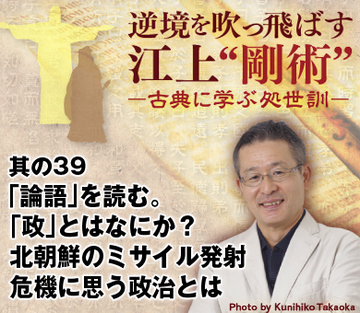
第38回
岩手県山田町で活動しているNPO法人が、震災の緊急雇用創出事業資金約8億円を使い切り、被災者の雇用を打ち切るというニュースが流れた。被災者の信頼を裏切ったのだが、この「信」とは何か?それは「人」と「言」であり、人の言葉ということなのだ。
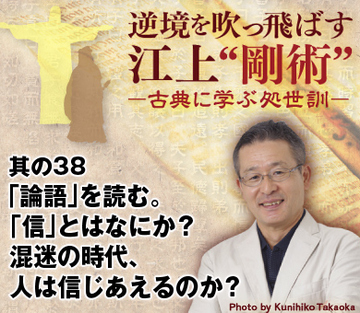
第37回
アベノミクスを先取りして株や不動産価格が上がり始めた。今度のバブルは、さまざまな格差の拡大を通して、国民を完全に二分するかもしれない。そんな時代に私たちはどんな生きる道を模索すればいいのか。
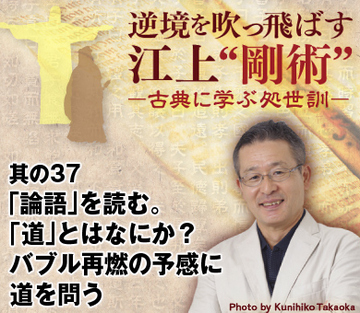
第36回
相変わらず追い出し部屋の記事が目につく。東証一部上場の大企業でもあっても、追い出し部屋などをつくる企業は「仁」に欠ける。まさに「巧言令色企業」、「仁義な企業」である。
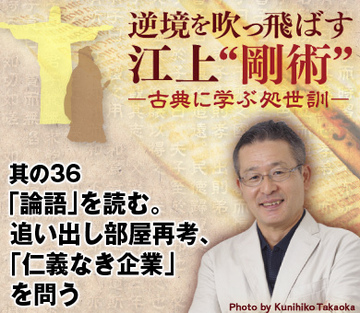
第35回
教育の現場、特にスポーツ指導の現場で体罰が常態化していたことが明らかになってきた。なぜ指導者たちは体罰に走るのか。「論語」によれば、学ぶことに師弟という関係はない。
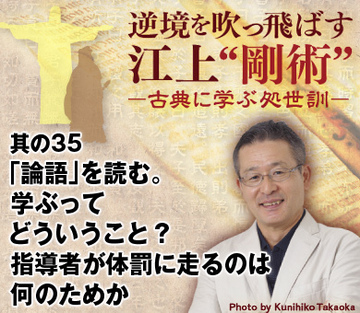
第34回
若いときにはは、無性に悲しくなったり、誰かに裏切られたり、会社で認められず悔し思いするときも多いだろう。その時、荘子の言葉に耳を傾ければ、ふっと気持ちを楽にしてくれるはずだ。
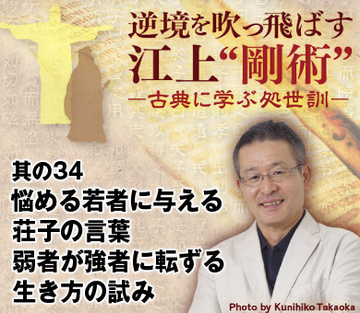
第33回
去年の年末に朝日新聞一面に「追い出し部屋」の記事がどーんと掲載された。退職に追い込む非道な手段だが、もし自分がリストラ対象者になったときの心の持ち様を、孔子、孫子、老子から学んでみよう。

第32回
アベノミクスとやらで一転して世の中は浮き立っているが、景気が回復するほどサラリーマンの悩みは深くなるだろう。年の初めに、論語の真髄ともいえる言葉から、現代のサラリーマンの心の持ち様を考えてみよう。
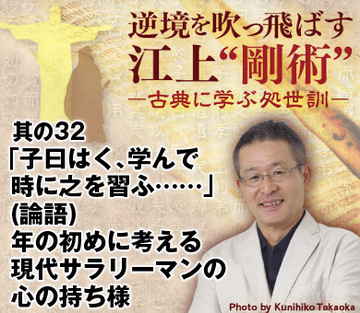
第31回
総選挙は自民党の圧勝に終わった。間もなく安倍晋三自民党総裁が首相に返り咲く。そこでドラッカーが掲げるリーダーの条件を基に、新首相のあるべき姿を考えてみたい。
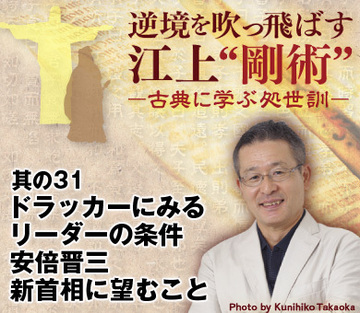
第30回
最近の若者の悩みを聞いていると、総じて傷つき易いし、傷つきたくないと思っていると感じる。失敗したくないという気持ちも強い。マラソンの経験のとキリストの言葉から、悩める若者に与える言葉を拾い出してみよう。
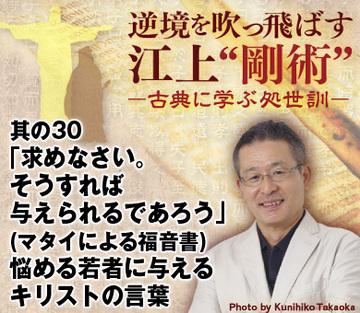
第29回
ある雑誌社から来年のキーワードは何かと問われて、月並みながら「イノベーション」と答えた。イノベーションと言えば、経営学の泰斗ドラッカーだろう。彼がイノベーションをどう捉えていたかをみてみよう。
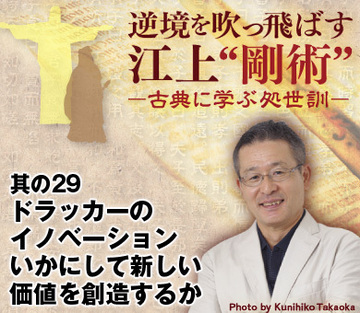
第28回
日本を代表する大企業の経営不振が続いている。では、どうやって再建に取り組めばいいのか。みなさんは早川種三という人を覚えているだろうか?「再建の神様」と言われた早川の言葉・姿勢には学ぶべき点が多い。
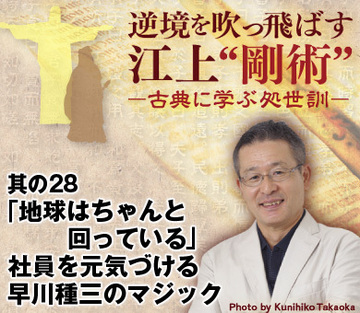
第27回
最近、モチベーションを上げるためにはどうしたらいいのかと聞かれた。私自身の支店長経験と「孫子」「史記」から、いかに部下や自分自身のモチベーションを上げるかを考えてみたい。
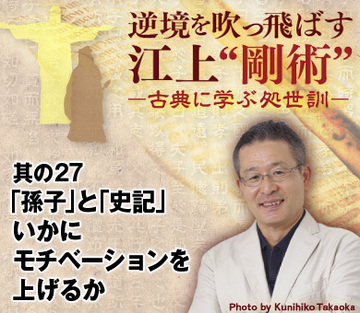
第26回
就職難が原因で自殺する若者が増えている。あなたは自分が弱いからといって、深刻になる必要はない。あなたにふさわしい出会いを求めれば、水が岩石を動かし、山を崩すように大きな仕事が、きっとできる。
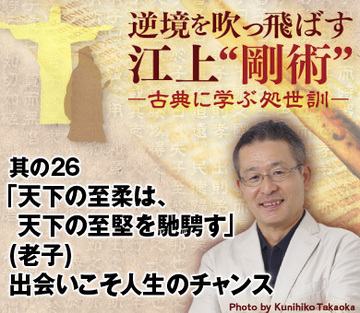
第25回
我が国の非正規雇用比率は、いまや男性が20.1%、女性は54.6%。若い人も、そうそう親のすねをかじってばかりもいられない。せめてなりたや正社員というのが、若い人の本音だとすれば、今回は混迷の世の生き方を考えてみたい。
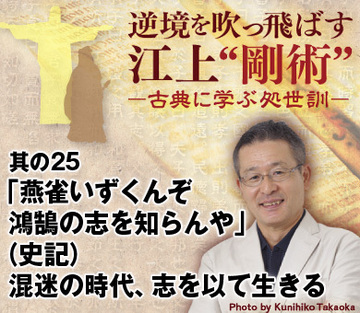
第24回
9月10日から一週間は「自殺予防週間」だ。日本は自殺大国。余程、この国が病んでいるという証拠だろう。山田風太郎氏が著した『人間臨終図巻』を手掛かりに、自殺について考えてみる。
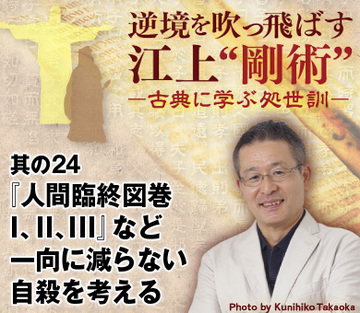
第23回
韓国のイ・ミョンバク大統領が、竹島に上陸するは、中国人が大挙して尖閣諸島に上陸を果たすは、日本列島を囲む四海波高しという状態になってしまった。では、日本はどのような外交を展開したらよいのか。中国の古典「史記」にそのヒントがある。