
小林俊介
日本の低成長と高インフレ、諸悪の根源は人口動態、少子化対策に全力を挙げよ
日本経済を悩ませる人手不足を単なる人口減少だけで説明することはできない。少子高齢化によって食べる口はあまり減らず、作り手だけが激減している。需給バランスが崩れ、人手不足が常態化しているのだ。
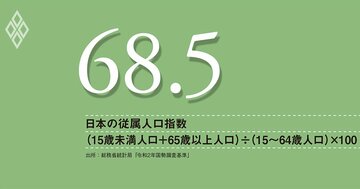
財政健全化の真の敵は、金利のある世界ではなく、制御不能なインフレだ
日本経済はインフレの世界に突入した。これはすなわち、「金利のある世界」への突入を想像させる。しかし、金利上昇に伴う利払い費の増加を通じて、財政の持続可能性が低下すると結論付けるのは早計だ。

米雇用統計のサプライズに要注意、1次集計と季節性にわな、不法移民のかさ上げ効果も影響
2025年8月1日に発表された米雇用統計は、金融市場にショックを与えた。5~6月分の雇用者数が合計で25.8万人も下方修正され、雇用市場の停滞が突如としてあらわになったためである。
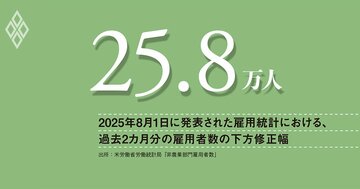
原油価格下落は干天の慈雨、トランプ関税の打撃を相殺、日本は自らの問題に注力を
トランプ関税の陰に隠れながらも、日本経済にとって“干天の慈雨”とも呼ぶべき現象が起きている。原油価格の下落である。
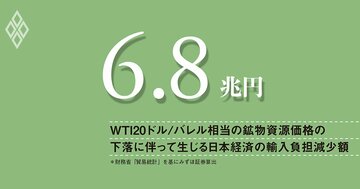
労働者の手取り停滞の真因は低い労働生産性ではない、社会保険料の抑制が急務だ
日本の「手取りの実質賃金」は、四半世紀にわたって停滞を続けている。1時間の労働に対して支払われる手取り賃金は、2000年から23年の間に、わずか0.5%の増加にとどまる。日本の労働者が豊かになれない要因は?

「年収の壁」打破に向けて供給力強化の視点が不可欠、扶養控除制度の改廃が本質
衆議院選挙の結果、与党連立政権は議席数で過半数を割り、国民民主党がキャスチングボートを握る運びとなった。その国民民主党が掲げる所得税減税策が注目を集めている。

ブラックマンデーの再発は金融政策の不確実性も原因、日銀は対話の方法を再考せよ
8月5日、日経平均株価はマイナス4451円と、史上最大の下落幅を記録した。下落の背景は、1987年に発生したブラックマンデーと同様、偏った投資ポジションの巻き戻しとみられている。

円の購買力は歴史的低水準、円安スパイラルを招いた根本要因に対処せよ
円安の勢いが止まらない。ドル円レートは、6月下旬に一時38年ぶりの水準である1ドル=161円台まで下落し、その後も1ドル=160円前後で定着しつつある。

24年の日経平均株価は「最高値更新の日常化」を象徴、日本でも日常風景になるか
2024年2月22日、日経平均株価はついに、バブル絶頂期の1989年12月29日に記録した最高値を更新した。日経平均最高値更新と表裏一体の現象として、デフレ不況は終焉を迎えたのであるが、「賃金と物価の好循環」に直結するかどうかは不透明だ。

失われた30年の諸悪の根源「バランスシート不況」は終焉、舞台は日本から中国へ
日本の「失われた30年」の原因は何か。このテーマはいまだに百家争鳴の状態だ。しかし、「バランスシート不況」に大きな影響力があったことは、広く認められている。

連合の弱気な賃上げ姿勢が日本経済好循環の壁に、組合は賃金交渉を活性化せよ
日本は既にデフレを脱却し、インフレの世界に突入しつつある。しかし、過去30年もの長きにわたって待ち焦がれてきたはずのインフレの到来は、必ずしも歓迎されているとはいえない。

訪日外国人旅行者の消費額は再び目標8兆円が視野に、高単価なサービスへの転換を
日本政府がかつて掲げた「2020年に訪日外国人旅行者数4000万人、消費額8兆円」という目標を覚えているだろうか。実に7年も前のことだが、コロナ禍前のピークの19年時点でも目標までは距離があった。その後、コロナ禍で目標の達成は一気に遠ざかった。しかしここにきて、8兆円という数字が突如として現実味を帯びている。
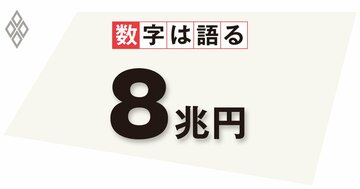
日本の生産性の低さは産業政策の不在のせい?政策の失敗を見直すべきだ
日本は生産性が低い。生産性の伸びも鈍い。成長戦略が必要だ。政策界隈やマクロ分析業界では、耳にたこができるほど繰り返されたフレーズである。日本の生産性は長らく伸び悩んできた。その背景として指摘されるのが、旧態依然とした日本の商慣行や規制の存在、先見性ある産業政策の不在などだ。

需要が失われた30年から供給が失われる30年へ、労働力不足の解消が急務に
過去の記憶として葬り去られつつある「失われた30年」。多くの要因から発生した劇的な需要不足が、日本経済の長期停滞を演出した。今は幸か不幸か、長年の賃金低迷と近年進展した円安の結果として日本人の労働コストが相対的に安価となり、空洞化は止まった。日本経済の問題は成長の天井を規定する供給側に移ったが、実は需要不足の陰で、供給能力の劣化は着実に進展している。

米国を中心に、世界的に金融システム不安が台頭している。米シリコンバレー銀行と米シグネチャー銀行は3月、破綻に追い込まれた。その後、連鎖破綻懸念は一時的に後退したが、5月1日の米ファースト・リパブリック銀行の破綻で新たな懸念が生じた。自力での経営再建が困難な銀行は、当局に救済のはしごを外されるリスクがあることを浮き彫りにした。

新型コロナ検査陽性率の顕著な低下やワクチン接種率の上昇により、米国では「黄金の20年代」再来ともいうべき好景気の到来が見込まれる。かたや日本は、2020年10~12月期の実質GDPが好調だったが、実体経済のV字回復に向けたハードルは、米国よりも高そうだ。日本のV字回復を妨げる真の課題を考える。

先日発表された2020年7~9月期の実質GDP成長率は、前期比年率+21.4%を記録した。史上最悪のマイナス成長となった4~6月期からの立ち上がりで、史上最大級の成長率を記録した格好だ。とはいえ、日本経済の先行きは決して平坦なものではない。今後の命運を左右する「2つの鍵」について考えよう。

安倍総理大臣の辞任を受けた自民党総裁選挙が行われる。情勢は菅官房長官の圧倒的有利となっており、17日に菅政権が誕生する可能性が高い。新リーダーには、アベノミクスが遺したいくつもの「宿題」をこなすことが求められる。取り組むべきポイントは何か。

コロナショックの拡大が続き、世界的な感染者数の増加、実体経済の悪化、金融市場の混乱が連鎖的に進展している。最初の感染者確認から現在までの局面変化を整理し、今後考えなくてはいけない経済・金融面での課題を展望しよう。次の「主戦場」はどこだろうか。

2月17日に発表された2019年10~12月期の実質GDP成長率は、前期比年率▲6.3%となり、リーマンショック以降の数値としては前回増税直後に次ぐ、大幅なマイナス成長を記録した。想像以上の落ち込みの背景と、今後の不確実性を探る。
