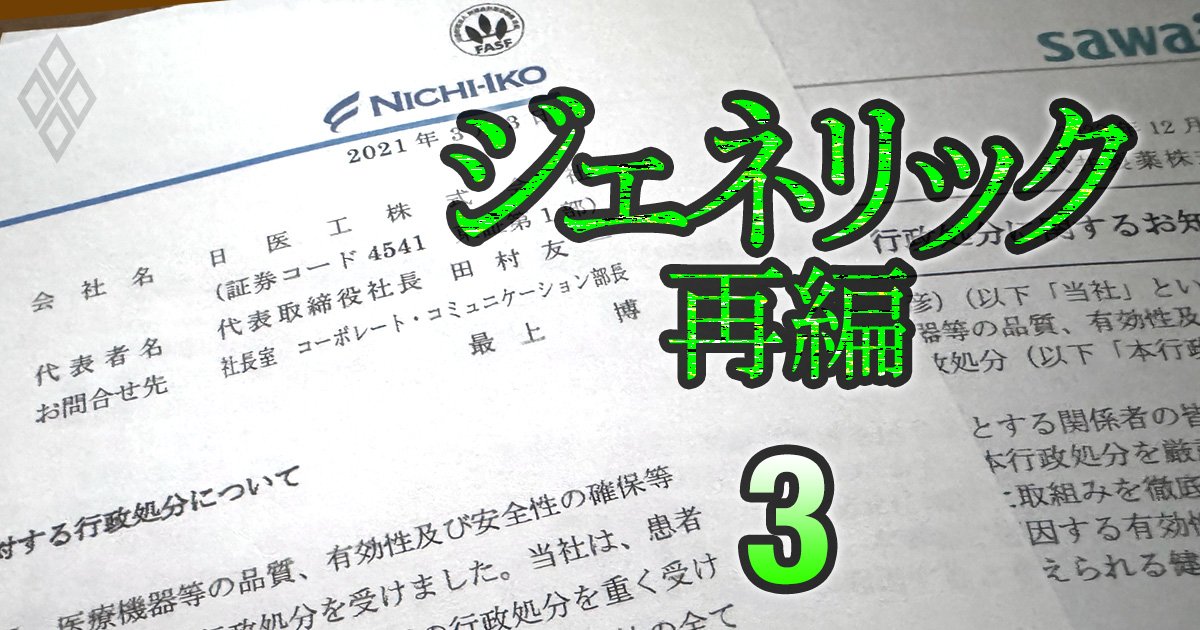いまは余生ではなく本生
自由の身となり住職の道へ
JMASは着実に実績を積み重ね、2006年には念願の地雷処理活動にも踏み出した。活動先はアフガニスタン、ラオス、アンゴラなどへと広がっていった。アフガニスタンなど戦火にさらされた国では、地雷原処理のほか復興支援の役割を担うこともあった。戦後の悲惨さと貧困が満ちた光景を目の当たりにし、「JMASの活動は微力かもしれないが、この国の平和と安寧、さらに復興と繁栄に尽くすことで、必ず波及効果は訪れるはずだ」と信じた。
2007年には理事長の座を退任。「法人組織は社会の財産であり、個人の所有物ではない。規範を示さなければ、社会からの支援は得られない。職務年数に制限をかけるべきだ」との考えから自ら申し出て、ヒラの理事になった。
その後土井氏は、アンゴラの現地代表者の地位に就いた。そもそもJMAS設立当初「無謀」と考えていたアンゴラでの活動を、「土井さんにはアクセルはあってもブレーキはいつも故障している」と半ばあきれられても決めたのが土井氏。内定していた現地代表予定者が土壇場になって家族の反対により辞退し、その後も適任者が見当たらなかったため、やむなく本人自ら赴くことになった。
2010年、68歳の誕生日にコマツを退社し、JMAS理事を退任した日も、いつものようにアンゴラの地で日々の仕事に追われていた。「アンゴラでは地雷処理に関する作業だけでなく、毎日のようにトラブルが発生。理事としての最後の仕事は宿舎にネズミが入ってこないように進入路をふさぐことだった」と振り返る。
日中には気温45度にも達するアンゴラ。人々の考え方も習慣も日本とは大きく違う。そんな環境で、土井氏は戦いを挑む気持ちで現地の人々と接し、日本の技術や文化が現地に根付くよう心がけた。「単に支援するだけでは意味がない。現地の人たちが、自分の手で地雷除去までできるようにならなければ、結局元に戻ってしまうからだ」と話す。
現地では地雷除去だけでなく、地域の環境整備にも注力。週末には現地の子どもたちとサッカーを楽しんだ。多くの現地住民が、土井氏らが日本から持参した松葉ボタンで家を飾るようになった。四年間の滞在で、「少しずつ、日本の心が伝わっていった手ごたえを感じた」と振り返る。
帰国した土井氏は、ほどなくJMASから離れた。以後いまに至るまで、意識して一線を引くようにしている。「JMASの置かれている状況は年々変化している。自分たちの世代が得た知識と経験を基にいつまでも干渉するのは業務妨害でしかない」と考えるためだ。
なお、JMASは設立から20年が経過したいまも各国での地雷処理活動を進めており、これまでに除去した地雷や不発弾は計42万発を超えた。活動が実を結び、支援国での地雷や不発弾のけが人も減少している。
自由の身となった土井氏が選んだのは、故郷・甲府市にある無人寺の住職の道だった。お寺があるのは、独居老人3人しか住んでいない限界集落。「住職となった以上、こういう場所に住んで自分のできることをやるのが責務だろうと考えた」という。住職の職務の傍ら、1000平方メートルにも及ぶ畑を耕し、農業にもいそしむ。買い物には車で片道30分を要するが、「ぜいたくな暮らしをしている」と話す。
これまで人に囲まれ、多くのことを成し遂げてきた。そんな土井氏は、「いまは余生ではなく、本生」と力を込める。これまでの人生すべてが、いまの生活を送るために必要なものだったのだ。
まだまだ、やりたいことはある。その一つが駆け込み寺「一福寺」の創設だ。「もともと女性救済のためにはじまった『駆け込み寺』だが、いまはそんな役割を担う寺は見当たらない。24時間いつでも、誰でも、どんな事情があっても迎え入れ、一服できるような場所をつくりたい」と話す。10月で80歳を迎えた土井氏の挑戦は、これからも続く。