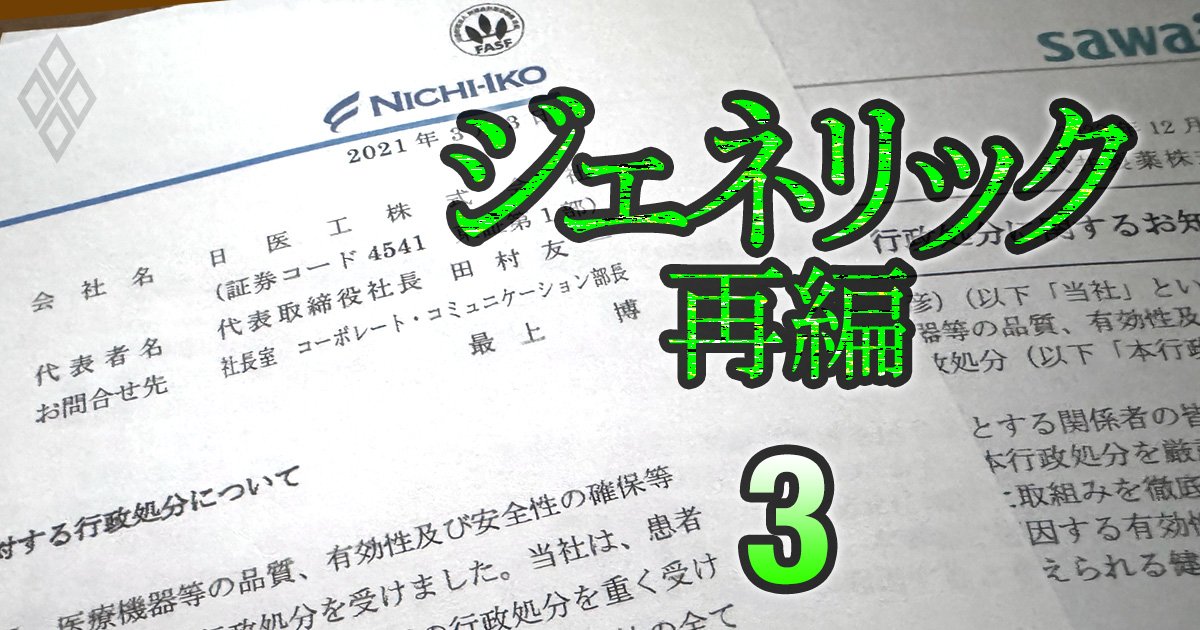古事記の時代から「そこにいるだけ」に
価値を見出す日本人
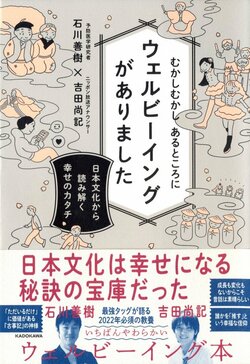 『むかしむかし あるところにウェルビーイングがありました 日本文化から読み解く幸せのカタチ』石川 善樹/吉田 尚記 著 KADOKAWA 1430円(税込)
『むかしむかし あるところにウェルビーイングがありました 日本文化から読み解く幸せのカタチ』石川 善樹/吉田 尚記 著 KADOKAWA 1430円(税込)
石川氏は、日本最古の歴史書である『古事記』をひもとき、そこに「いてもいなくてもいいような神様」がなぜか登場することを指摘する。
例えば、旧約聖書で言えば天地創造に当たる「天地開闢(てんちかいびゃく)」の時に「造化の三神」と呼ばれるアメノミナカヌシ、タカミムスヒ、カムムスヒが現れるのだが、このうちアメノミナカヌシだけは、最初に登場したきり、二度と現れない。
また、アマテラス、ツクヨミ、スサノオの「三貴神」の中で、ツクヨミは「ほぼ何もしない」のだという。
「いてもいなくてもいいのにいる」ということは、逆に考えれば「いるだけで価値がある」ということでもある。この、何かをする(doing)ではなく、いる(being)こと自体に価値を認めるのが日本文化の特質の一つではないかと、石川氏は分析している。
何かを「しなくてはならない」状況から離れ、「いるだけでいい」となった時に、退屈するほど長い時間でなければ、人は「癒やし」を感じるのではないだろうか。それもウェルビーイングのかたちの一つに他ならない。
また石川氏は、日本の昔話や落語に「Nobody」という特質があることを言っている。登場する人物が「何者でもない」ケースが多いというのだ。
日本の昔話は、西洋の童話などと比べて、おじいさんやおばあさん、つまり高齢者が登場することが圧倒的に多い。しかも、「むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました」で始まり、たいていは最後まで名前が明かされない。どこにでもいる「おじいさん、おばあさん」なのだ。
落語にしても、熊さん、八っつぁん、ご隠居、与太郎など、一応は登場人物に名前があることが多い。だがそれは、どこにでもいる庶民の符号でしかない。彼らは、有名人ではない。何者でもない。
ストーリーにしても、西洋の童話や児童文学のように「血湧き肉躍る大冒険」がなされることが少ない。浦島太郎は、どこにでもいる平凡な漁師が、ひょんなことから亀を助け、そのお礼に海中の竜宮城に招待され、飲み食いして帰ったら、白髭の老人になった。それだけの話だ。