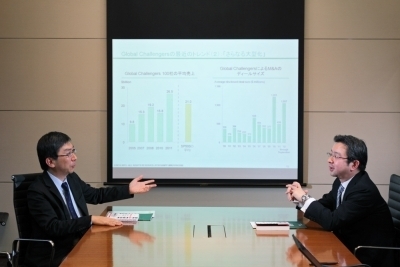新興国市場は、もはや取り組まないほうがリスクとなっている――リバース・イノベーションの視点から見ると、日本勢の新たな活路となるどんな戦略が見えてくるのか。
前回に続き、ボストン コンサルティング グループのシニア・パートナー&マネージング・ディレクターの太田直樹氏と『リバース・イノベーション』日本語版の解説を執筆した慶應義塾大学大学院教授の小林喜一郎氏の対談です。前回明らかになった新興国の企業の躍進ぶりに対し、日本企業がどのような戦略をとれるかを中心に対談は広がります(構成/渡部典子、撮影/矢島幸紀)。
新興国の時間軸や物差しで
動かなければダメ
小林:この20年間、失われた時代やデフレを経て、体力的に落ちてきた日本企業は総じて、業績について非常に短期志向になっています。もちろんギャンブルではいけませんが、長期的な目線を持って、試行錯誤と学習を行っていかないと、いきなりすごいイノベーションは出てきません。
以前イノベーションに関する研究論文で、企業の多角化の度合いを説明する変数の一つに、トップマネジメント・チームの平均在籍年度を用いました。すると、在籍年数が長いほどイノベーション(この場合は多角化)は進むという結果になったのです。実際、GEやP&Gなどの例を見ると、経営陣の腰を据えた取り組みが求められるなと感じます。
 太田直樹(おおた・なおき)
太田直樹(おおた・なおき)ボストン コンサルティング グループ(BCG)シニア・パートナー&マネージング・ディレクター。東京大学文学部卒業。ロンドン大学経営学修士(MBA)。モニターカンパニーを経て現在に至る。BCGフェロー。BCGテクノロジー・メディア・テレコミュニケーション・プラクティスのアジア・パシフィック地域リーダー。BCGソーシャルインパクト(社会貢献)ネットワークのコアメンバー。
太田:確かに(日本の多くの大企業のトップの在籍期間の)4年くらいの任期では難しいですね。既存の意思決定や損益計算書の枠内では、長期的な時間軸でのリスクがとれないとすると、器を分ける、つまり会社を世界の大きな地域ごとに分けるのが一番現実的な答えだと思います。たとえば、シスコシステムズはバンガロールに、IBMは北京に、地域の本社を置いています。新興国の企業などを見る本社機能や担当を置くのも一つのやり方でしょう。
このように、地域軸をうまく使う方法も、日本企業にもできる余地がありそうです。つまり、グローバル戦略や新興国戦略と一括りで捉えるのではなく、アメリカはアメリカで、アジアはアジアで、アフリカはアフリカでというように、地域ごとの戦略をしっかり構築して、その地域を任せる人材を何年かかけて育てることに取り組むべきです。そこからトップになる人が出てくれば、チャンスが広がってきます。
小林:そうですね。海外経験をさせると言っても、先進国の主要都市だけが出世コースという日本企業はかなりあります。新興国などそれ以外の場所の支店長が出世コースになってくれば、会社全体の認識も変わってくるのでしょうね。
それから、去年まで円高で日本企業はずいぶん海外企業を買収しました。買収した企業をうまく利用して、海外は海外で独自に日本本社のコントロールを離れて頑張ってもらうのも、日本企業のグローバル化の一つのやり方かもしれません。そんな日本企業の事例をご存知ですか。
太田:日東電工の水ビジネスなどは、そういうふうに現地をうまく活用している例だと思いますね。同社はもともと粘着技術や塗工技術などをベースに幅広い製品を扱う化学メーカーですが、廃液処理など水の浄化を行うサービス事業を展開する際に、日本主導ではなく、シンガポール政府が作った国際研究施設「ウォーターハブ」内に事業開発拠点を設置し、すべて任せたのです。
従来の物を売るビジネスからサービス事業への転換が必要でしたが、現地スタッフを中心に現地のニーズを踏まえて開発し、グローバルなマーケティングも任せました。下手に本社直轄のプロジェクトを行うよりも、現地のチームに自由にやらせて、その力を活用するやり方は、日本企業にとって学ぶところが多いと思います。リバース・イノベーションの文脈かもしれません。
小林:本社がリモート・コントロールで新興国など現地のニーズに応えようとしても、難しいからですからね。本社の製品やサービスを販売するために現地子会社をつくったら、あとはそこに新しい事業を起こすようなミッションを持たせたり、地域である部分は自由にやってもよいと許可を与えたりするのは、一つのやり方でしょう。