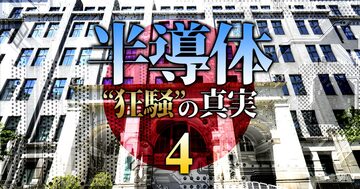Photo by Yuji Nomura
Photo by Yuji Nomura
日本の半導体産業の復活に向けて1兆円超の支援を行うなど、かつてない産業政策を打ち出している経済産業省も、人材流出問題とは無縁ではない。特集『公務員970人が明かす“危機”の真相』の#2では、通商産業省(現経産省)に23年間、勤務した経験がある齋藤健・経産相に、霞が関の政策立案能力に関する危機感や、国家公務員の人材確保に向けた改革の具体策などを聞いた。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)
経産省の後輩たちのモチベーションは高い
幹部の意識の高さは省庁ごとに格差あり
――経済産業省の官僚をされていた当時と、現在の中央省庁を取り巻く環境はどう違いますか。また、霞が関にどんな危機感を持っていますか。
私は23年間、通産省に勤務し、その後15年、国会議員をやっています。その間、接してきた日本の官僚は依然として非常に優秀です。世界的に見ても優れていると思います。
官僚の役割は、私の現役時代より重要になっています。経産省の政策を考えても、国益を懸ける場面は増えている。GX(グリーントランスフォーメーション)とかDX(デジタルトランスフォーメーション)、経済安全保障といった新しい課題が山積みです。政府の役割はますます大きくなっています。
国の仕事の魅力は変わっていないし、経産省の若手を見ると、やりがいを持って活躍している人が目に付きます。例えば、元日に能登半島地震が起こったとき、被災された人たちのために働きたいと自ら手を挙げて乗り込んでいって、現場を仕切っている若い職員がたくさんいました。被災地から戻った彼らから話を聞きましたが、本当に大活躍しています。
また、昨年のG7(主要7カ国)会合の運営を若い人たちがやりましたが、何と参加国から感謝状をもらった入省2年目の職員がいます。
一方で、霞が関全体で公務員志望者が減り、離職が増加傾向にあるのも事実です。一言でいえば、私は大いなる危機感を持っています。
――どんな危機感ですか。
実は、私は経産省の大臣官房秘書課で、課長補佐以下の人事や採用の責任者をやっていました。
人材が採れた年(の同期の職員たち)は何年たっても良い。つまり、優秀な人材の採用は、組織の人材力を決める最も大きな要素の一つといっても過言ではないのです。
正直、今そこが崩れてきている。以前よりも国家公務員を志望しなくなってきているし、入省してもすぐ辞める人がいる。ここの崩れは重大です。
では、どうするか。まず大事なのは、「ブラック霞が関」というようなイメージを払拭することです。最近、公務員について非常にネガティブな発信がすごく多い。
しかし、さっき言ったようにやりがいはあるし、辞めずに生き生きとやっている人たちも大勢いる。そういうポジティブな実態を、もっと発信していかなければいけません。
だから、経産省の職員が仕事の魅力を伝える必要がある。それで、私自身が学生向けのイベントに参加しました。いかに自分が通産省で幅広い経験をし、いろんな人と知り合い、成長できたかを話しました。大臣が採用のイベントで学生と対話するのは、多分、霞が関の歴史上初めてのことではないでしょうか。
今までみたいに待ちの姿勢ではなく、職員自身が発信してネガティブな情報に対抗し、学生が実態を踏まえて判断できるようにすることが大事です。
採用試験の在り方も抜本的に見直さなければいけません。民間の採用活動が早期化して、大学4年の4月には6割の学生が企業から内定をもらっているとの報道もあります。
海外や地方も含め優秀な人を採りたいなら、従来の大学4年夏の試験で選別するという発想では難しいのです。