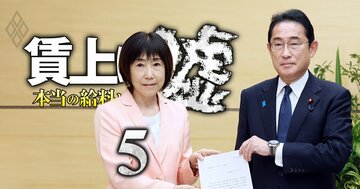Photo:JIJI
Photo:JIJI
人材流出に悩んでいる経済産業省が、日立製作所などの大企業を見習って人材マネジメントの改革に乗り出している。省内人事を担当する秘書課の人員を10年で2割以上増やし、採用や研修などを強化した。特集『公務員970人が明かす“危機”の真相』の#3では、中央省庁の中で、人材開発の先頭を走る同省の危機感や改革の中味を紹介する。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)
高度経済成長時代、霞が関には
人材マネジメントがほぼなかった
経済産業省は霞が関の中でも、官僚個人の能力によって政策を実行してきた官庁といえる。
その組織風土は時に「あれオレ詐欺」的などと表現され、政策を主導した官僚以外の者が、その功績を自分のものとしてアピールすることも少なくなかった。
極端なケースでは、「ZOY(ぜんぶ・おれが・やった)」というあだ名を付けられる幹部がいるほどで、官僚同士の実績争いの激しさは際立っていた。
「個人で目立って何ぼ」という組織風土の下で育つ経産官僚の政策立案能力と実行力を評価し、重用したのが安倍晋三元首相と菅義偉前首相だった。両政権を首相秘書官などとして支えた今井尚哉氏らいわゆる「官邸官僚」を経産省は輩出した。
ところが、幹部の華々しい活躍の裏で、現場は疲弊していた。
同省関係者は、「この10年で仕事は2~3割増えたのに、定員はほとんど増えなかった」と内情を語る。官邸が、AI(人工知能)やデジタル化の国家戦略を策定するとなれば、欧米の政策や企業の最新動向に明るい経産官僚が大量に引っ張られる。
それだけではない。「地方創生の戦略作成など(他省庁の方が知見がありそうなテーマ)でも経産省から人を出させられた」(同省関係者)。
官僚たちは、こうした業務に残業を増やすことで対応したが、限られた人員ではさすがに限界があった。優秀な若手は、高額報酬やキャリアアップを求めてコンサルティング会社などに流出した。
経産省の官僚は企業と情報交換することが多く、民間でも通用する常識と能力を持つ。だからこそ、他省庁に比べて転職も容易なのだ。
経産省内の危機感は高まり、局長級幹部が率先して人材開発にコミットする「組織“経営”改革」を2023年6月に宣言。齋藤健経産相は、国家公務員志望者が減り、離職が増えていることに、「大いなる危機感を持っている」と公言し、自ら人材確保に乗り出している(詳細は、本連載の#2『経産相が官僚人材採用に「大いなる危機感!」ペーパーテストに偏重した公務員試験の抜本改革を提言』参照)。
次ページでは、経産省の人事改革の実態や課題を明らかにする。同省が目指す「個の突破力」から「多様なチーム力」へのシフトを成功させるために、どんな課題があるのか。