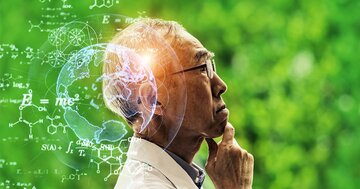写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「悩んでいたけど、寝て起きたら解決策がひらめいた」という不思議な体験があるように、我々はいまだに脳の全容を解明できていない。記憶の整理などもそんな脳の重要な働きであるが、今回は記憶のメカニズムを解説していこう。本稿は、井ノ口馨『アイドリング脳 ひらめきの謎を解き明かす』(幻冬舎新書)を一部抜粋・編集したものです。
災害や事故を経験した人は
なぜトラウマの記憶がよみがえる?
人はどのように記憶して、思い出すのでしょうか。
たとえば、普段は全く忘れていることでも、思い出そうと頑張るとつらつらとよみがえってくる瞬間があります。一方で、思い出したくないことを、何かの拍子に思い出してしまうこともあります。極端な例がPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。
災害や事故を経験した人が、人混みや乗り物など直接は関係ない状況でトラウマの記憶がよみがえってしまうというような症状です。
なぜこんなことが起きるのでしょうか?
この問いには、そもそも記憶がどのようにしてつくられるかが関係しています。記憶は、アイドリング脳(編集部注:睡眠中や休息中など、何かに集中していないときの脳の状態や働きや潜在意識下の脳の状態や活動のこと。例えば「寝て起きたら解決法がひらめく」などの現象)にも密接に関係する事柄なので、ここから僕の研究成果とからめながら、記憶のメカニズムについて紹介していきます。
記憶は、脳の中で物理的につくられています。その担い手は、脳の神経細胞。ここからは「ニューロン」とよびましょう。
ニューロンの仕事は、情報を伝えることです。1つのニューロンの細胞内では、電気信号によって情報が伝わっていきます。
ニューロンとニューロンのつなぎ目では、いったん電気信号は途絶えます。つなぎ目にはわずかな隙間があり、この隙間に化学物質が放たれ、反対側でキャッチされることによって、信号が伝わります。この隙間を含むニューロンのつなぎ目を「シナプス」といいます。
人間の脳全体には約1000億個のニューロンがあります。そして、互いにシナプスでつながりあって、ネットワークをつくっています。……とひとことで片付けましたが、そのネットワークは想像するのも難しいほどの複雑さを有しています。