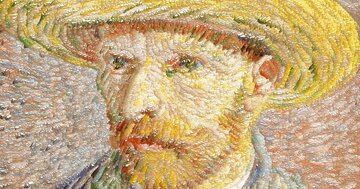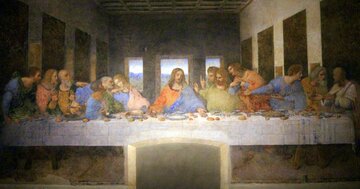そしてさらに、単にルールを知らない人もいる。時代を経てもろくなった芸術作品に関するさまざまな問題はすべて、「触るな」という1つの回答にたどり着くのだが、そんなことをじっくり考えたこともないという人たちである。私はある日、古代のウェヌス像の膝によじ登ろうとしている中学生の少年を止めたことがある。するとその少年は謝り、もの思わしげに周囲を見ながらこう言った。「だから、ここにあるのはみんな壊れてるの?」。言われてみればそこは、頭や鼻、手足のない古代の彫像の戦場のようだった。「全部ここで壊れたの?」
そのほか、一風変わった人々が私の目を引くこともある。たとえば、見ることに疲れ、歩行器につかまってほぼ水平に身を屈めている高齢の男性と、その耳元に何やらささやきかけている妻とがいる。夫の体力が尽きたため、これ以上見てまわることのできない中世の聖遺物について、妻が夫に長い時間をかけて細かく説明しているのだ。それが終わると、妻の助けを借りて夫は体を起こし、2人は先へとゆっくり歩いていった。
驚嘆と奇問に満ちた
美術館での出来事の数々
また、アメリカ美術の展示エリアにある噴水のところで、ある母親が子どもに2枚の硬貨を渡しながらこう言っていた。「1枚は自分のお願いのため、大きさが同じもう1枚は、ほかの人のお願いのため」。私はこれまでそんな言葉を聞いたことがなかったが、いつか自分の子どもにもそう言おうとすぐに思った。
さらには、まったく同じ服装をし、同じように髪が白い2人の老婦人がいた。よく見ると、2人は双子だった。さらによく見ると、2人の間に1カ所だけ違いがあった。一方はひも状の蝶ネクタイをつけていたが、もう一方はつけていなかった。
そんな人たちを1分余りしげしげと見ていると、不思議なことが起きる。突然その人が踵を返し、こちらに歩いてきて私に質問をするのである。
ある日の午後、ルネサンス初期の展示室に立っていると、驚異に打たれながらも楽しそうなある男性を見かけた。男性はいま、ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャの『聖母子』を見つめ、聖母のベールの美しいひだ、そのリズム、その繊細さに感銘を受けている。やがて男性は、私のほうを振り返ると、この小さな傑作を肩越しに見ながら言う。「この部屋の絵は……これは……」。そこで言葉が途切れる。「これは……」。自分の言いたいことがよくわかっていないのだろうか。「これは……その……岩屋で見つかったものなの?」