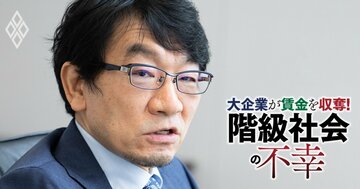他社も上げてないからうちも…
日本企業に広がる“沈黙の同調圧力”
企業の賃上げが十分にできないのは、「内部の力」だけでは弱いからだ。特に、大企業では、2000~2013年にかけて財務リストラによって、経常利益を捻出する経営的技巧を高めた。コストを抑える圧力はこの期間に極端に強まった。
企業は、トップライン(損益計算書の最上段)と呼ばれる売上がそれほど増えなくても、ボトムライン(損益計算書の最下段)の利益を増やせることに自信を持ってしまった。そのため、中長期計画で人員・人件費削減の計画を立てて、利益重視の方針を打ち立てた。これは基本姿勢として賃上げはしないということだ。
末端の中間管理職が賃上げは必要だと考えても、彼らは権限がないから賃上げは行えない。日本企業では、なかなか内部から既定の方針を覆そうという機運は生まれない。労働者の側も、経営層に敢えて抵抗はしない。
そうした内圧は、1990年代以降に強まり、近年は逆に「他社も上げないから自社も上げない」というかたちで強まった。外側の力すら働かず、賃上げをお互いにしない作用に変わっている。
賃上げをするには、この「内部の力」を「外部からの力」でねじふせる必要がある。「外部からの力」が強く意識されるとき、経営者は仕方なく賃上げに応じるだろう。
例えば、労働組合の要求は、重要な「外部からの力」である。
2022年は、英国では30年ぶりという鉄道ストライキが行われた。鉄道、地下鉄、バス、郵便、船員、空港職員など多岐にわたる。4万人以上が参加し、2022年6~9月にかけて行われた。9月にエリザベス女王の葬儀が盛大に執り行われるのと同時に、首都ロンドンでは各地でストライキが行われた。フランス、ドイツ、米国でも航空・港湾の労働者のストライキがあった。
対する日本は、ほとんど目立たない。2021年の労働争議件数は297件と、1957年以来で2番目の低さだ。労働者が声を上げないことは、経営者に対して「外部からの力」を意識せずに済むという環境を作っている。