
熊野英生
高市政権の「危機管理・成長投資」は投資主導で「強い経済」実現を目指すが、政府主導の産業振興には採算面が後回しになる危険もあり、また経済安全保障の名を冠してコスト面で割高のものを供給することを正当化しようとしている面がある。民間企業や金融機関が参加するには事業としての採算性チェックが不可欠だ。

日本銀行が政策金利を0.75%に引き上げた主な狙いは、輸入物価上昇の要因となっている円安の流れを止めることだと考えられるが、利上げ決定後も円安は進む一方で長期金利は2%台にまで上昇した。26年以降も政策金利は2%程度とみられる中立金利に向けて引き上げられると予想するが、円安・物価高のトレンドを変えられるかは見通せない。

高市新首相は物価高対策が当面の最優先課題としてガソリン税暫定税率廃止や電気・ガス代補助などを打ち出したが、重要なのは経済を回して賃上げを物価上昇に追い付かせることだ。投資拡大や働き手のスキルがより生かせる職場への在籍型出向や転籍を増やして生産性を向上させ高賃上げをいかに継続するかだ。

次期首相となる 高市早苗・自民党新総裁の経済政策は積極財政・金融緩和を柱にした「アベノミクス2.0」の色合いが濃い。だがアベノミクスがデフレ下にその脱却を掲げたのに対し今は歴史的なインフレ下だ。円安、物価上昇が加速し物価対策の上積みが必要になる悪循環に陥る懸念がある。

物価高対策で給付金や減税の議論が続くが、「所得再分配調査」では日本の所得再分配はそれなりに機能している。多くの人が生活の苦しさを訴えるのは所得水準自体が低いからだ。給付金などの議論への違和感は、所得を増やす成長政策の議論がなおざりにされていることに原因がある。

参議院選挙では物価高対策で「賃金と物価の好循環」を掲げていた石破首相も現金給付を言い出し、消費減税を掲げる野党とのアピール合戦だ。首相は党内の意見に引きずられようだが、背景には年金生活世帯など賃上げの恩恵が及ばない層が総世帯の約4割を占めることもある。重要なのは中小企業への賃上げ波及や年金受給層などの資産運用収入を支えることだ。

トランプ大統領の就任100日は過激な関税政策への不安からドルが売られ、円ドル相場は約1割の円高進行となった。2025年内のどこかで所得税、法人税の減税へとかじを切ればドル安の流れも一服するとみられるが、トランプ関税の大方が撤廃されずに残ると、米国経済の悪化からドル安円高が進み、日本経済もダメージを受ける。現状ではその可能性が高い。

「外国人材の給料が高すぎる」と怒る人が目をつぶる「日本人の能力不足」という大問題
エコノミストの熊野英生氏は、近年の超円安傾向には物価高騰以外にも多くのデメリットがあると指摘する。このまま円安が続けば、海外投資家から見放され、日本は未来がない国と見なされる恐れがある。日本経済が陥る負のスパイラルと、その打開策に注目が集まる。※本稿は、熊野英生『インフレ課税と闘う!』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

え!そんな方法で?一流エコノミストが大真面目に提案する「ポップでユニークな賃上げ促進策」
政府は2020年代中に最低賃金を全国平均1500円に引き上げる目標を掲げている。物価高騰への対応が背景にあるが、実現には至っていない。エコノミストの熊野英生氏は、日本企業の体質が賃上げの障害であると指摘し、企業意識の改革が鍵であると主張している。※本稿は、熊野英生『インフレ課税と闘う!』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

そりゃバンバン追い抜かれるわ…「成長しない日本企業」と「成長したアジア企業」の決定的な違い
約45年前は、製造業の輸出産業において世界から一目置かれていた日本。しかし、90年代後半から日本の国際競争力は急速に衰えていき、現在も低空飛行を続けている。なにゆえ、日本は競争力を失ってしまったのか。日本銀行出身のエコノミストとして活躍する熊野英生氏が、日本が辿った栄枯盛衰について解説する。※本稿は、熊野英生『インフレ課税と闘う!』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

減税や規制緩和への期待が強かった「トランプ2.0」だが、関税政策や“政府効率化”などの企業ビジネスへの影響が大きい政策が前面に出る中で、「トランプ不況」の方が意識され始めている。米国や日本の株価の急落、不安定化はそれを象徴する。

2024年は訪日外国客数が過去最高となり、訪日外国人消費は前年比で2.8兆円も増えて8.1兆円に達した。この勢いは名目の家計最終消費の伸び率を+1.0%ポイントほど押し上げるものだ。25年も円安などの効果で訪日数は増えるとみられ、地方にとって地方経済の活性化、地方創生の鍵になる。

日本銀行は12月金融政策決定会合で利上げを見送った。前日のFOMCでFRBの2025年の利下げペースがトランプ政策のインフレ・リスクへの懸念から減速する見通しになったことが大きな要因だ。米国のインフレ・金利高止まり予想で今後、円安が進むとみられ日銀は25年1月以降、追加利上げを繰り返すことになりそうだ。

石破政権は、物価高対応などの経済対策で住民税非課税世帯に3万円を配ることを決めるようだ。給付が2021年から何度も繰り返されているのは住民税非課税世帯の約75%が年金生活世帯で物価上昇の影響を大きく受けているからだ。本来は年金制度改革で対応すべきなのに、当面、当座の対応をしているに過ぎない。

2024年の出世数は70万人を割る可能性があるが、出生数減少の陰には婚姻数の減少がある。23年の婚姻数は47.4万件とコロナ禍前の8割に減り、50歳時での未婚者はこの20年間で男性は2.2倍、女性は3.1倍に増えた。婚姻数減少に対応しないで出生数を増やすのは甚だしく困難だ。

日経平均株価は8月5日の歴史的暴落のあと、急速に回復しているが予断は許さない。当面、米国の経済指標や米大統領選挙の行方を見極める必要がある。日経平均株価がピークを付けた後、景気後退になった確率は1985年以降では7割。投資家はこのリスクシナリオも頭に入れておく必要がある。

米大統領選で優位に立つトランプ前大統領の「米国第一」の政策はインフレ再燃やドル高など、その意図とは「逆の効果」を生むリスクが高い。日本や世界経済もそれに巻き込まれる懸念がある。バイデン氏撤退で「ほぼトラ」の流れが変わるのかは、人ごとではない。
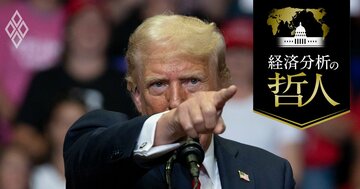
消費者物価上昇率は鈍化しているが、日本銀行は財政への配慮から低金利を維持せざるを得ず、円安と内外物価格差によってインフレ圧力は続き、消費者物価の上昇率は当面2~3%で推移する。しかしこれは政府・日銀が目指す賃金と物価、景気の“好循環”にはならず「家計の窮乏化」が続く可能性が高い。

マイナス金利解除を皮切りに金利水準の正常化が進む見通しだが、営業利益に対する金利コストの割合を規模別、業種別に独自試算したところ、資本金2000万円未満の中小企業の金利支払い能力はかなり低いことが分かった。収益力が弱いまま長年の超低金利時代に借り入れを増やしてきた企業への調整圧力が強まることになりそうだ。

#10
日経平均株価は史上初めて4万円台を付けたが、急騰の背景には半導体などITの好況を反映した米国株上昇との連動がある。日本では「実感なき株高」との声もあるが、米株価が大きく腰折れしない限りは日本株の上昇は続く。懸念は米国にも市場がFRBの利下げを強く織り込み過ぎている「虚」の部分があることだ。
