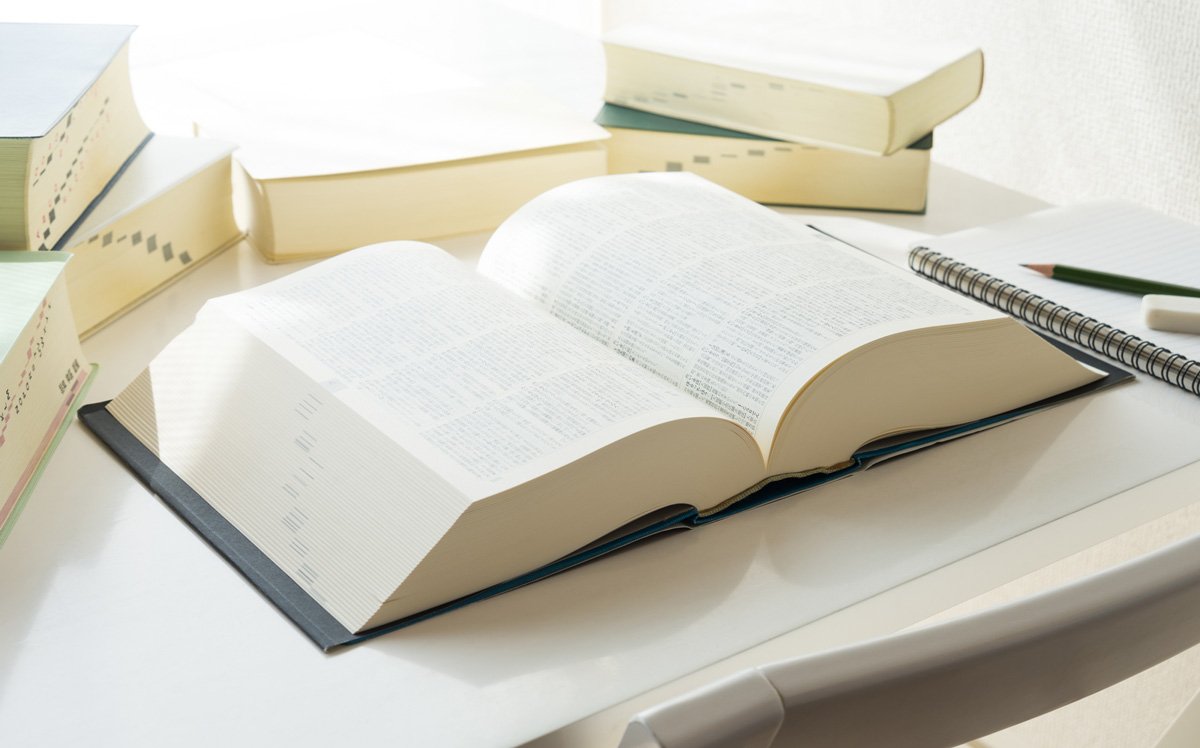 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
問屋からスーパー、スーパーからプラットフォーム、そしてこれからはAIエージェントへと、時代ごとに“鍵を握る存在”が移っていく中でも、本質的には「相手やシステムにはそれぞれの都合や制限があり、必ずしも自分の希望が優先されるわけではない」という真理はずっと変わらない。
そして、技術の発展と社会の変化がますます加速する現代において、ことわざや表現が時代の実態に合わなくなるスピードもまた早まっていくだろう。
江戸時代から今に至るまで長く生き残ってきた「そうは問屋が卸さない」も、あと少しで日本語から消え、代わりに、「そうはプラットフォームが勧めない」や「そうはAIが動かない」といった新しい表現が広がる時代が来るかもしれない。そして、その先にはさらに別の主体やテクノロジーが登場し、私たちはまた同じような構造を別の言葉で語ることになるだろう。
こうして考えてみると、冒頭の若い人の質問は、私たちに「時代の変化とことわざ(言葉)の関係性」を考えさせるきっかけとなる。
「いつか古い言葉は消えてしまうのか。それとも形を変えながら残っていくのか」という問いは、まさに言語そのものが生き物のように変わりゆく性質を持っていることを示している。いずれにせよ、たとえ新旧の表現が入れ替わろうと、「物事はそう都合よくはいかない」という真実だけは不変である。
だからこそ、人間の営みや社会の仕組みを学び続け、新たな流れに適応しようと努めなければならない。それは、言葉の問題だけでなく、私たちが今後どのように暮らし、仕事をするのかを左右する大きな課題でもある。
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)







