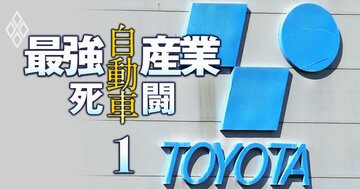なぜトヨタとダイムラーは合従連衡へ動いたのか
振り返れば2017年、ダイムラーは乗用車と商用車の事業の分離を発表し、現在の経営体制ができた。その後、ダイムラーは協業相手を探す中で目星を付けたのが、トヨタ陣営だった。
23年5月、トヨタとダイムラー、三菱ふそうトラック・バス、日野自動車の4社は協業を発表した。日野と三菱ふそうを統合した上で、トヨタとダイムラーは持ち株会社を設立し上場を目指すスキームだ。
しかしその後、日野でエンジン認証不正問題が発覚したことにより、日独トラック連合の誕生が遅れていた。そして今年1月、日野は12億ドル(約1700億円)の制裁金を米国当局に支払うことで合意。こうしてトヨタとダイムラーは再度、日野と三菱ふそうの統合協議を詰め、持ち株会社の設立を急ごうとしている。
背景には、100年に1度と呼ばれる自動車業界の変革と、中国勢の台頭がある。中国では電動化やソフトウエアが自動車の性能を決めるSDVの開発が加速している。
4月に上海で開催されたモーターショーは、それを確認する絶好の機会だった。ファーウェイによる完全自動運転技術が注目を集めた一方、日本の自動車のソフトウエア化の遅れが明るみになったのだ。中国勢は、空飛ぶクルマとも呼ばれるeVTOL(電動垂直離着陸機)も発表した。
商用車分野においても24年、世界の中・大型トラック市場のトップ5のうち2社が中国企業だった。トップは09年に山東省政府下で、省内の重工や自動車部品メーカーが統合してできた山東重工業。4位は中国国営の自動車メーカーである第一汽車だ。
日本の石油化学や家電の分野は、中国勢に価格面はもちろん技術面でも追い付かれてしまった。「対策は難しい」と口にする企業経営者は多い。同様の波が自動車分野にも押し寄せているのは明白だ。