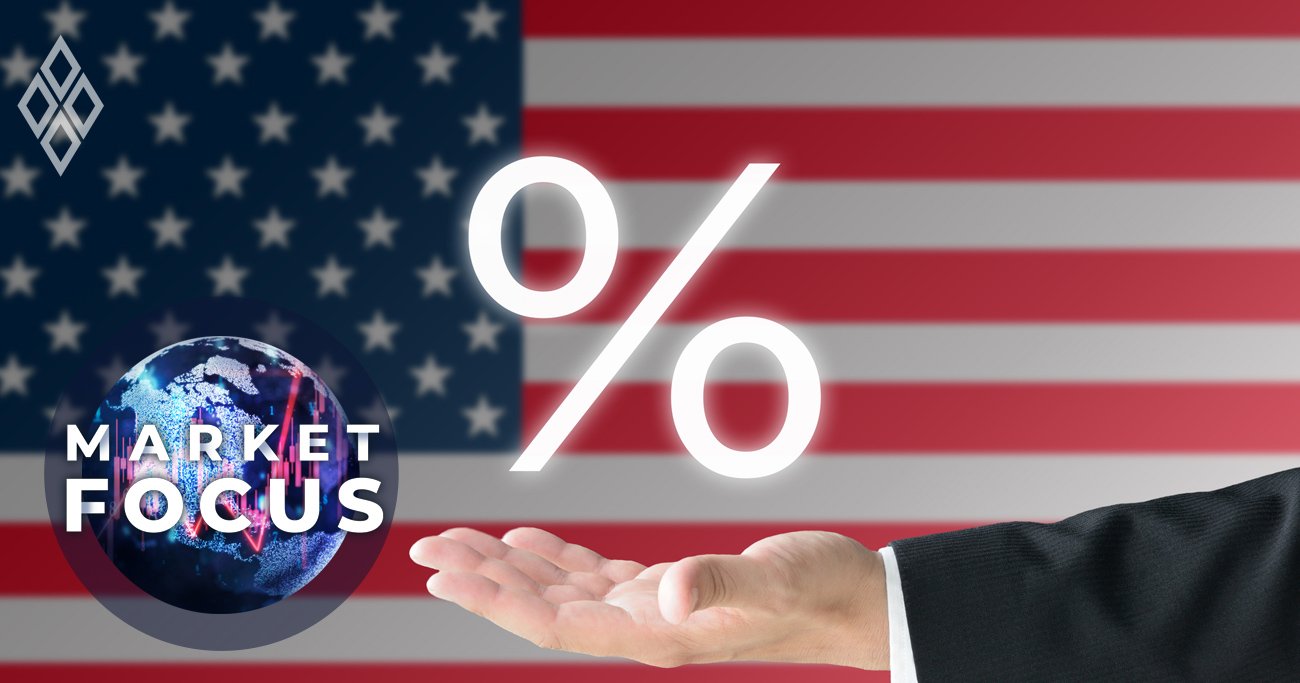 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
トランプ減税延長を中心とする減税法案が成立した。審議の過程では、米国債の格下げもあったが、減税延長による赤字は関税収入で賄うというのがトランプ氏の公約。そのため、関税交渉で大きな譲歩は期待できない。ただ、関税収入への期待が米国の長期金利上昇を抑制することになるだろう。(SMBC日興証券 チーフ為替・外債ストラテジスト 野地 慎)
主要国で高まる
財政リスク
英国のスターマー政権は、障害者手当の変更案で66億ポンドの歳出削減効果を見込んでいたが、120人以上の労働党議員による反発を受けて大幅に譲歩した。
その直前には数百万世帯の年金受給者に対する冬季燃料手当の廃止を撤回し、12億5000万ポンドの財政拡張を余儀なくされており、同政権のリーブス財務相には辞任観測が強まっていた。
加えて、7月2日、スターマー首相が財務相支持を明言しなかったことから、英国債のイールド(利回り)カーブが大幅にスティープニング(短い期間の利回りから長い期間の利回りへの曲線の傾斜が急になること)し、それはドイツや米国の長期金利にも影響を及ぼす格好となった。
25年上半期の市場の最大のテーマはトランプ政権による関税政策であることに相違はないが、債券市場にとっての最大のテーマは、財政拡張や国債発行増、そして需給環境悪化をよりどころとした長期金利上昇などだ。
トランプ政権が関税政策に係る交渉に絡めてEU(欧州連合)等への防衛費拡大を求めており、その結果としてのドイツなどの財政拡張であることを考えれば、結局のところ「トランプ」が原因である。
我が国も同様の圧力を受けながら「(防衛費については)日本が決めるべきで、外国から言われて『わかりました』と決めるものではない」と石破茂首相がかたくなにそれを拒む状況だ。
ただ、我が国の場合、参院選の結果のいかんによっては各党の要求をのむような拡張的な財政運営が展開されるとの懸念が消えず、実際、英国の長期金利が大幅上昇となった翌日である7月3日に行われた我が国の30年債入札は弱い結果となり、超長期国債利回りの上昇を招いている。
このように、数多くの国がトランプ政権による「ディール」や「要求」などを遠因とした財政拡張懸念にさいなまれている。当の米国でも5月に米国債が格下げされるなどしており、債券市場においては、財政リスクが常に俎上に載る状況だ。
次ページでは、米国の財政リスクについて考察し、トランプ関税や米国の減税の市場へのインパクトを予測する。







