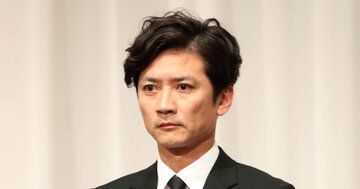圧倒的な実績と世界的評価を誇っており、プレイ以外の場で公に報道される言動など、誠実で清廉なイメージーー日本人にとっては「理想の自己投影先」のような存在だったりする。そのような人物に万が一にでもスキャンダルが出た場合、人々は強烈な認知的不協和を経験することになる。
「完璧な人物である」「しかし不倫という不道徳な行為をした」 という2つの矛盾する認知が同時に存在するとき、人はそれを統合できず、不快感を覚える。
そのとき、人々は次のように反応する可能性が高い。
・「事実ではないと信じたい」
・「報道が誤っているに違いない」
・「誘惑した相手が悪い」
これは、アメリカの心理学者・フェスティンガーの認知的不協和理論が説明する典型的反応である。人は、自分の中の「理想像」と「現実」との矛盾を抱えきれないとき、現実を歪めてでも理想像を維持しようとするのだ。
“個別判断”の世論と、“公平な判断”の法
誰が叩かれ、誰が許されるのかは、その人の属性・背景・タイミング・支援構造・キャラクター・報道環境によって大きく左右される。
そして何よりも、情報の受け手である「私たちの心理」が、その火の勢いを決めている。
こうしてみると、「法」という制度のありがたさが見えてくる。人間の感情は偏るし、矛盾も歪曲もする。正義も、好感度も、同情も、ある種の“演出”や“物語”によって変化する。だからこそ、人の背景によって処遇が変わらないよう制度を整える「法の支配」には一定の意味がある。
誰かの失敗や過ちに接したとき、私たちは「怒るか、許すか」を自動的・瞬間的に判断している。
しかし、その判断こそが「社会の鏡」であり、「私たち自身の価値観」でもある。不祥事の情報に振り回されている今こそ、何を許し、何を許さないかーーその判断の軸を、一人ひとりが一度、冷静に問い直してみる必要があるのではないだろうか。
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)