広告企画

2003年に発売された『ヘルシア緑茶』は、体脂肪を減らすのを助ける特定保健用食品としてブームを巻き起こした。その研究過程には、茶カテキンの発見と苦味を克服する過程があり、特定保健用食品への険しい道のりや、良質な茶葉を探す努力があった。今スティックタイプの新製品『ヘルシア 茶カテキンの力 緑茶風味』(機能性表示食品)の発売で、ヘルシア新時代の幕が開く。




郵便局のみまもりサービスである「みまもり訪問サービス」は、離れて暮らす親に郵便局社員が会いに行き、生活状況を聞き取り報告するサービス。相手が“郵便局の人”だから、高齢の親御さんも安心して迎えることができる。訪問先ではどんな会話が交わされるのか。相模原郵便局の訪問に同行した。




ビジネスの「デジタル化」とは、人工知能(AI)やIoT(モノのインターネット)などに関する先端的な技術を活用して、既存のビジネスを変革したり、新たなビジネスを生み出すこと。経済産業省が推進する「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」は、デジタル化の推進により従来のビジネスや組織を変革し、新たな付加価値を生み出すことを目指す。そこで早い時期からDXを推進し、現場のスマート化を達成し、さらにその先を目指している先進企業のソニーセミコンダクタマニュファクチャリングと中部電力のケースを取り上げ、現場がどのように変革したのかを、経産省の取り組みを含めてお伝えする。



ニーズ・シーズの発見から始める新産業の育成。農林水産省が進める業界の壁を超えた「『知』の集積と活躍の場」プロジェクトでは、実用化と産業強化への道筋を示して研究開発をけん引する「プロデューサー」が活躍し、オープンイノベーションの成果を高めている。
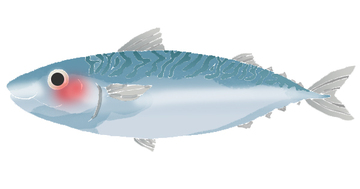
税理士法人リーガル東京では、弁護士法人リーガル東京と一体で、これら相続に関する問題の解決にあたっている。税務と法務の双方に精通した専門家集団がワンストップでサービスを提供できることが強みである。また、不動産会社を併設しているため、相続不動産売却の相談にも対応している。

司法書士法人・行政書士リーガルサービスは、「法務でしあわせを届ける」を合言葉に、東京・神奈川にある5つの相談室を拠点に、相続・遺言・家族信託・生前整理・登記などの業務を展開しており、相談の累計は6万件を超える。

山口県岩国市に事務所を構える山本修税理士事務所は、中国・九州エリアや東京エリアにおいて、建設、土木、医療、飲食などの法人を中心顧客として、年間500件以上の案件に携わっている。

税理士法人山田&パートナーズは、資産税に強い税理士法人として多くの顧客・金融機関から高い評価を得ている。事業承継コンサルティングにおいては、豊富なコンサルティング実績に基づき、最適な承継方法を提案している。

森山税務会計事務所は、愛知県を中心に東海地区で相続税対策と相続税申告を専門に行っている。特に相続税申告については、森山貴弘代表が名義預金等の税務調査対策・立会経験が豊富であることから、“税務調査が実施されても不安にならない相続税対策”で多くの実績を積んでいる。

むさしの税理士法人は、法人設立時から他の士業や専門家との連携を意識して業務を運営してきた。相続においては弁護士、司法書士等の専門家との協働により、複雑な案件にも総合力で対応している。

むかいアドバイザリーグループは、税理士法人と司法書士事務所、行政書士事務所等で構成された北陸地域では数少ない税務・財務と法律に関する総合専門家グループ。企業や個人事業主、資産家の方々を主なクライアントとして、各種コンサルティング業務や手続きの実行、税金の申告等のサポートを行っている。
