ローソン
米オハイオ州に、J.J.ローソンが牛乳販売店を営んでおり、「新鮮な牛乳」と地域の評判となっていた。その後J.J.ローソンが「ローソンミルク社」を設立し、日用品なども販売するようになり、米国北東部を中心にチェーン展開。コンビニエンスストア「ローソン」という名も、看板に用いているミルク缶のデザインも、この米国の牛乳店「ローソン」が発端となっている。
関連ニュース
2020/3/7号
コンビニの裏側は搾取の連鎖、商社が君臨し取引先・加盟店が泣く
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
コンビニエンスストア業界で苦境に追い込まれているのは、フランチャイズ契約先の加盟店だけではない。厳しい取引条件に泣く食品メーカー、ノルマに追われる本部社員もいる。一方、本部の親会社である総合商社は、配当金や幹部人事、そして商流を押さえ、いわば“勝者”として君臨している。
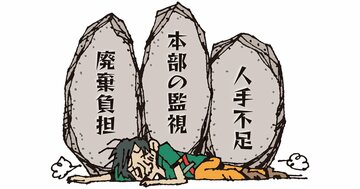
第114回
ローソンはなぜドローンで「からあげクン」を配送するのか
情報工場
24時間営業問題に揺れるコンビニ。実は、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートのコンビニ3大チェーンは24時間営業を始めてから40年以上になるという。この年月の中でコンビニは、人々の生活を支える「インフラ」の役割を果たすようになっていった。

#11
ローソン竹増社長に聞く、「売り上げ至上主義」から脱却する秘策
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
コンビニ加盟店の利益を、全社員の賞与を決めるKPI(重要業績評価指標)に設定したローソン。ダイヤモンド編集部のインタビューに応じた竹増貞信社長は、既存店売上高を本部の目標に据えてきた弊害を反省。店利益をKPIに定める、戦略を語った。

日本に残された未開拓市場、農業における生産性向上のカギとは
鈴木一之
海外では和食ブームが続いており、日本の農産物輸出は7年連続で史上最高を更新。農業参入への規制緩和、法人化、農地バンクなどによって企業サイドにも農業が有望なビジネスとして映っている。地方都市では私鉄、ガス会社、スーパーマーケット、エンタメ企業など、その地方の中堅企業が相次いで農業への参入を試みている。さらなる農業の活性化に向けて、取り組みを強化すべき方策や、すでに農業分野に進出している企業群を紹介する。

#8
コンビニ搾取構造に甘い公取委、本部の言い逃れを専門家が一刀両断
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
仕入れの強制、無断発注、見切り販売の“妨害”……。コンビニエンスストア本部による加盟店への“横暴”は以前から存在した、いわば「古くて新しい問題」である。“市場の番人”と呼ばれる公正取引委員会に対して、加盟店オーナーの期待は高まっているものの、公取委は処分に及び腰だ。そこで独占禁止法の専門家の意見を基に、公取委が詳しく把握すべき事例を紹介する。

#6
社会保険未加入事業者のための「対応マニュアル」、コンビニオーナー必見!
ダイヤモンド編集部,相馬留美
「もしも年金事務所の担当者が、突然店を訪れたら?」「今まで未加入だったが、これから社会保険に入りたいときはどうしたらいいの?」。社会保険未加入のコンビニオーナーはもちろん、それ以外の未加入事業者も必見の「対応マニュアル」をこっそり公開する。

#5
コンビニの「社会保険廃業」続出か、業界を崩壊させる最強の時限爆弾
ダイヤモンド編集部,相馬留美
社会保険に加入していないコンビニ加盟店に対して、年金事務所による加入促進の圧力が強まっている。高騰する人件費に苦しみ、保険料を支払う余裕がないオーナーたちの店舗が大量閉店する日も近いかもしれない。同様のリスクは、他の小規模事業主にも付いて回る。
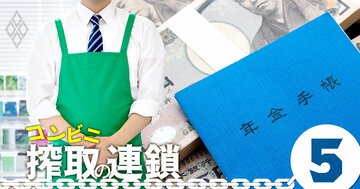
#3
三菱商事がローソンを、伊藤忠がファミマを「食い物」にする商社支配のリアル
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
三菱商事はローソンを、伊藤忠商事はファミリーマートを子会社化。配当収入を得るだけでなく、商品や原材料の仕入れから物流、加盟店の消耗品まであらゆる流通ルートに入り込み、売り上げなど収益を上げることに成功した。子会社にも“進駐軍”のごとく人材を送り込んで着々と重要なポストに就かせ、コンビニよりも商社の利益を優先しかねない状態になってはいないか。
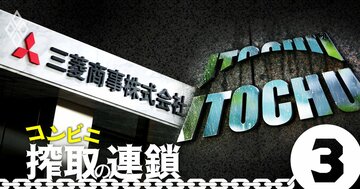
予告編
コンビニ搾取の連鎖、メーカーと加盟店の犠牲で商社が潤う実態【予告編】
ダイヤモンド編集部
“コンビニ地獄”は加盟店だけではない。食品メーカーなどの取引先、そして末端の本部社員もまた、厳しい要求やノルマに追い込まれている。その背後には、親会社として配当金やあらゆる取引機会を手にする大手商社が君臨している。

第8回
ラグビー元慶應スター選手・玉塚元一氏「成功体験のルーツはラグビー」
ダイヤモンド編集部
特集「熱狂!ラグビー ビジネス・人脈・W杯」(全10回)の第8回は、デジタルハーツホールディングスの社長で、ローソンなどでも社長を務めた玉塚元一氏を直撃。経歴は華麗だが、その気持ちの強さの原点は慶應大学ラグビー部時代の「地獄の山中湖」にある。

コンビニ3社店舗飽和で伸び悩み、王者セブンは24時間死守へ100億円「支援策」【決算報19秋】
ダイヤモンド編集部,岡田悟
コンビニエンスストア大手3社の2020年2月期中間決算が出そろった。売上高が伸びず、過当競争のより店舗拡大もままならない。惣菜に注力して客単価を上げ、なんとか1店当たりの売上高を維持している状況だ。最大手のセブン‐イレブン・ジャパンは24時間営業店への支援強化を表明し、体力を競う消耗戦に突入した。

コンビニFC店を「覆面調査員」が監視、オーナーの自由を奪う本部の重圧
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
さまざまな苦境が明らかになったコンビニエンスストアの加盟店。本部は直接的に圧力をかけるだけでなく、店舗に覆面調査をかけて品揃えや接客態度を採点するなど、あらゆる手段を使って加盟店オーナーの手足を縛り、自由を奪ってきた。

コンビニ「出来たて弁当」は消費増税後に人気商品として広がるか
森山真二
コンビニではレジカウンターの揚げ物総菜などのファストフードがドル箱的存在だが、これを利用して出来たて弁当を手掛けるチェーンは少なくない。ローソンは出来たて弁当に注力、拡大を目指しているし、セイコーマート、デイリーヤマザキ、ポプラが現在も力を入れる。だがセブン-イレブンはいくつかの実験をしてきたが、今のところ出来たて弁当らしき商品はない。出来たて弁当は10月からの消費増税でコンビニの優位性を発揮できる商品などといわれているが、果たして広がるのだろうか。

コンビニオーナー10人中10人が訴えた「苦境」、経産省ヒアリングで
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
経済産業省のコンビニエンスストアに関する有識者会議が、現役の加盟店オーナーへのヒアリングを実施した。オーナーは人手不足や廃棄負担による苦しい現状を、不平等な契約関係から改善出来ないと訴えた。オーナーたちの悲痛な叫びは国や本部を動かすことができるか。

ローソンも始めたウーバーイーツが「コンビニ労働問題」の二の舞になっているワケ
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
ローソンが食品宅配サービスのウーバーイーツで商品を配達する実験を始めた。消費者の利便性は高まるが、ウーバーイーツの配達員はウーバーと雇用契約を結ばない事業者という立場であるため、雇用保険や最低賃金が適用されない。コンビニエンスストア加盟店オーナーを事業者と労働者のどちらとみなすかという議論がある中、ウーバーの配達員の間でも問題を訴える声が上がっている。

CASE3
コンビニより多い6万店にメス、調剤薬局3万店への大淘汰
ダイヤモンド編集部,大矢博之
コンビニよりも多い約6万店――。増え過ぎた薬局にメスが入ろうとしている。とりわけ厳しい目が向けられているのが、病院の前に乱立する門前薬局だ。医薬分業という国策に乗って増殖した薬局が、3万店まで淘汰されるという声もささやかれ始めた。

#5
三菱商事が三菱自動車を支援せずローソンに1400億円超を投じた理由
ダイヤモンド編集部
三菱商事と三井物産。商社業界における長年のライバルである両社に共通するのは、創業の原点に立ち返る動きが起きていることだろう。そのきっかけと考えられるのが、2016年の赤字転落というショックを経験したことだ。

第20回
プロ経営者が語る「大政奉還」の条件
ダイヤモンド編集部,重石岳史
非上場企業の代表として知られるサントリーホールディングスは現在、会長に佐治信忠氏、副会長に鳥井信吾氏という創業者一族が経営中枢を担う。現在は創業家ではない新浪剛史氏が5代目社長を務めるが、新浪氏のミッションの一つであった米蒸留酒大手ビームとの統合作業を終え、創業家の鳥井信宏副社長が次期社長に就く「大政奉還」が、いずれ行われる見通しだ。

第16回
ドローンに電子タグ、デジタル技術でリアル店舗の価値を上げる
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
人手不足が大きな課題となっているコンビニエンスストア。ローソンの竹増貞信社長は、将来、電子タグ(RFID)の実用化が進めば、従業員の負担を大きく減らし、温かみのある接客により多くの時間をさけると話す。

ローソン「ワンオペ化」はコンビニのブラック度を増すのか?
島野美穂
昨年10月、コンビニ大手のローソンが2025年をめどに、デジタル技術を導入することを発表した。レジの無人化や商品陳列の自動化を進め、全商品にICタグを導入することで、店員1人体制でも店舗を営業できるよう仕組みを整えるという。コンビニ業界の働き方が、今大きく変わろうとしている。そこで、コンビニ社労士®の安紗弥香氏に業界が抱える課題と今後の展望について聞いた。
