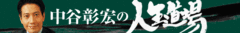組織・人材(25) サブカテゴリ
第81回
成功したイノベーションはシンプルである
成功したイノベーションは、驚くほどシンプルである。イノベーションに対する最高の賛辞は「なぜ自分には思いつかなかったか」だと、ドラッカーは言う。

最終回
叱って嫌われることを、恐れない。
怒ることは、勇気が要ります。でも、1回怒って嫌われる関係ができたほうが、仲よくなれます。1回この体験をすると、お互いの関係が一皮むけるのです。
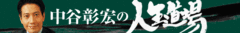
第2回
男性と女性、サボり上手なのははたしてどちらか? もちろん男性も女性もそれぞれ工夫して息抜きを楽しんでいる。とはいえ、あからさまなサボりは、とくに男性に多くみられるようだ。

第33回
部下の「SOS」に気づく。
リーダーのもう1つの要件は、コミュニケーション力です。本当は辞める必要がない部下を辞めさせてしまうのは、上司がコミュニケーションをとらなかったからです。
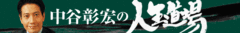
第22回
サッカー界のトップに君臨し続けた川淵三郎氏に代わり、元浦和レッズ社長の犬飼基昭氏が日本サッカー協会の新会長に就任。元ビジネスマンらしい広い視野を活かし、サッカー界に新たな風を吹かせようとしている。
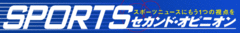
第1回
女性には「感情的になりやすい」「すぐ涙を武器にする」、そんなイメージがある。しかし本当に「女性は感情的」なのだろうか?最近は男女を問わず、感情的になりやすい社員が多いのかもしれない。

第32回
昔話を、しない。
「あの人についていきたい」と思われるリーダーは、話題が豊富です。「なんでこんなことを知ってるんだろう」と思える人は、なんとなくカッコよく思えるものです。
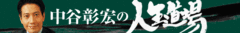
第41回
ピーター・ドラッカーは「グルの中のグル」と称されることが多いが、ドラッカー自身は「その賛辞はフレデリック・ウィンズロー・テイラーに贈られるべきだ」とよく言っていた。

第31回
まず、自分が動く。
人を動かすのがリーダーと思っているとしたら、それは大きな勘違いです。リーダーがじっとしていたら、人は動きません。人を動かすには、まず自分が動くことです。
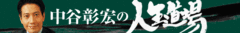
第74回
知識労働者は全員エグゼクティブでなくてはならない
現代社会では、すべての者がエグゼクティブであるとドラッカーは言う。仕事の目標、基準、貢献は自らの手にある。したがって、物事をなすべき者は皆、エグゼクティブである。

第13回
今回のテーマは「官僚制度」。官製談合などで問題視される官僚制度ですが、今年制定された「国家公務員制度改革基本法」で本当に問題は解決されるのでしょうか?
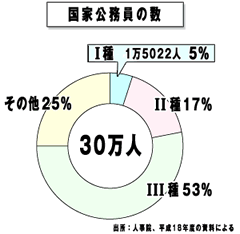
第30回
今の売上げよりも、明日の人材をつくる。
10年後も会社が元気でいるために、商品開発・企画をするのも1つの方法です。でも、一番先にやらなければならないのは、人材を育てていくことです。
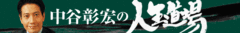
第33回
ゆうちょ銀行のトップとその秘書の人事について、合法性や妥当性を問う炎が国会で燃えている。焦点の人物は、高木祥吉社長と、同社長が大蔵省・金融庁時代から重用してきたという女性秘書の2人だ。
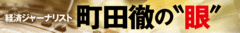
第37回
ロディックは当時のイギリスでは比較的新しい、フランチャイズ方式でボディショップの拡大を図った。この手法には同社の理念や情熱を持続させるだけの力があった。
![アニータ・ロディック[ザ・ボディショップ創業者]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/2/240wm/img_429eba068f1763ba0a12f3bcc3ab6ddd12730.jpg)
第39回
シャインは画期的な著書『組織文化とリーダーシップ』で組織文化という概念を構築し、現在頻繁に使われるようになった「心理的契約」「キャリアアンカー」という言葉を造り出した。

第70回
特定の目的の集積から共通の善を生み出す
新たな多元社会にあっては、個々の組織は、自らの目的こそ、最も重要な中心的目標であると見る。だがそれらの目的の一つひとつは、相対的な善の一つであるにすぎない。絶対的な善ではない。

第29回
何かをやる時には、常にリスクがつきまといます。リスクがあるからリターンがあるのです。リスクがなくリターンだけあることなどありません。リスクをとれるのが、リーダーです。
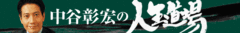
第11回
感情的な上司に、卑劣な同僚。そんな“アスホール”(くそったれ社員)を排除することでグーグルなど勝ち組企業は高成長を維持している、とサットン博士は説く。
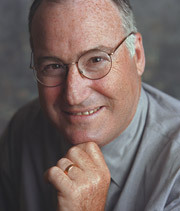
第69回
マネジメントが経済と社会の発展をもたらす
マネジメントは共通の目的のために個人、コミュニティ、社会の価値観、意欲、伝統を活かすものである。マネジメントが伝統を機能させない限り、社会と経済の発展は起こりえない。
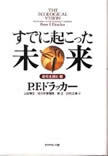
第28回
ナンバー2を、大切にする。
ナンバー2を育てられる人が、みんながついていきたくなるリーダーです。ついていきたいリーダーは、上の悪口を言わないで、ナンバー2を一生懸命もり立てている人です。