
加藤嘉一
第68回
台湾総統選挙・立法委員選挙において、蔡英文主席率いる民進党が躍進し、蔡氏は初の女性総統に当選した。この選挙結果によって、今後中台関係はどう変わるのか。それが対岸・中国の“民主化”プロセスにもたらし得るインプリケーションを、3つの観点から解説したい。

第67回
12月中旬、中国がイニシアティブを取るかたちで開催した第二回世界インターネット大会に姿を現した習近平が“重要談話”を発表した。その談話や仕草から見えた、米国への対抗心と主権への固執に染まる中国共産党のサイバー戦略の「現在地」について、考察しよう。

第66回
政権中期に差しかかる習近平体制において、中国の政治・社会体制はどのように変わって行くのか。その運営を見据える上で重要な、経済・社会政策をめぐる3つの政治会議が、過去1ヵの間に北京で開催された。これらの会議から、今後の政権運営を占ってみよう。
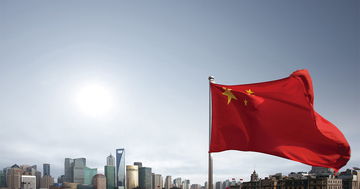
第65回
11月20日午前、中国共産党中央が北京の天安門広場の西側に隣接する人民大会堂で、胡耀邦同志の生誕百周年を記念する座談会を開いた。胡耀邦の名誉を回復し、再評価しようとする動きの背景には、中国共産党の思惑も透けて見える。
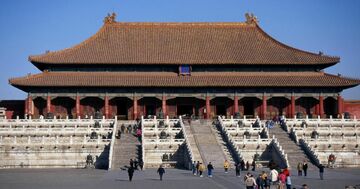
第64回
習近平と馬英九による中国と台湾の歴史的なトップ会談が開催された。いわゆる“馬習会”よって、国交のない両国は「1つの中国」に向け、今後どのように動き出すのだろうか。中台間の微妙な駆け引きを象徴する3つの文脈を取り上げ、その見通しを占おう。

第63回
先日、習近平国家主席が英国を公式訪問した。米国への公式訪問から1ヵ月経たないインターバルで実行された訪英からは、習近平時代の中国共産党を占う3つのインプリケーションが見えてくる。

第62回
中国のような国家にグローバル経済のルールを決めさせてはならない――。オバマ米大統領はTPPの大筋合意を受けて、こうした声明を出した。筆者は中国世論の荒れ模様を予感した。実際に中国は、TPPをどれくらい警戒しているのか。

第61回
米国というプレイヤーは、私たちの中国理解にとって、時に“引き出し役”を担ってくれる。ワシントンDCで習近平訪米を眺めながら、私はそう感じた。米国公式訪問で引き出された習近平政治の意外な素顔を通じて、今回消極的に見えた中国外交の課題を指摘したい。

第60回
“中国人民抗日戦争兼反ファシズム戦争勝利70周年記念式典”と題して敢行された閲兵式を眺めながら、私が注目したケースを6つ取り上げ、そこから導き出されるインプリケーションに踏み込んでみたい。共産党の動向を追跡する意味において、“9.3大閲兵”は貴重なケーススタディになるはずである。

第7回
挑発もせず、譲歩もしない。事実に基礎を置くことで日中関係は前進する
今年は終戦から70年を迎える重要な年であり、特に中国・韓国といかなる関係を構築するのかが改めて議論されている。揺れる巨人・中国はどこに向かっているのか、そして、日本は中国といかに向き合えばよいのか。「日中歴史共同研究委員会」日本側座長などを務めた北岡伸一氏に、加藤嘉一氏が聞いた。
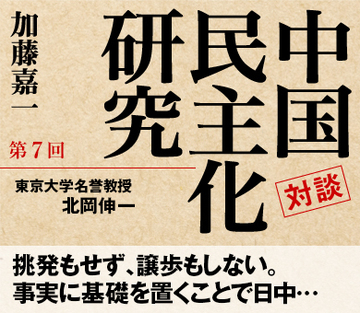
第6回
米国の民主主義に触れることで、中国人留学生はより“愛国的”になる
今年は終戦から70年を迎える重要な年であり、特に中国・韓国といかなる関係を構築するのかが改めて議論されている。揺れる巨人・中国はどこに向かっているのか、そして、日本は中国といかに向き合えばよいのか。「日中歴史共同研究委員会」日本側座長などを務めた北岡伸一氏に、加藤嘉一氏が聞いた。
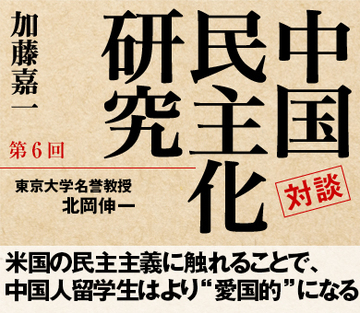
第5回
皇帝・習近平は、中国をいかに統治すべきか
今年は終戦から70年を迎える重要な年であり、特に中国・韓国といかなる関係を構築するのかが改めて議論されている。揺れる巨人・中国はどこに向かっているのか、そして、日本は中国といかに向き合えばよいのか。「日中歴史共同研究委員会」日本側座長などを務めた北岡伸一氏に、加藤嘉一氏が聞いた。

第4回
「中華民族の偉大なる復興」はリアリティを持たない
今年は終戦から70年を迎える重要な年であり、特に中国・韓国といかなる関係を構築するのかが改めて議論されている。揺れる巨人・中国はどこに向かっているのか、そして、日本は中国といかに向き合えばよいのか。「日中歴史共同研究委員会」日本側座長などを務めた北岡伸一氏に、加藤嘉一氏が聞いた。
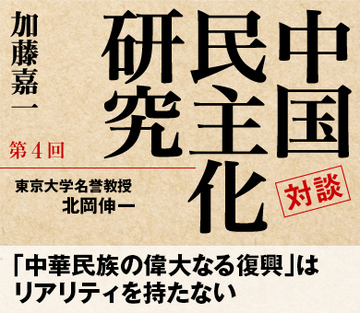
第59回
今回の“上海ショック”で、公安が株式市場に介入した事実は、中国共産党指導部が、今回の株価乱高下という経済情勢が、政治の安定を脅かす“政敵”になり得ると判断したために他ならない。李克強首相は、中国共産党の絶対的・究極的・最終的命題を担保する上で不可欠な経済社会の安定的成長を保証するために、もがき、苦しみ、奔走している。

第3回
中国人の力を最大限に発揮するためには、人種のダイバーシティが不可欠である
日本を代表するオンライン金融グループのマネックスグループは、かねてより積極的に中国市場でのビジネスを行っている。日本企業が中国でビジネスを進めるうえでは、何を重視すべきなのか。マネックスグループ代表執行役社長CEO・松本大氏に、加藤嘉一氏が聞いた。
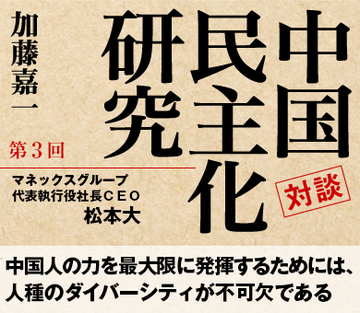
第2回
中国に変化を期待するのではなく、自分たちがどう付き合うかが大切
日本を代表するオンライン金融グループのマネックスグループは、かねてより積極的に中国市場でのビジネスを行っている。日本企業が中国でビジネスを進めるうえでは、何を重視すべきなのか。マネックスグループ代表執行役社長CEO・松本大氏に、加藤嘉一氏が聞いた。
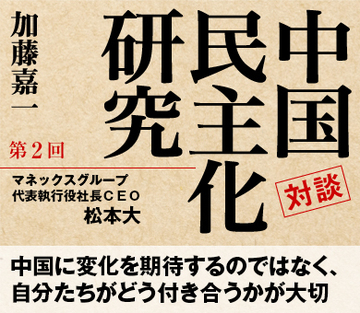
第58回
8月14日に公表された安倍談話には“侵略”“植民地支配”“心からのおわび”の3つのキーワードを含んでいた。中国共産党指導部が談話をどう認識し、どう反応し、そしてこれからの対日関係をどうマネージしていこうとしているのか、という問題を考えてみたい。

第57回
約10日後に発表される安倍晋三首相による戦後70年談話を巡る動向を、中国は静かに、しかし継続的に注視しているように見える。中国共産党指導部は“戦後70年安倍談話”に対して、何を、どこまで求めていくであろうかという点を浮き彫りにしていきたい。

第1回
戦後70年、米国から考える日中関係そのとき、日本のリーダーは何をすべきか
今年、終戦から70年を迎える。「70年談話」で先の戦争をいかに総括するのかは、日本国内のみならず、中国や米国などの関係諸国でも大きな注目を浴びている。中国問題の専門家は、こうした動きをいかにとらえているのか。ウィルソンセンターフェローのリチャード・マグレガー氏と加藤嘉一氏が語る。

第56回
先日、安保法案が衆院で強行採決された。中国の政府関係者や識者たちは、このことに対してどんな本音を持っているのか。不満を露わにする識者たちの声がある一方で、中国共産党は強い警戒心を抱きながらも、日中関係の発展を重視しているようだ。
