上田惇生
第80回
意思決定は問題の根本を理解して行なう
意思決定は、問題の根本を理解して行なわなければならないとドラッカーは言う。不変のものを見なければならない。賢くあろうとせず、健全であろうとしなければならない。

第79回
21世紀の問題を解決するための社会生態学
ドラッカーは、自らを社会生態学者と規定する。「自然生態学が生物の環境を研究するように、社会生態学は、人間によってつくられた人間の環境に関心をもつ」という。
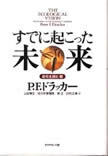
第77回
事業は何かを決めるのは顧客である
事業が何かを決めるのは顧客である。事業は何かとの問いに対する答えは、事業の外部、すなわち顧客や市場の観点から事業を見ることによってのみ得られる。

第76回
すでに起こった未来は体系的に見つけられる
あらゆる変化が、他の領域に変化をもたらす。そして機会をもたらす。そこには、タイムラグがある。そこでドラッカーは、それらの変化を“すでに起こった未来”と呼ぶ。

第75回
予期せぬ成功の追求が自らの成長につながる
成功の鍵は責任にある。大事なことは、自らに責任を持たせることである。あらゆることが、そこから始まる。責任ある存在になるということは、成長の必要性を認識するということである。

第74回
知識労働者は全員エグゼクティブでなくてはならない
現代社会では、すべての者がエグゼクティブであるとドラッカーは言う。仕事の目標、基準、貢献は自らの手にある。したがって、物事をなすべき者は皆、エグゼクティブである。

第73回
最高の人材は最高の機会に割り当てる
ドラッカーは、最高の機会には最高の人材を、最高の人材には最高の機会を割り当てよという。割り当てるべき人的資源がない場合には、なんとしてでもそれを手に入れなければならない。

第72回
リーダーシップは資質ではなく仕事である
リーダーシップとは、資質でもカリスマ性でもない。意味あるリーダーシップとは、組織の使命を考え抜き、それを目に見えるかたちで確立することである。

第71回
経営責任の制度化としての事業監査
1980年代、米国の経営者はプロとしての仕事をしていなかった。そこで乗っ取りブームが起きた。長年勤めた企業の乗っ取りと解体は、知識労働者への裏切り以外の何物でもなかった。

第70回
特定の目的の集積から共通の善を生み出す
新たな多元社会にあっては、個々の組織は、自らの目的こそ、最も重要な中心的目標であると見る。だがそれらの目的の一つひとつは、相対的な善の一つであるにすぎない。絶対的な善ではない。

第69回
マネジメントが経済と社会の発展をもたらす
マネジメントは共通の目的のために個人、コミュニティ、社会の価値観、意欲、伝統を活かすものである。マネジメントが伝統を機能させない限り、社会と経済の発展は起こりえない。
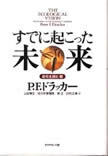
第68回
報告と手続きは道具であって支配者ではない
報告と手続きは誤った使い方をされるとき、道具ではなく支配者となる。よく見られる誤りが、手続きを規範と見なすことである。しかし手続きは完全に効率上の手段である。

第67回
共通の目的を持つ専門家集団が組織である
組織は、常にそれ自体が専門化した存在である。これに対し、社会、コミュニティ、家族は、言語、文化、歴史、地域など人を結び付ける絆によって規定される。
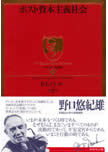
第66回
ベンチャーの成功は予期せぬ顧客が現れたとき
ベンチャーにはアイディアがある。製品やサービスがある。コストは確かにある。そして収入があり、利益がある。だが、失敗するベンチャーには事業がない。

第65回
ネットワーク社会で増える組織間のパートナーシップ
多くの企業、病院、政府機関が、仕事をまるごと専門企業に委託している。まもなくほとんどの組織が、自らにとって主たる収益源でない支援的な業務のすべてをアウトソーシングするようになる。

第64回
意見の不一致が存在しないときは決定をしない
選択肢すべてについて検討を加えなければ、視野は閉ざされたままになる。成果をあげるには、教科書にいう意見の一致ではなく、意見の不一致を生み出さなければならない。

第63回
全体を理解する知覚的な認識が不可欠である
「300年前デカルトは、『我思う。ゆえに我あり』と言った。今やわれわれは『我見る。ゆえに我あり』と言わなければならない」。ドラッカーは、これからは分析と知覚とのバランスが不可欠だという。

第62回
不適切な多角化はマネジメントを不可能にする
「組織は多角化していないほどマネジメントしやすい」。単純であれば明快である。ところが長いあいだ、多角化しさえすれば業績が上がると信じられてきた。

第61回
マネジメントチームという組織の骨格
複数の人間が協力して、多様な課題を同時に遂行する必要が生じたとき、組織はマネジメントチームを必要とする。マネジメントチームを欠くとき、組織は管理不能となり、計画は実行に移されなくなる。

第60回
変わるためには捨てる能力を身につける
人は学べば学ぶほど、学んだことを捨てられなくなる。したがって学ぶ能力とともに、学んだことを捨てる能力を身につけなければならない。
