小宮一慶
第134回
経営者には、もちろん能力や事業に対する熱意が必要です。しかし、成功するためにはそれだけでは不十分。重要なのは、「正しい考え方」を身に付けることです。ただ、この「正しい考え方」を身に付けたつもりになって、自分の欠点を顧みない経営者も少なくありません。

第133回
今年の4月から、中小企業も働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の対象になります。すでに働き方改革に取り組んでいる企業も多いですが、その一方で、中間管理職に業務量の“しわ寄せ”が起こっているという現状もあります。
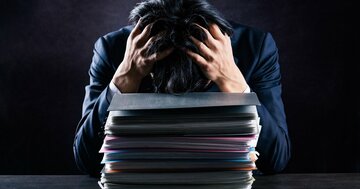
第132回
新しいアイデアを次々と思いつくことは、悪いことではありません。しかし、その段階ではただの「思いつき」。ビジネスパーソンとして必要なのは、アイデアの実現可能性を仮説検証し、ビジネスにつながるアイデアにすることです。

第131回
オリンピックイヤーとなる2020年がスタートしました。中東情勢の緊迫化で、年初から世界経済は予断を許さない状況が続いています。2020年の景気はどうなるのでしょうか。昨年の数値を振り返りながら考えてみたいと思います。

第130回
2019年も残すところ数日となりました。この冬休みの間に、2020年の目標を立てる経営者は多いはずです。その際は、売上高や利益といった会社の目標だけでなく、経営者個人の目標を立ててください。経営者は従業員以上に、個人として会社にどう貢献するかが問われているからです。

第129回
事業承継にM&Aを選択する中小企業経営者が増えてきました。自分の会社は売るなら高く売りたいものですが、そもそも「会社の値段」はどのように決まるのでしょうか。2通りの方法をご紹介します。

第128回
経営者が「〇歳までに辞める」と、自ら定年を宣言することはよくありますが、実際のところ言葉通りに辞める人はほとんどいません。ただ、ある程度の年齢になれば、引退を考えなくてはならないでしょう。経営者は自らの「引き際」をどうやって決めるべきなのでしょうか?

第127回
日本の各地に甚大な被害をもたらした台風19号から1ヵ月。被災地の状況が報じられる中で、企業の苦境も伝えられています。災害は予測不能なものですが、突然起こる危機に対して経営者が日ごろからどのように備えておくべきでしょうか?

第20回
悪いときはもちろん、良いときも反省し、何が悪かったのか、何が良かったのかという本質を分析する習慣をつける
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第19回
部下からアイデアや意見を求めるときは、自分なりの仮説を持ったうえで衆知を集めるようにする
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第18回
働く人たちが意義を感じられ、やる気が出て、売上や利益が伸びるような中間目標を設定できるか。そこが経営者の腕の見せどころ
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第126回
人脈は、経営者の財産のひとつ。ビジネスの環境が急速に変化する中で、狭い世界にとどまらず自分自身に良い示唆を与えてくれる人と付き合うことは重要です。しかし、中には人脈を自分の利益のために利用しようとする人もいるので注意が必要です。

第17回
最新のデータを眺めてみて、「変だな」と思ったことは、とことん自分の頭で考えてみる
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第16回
自分の頭の中に日本経済新聞を読めるだけの「定義」と最新データのデータベースをつくる
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第15回
本を読んだらポイントを要約してメモし、人に手短に説明してみる。アウトプットの習慣を身につけよう
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。
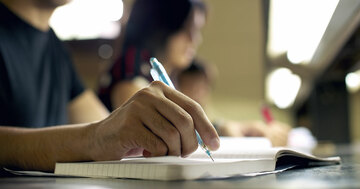
第14回
「結論を簡単に求めない」まず、自分の頭で「仮説」を考えてみる
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第125回
当社の社員には危機感がないと嘆き、従業員に対してむやみに危機感をあおり、危機感を共有したがる経営者がいます。しかし、経営者が従業員に語り、共有すべきなのは危機感ではありません。「現場」「理念」「夢」の3つです。

第13回
思考力を高めるためには、論理的思考力が高い人が書いた読み応えのある難しい本をじっくり読む
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第12回
良い絵を見て「直観力」と「想像力」、「大局と細部を見る力」を鍛える【後編】
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。

第11回
良い絵を見て「直観力」と「想像力」、「大局と細部を見る力」を鍛える【前編】
今、社長の人も、これから社長を目指す人も、さらにレベルアップ、スキルアップするためには、何をどうすればいいのでしょうか? 人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『社長の成功習慣』(ダイヤモンド社、9月5日発売)は、経営者になる人にぜひ身につけてほしい50の行動習慣について解説した社長のための教科書です。本連載では、同書から抜粋して、経営者としていっそう成長するためのポイントについてお伝えしていきます。
