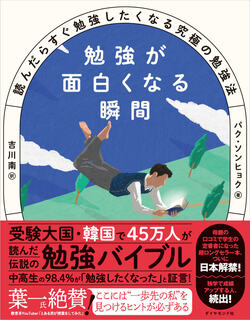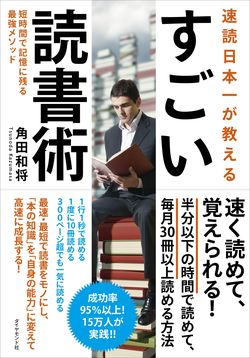韓国で45万部の超ロングセラーが発売から7年、いよいよ日本に上陸。韓国で社会現象を巻き起こした『勉強が面白くなる瞬間』。この本を読んで、学生の98.4%が「勉強をしたくなった」と証言! なぜ、勉強をしなかった人たちが勉強に夢中になるのか。10代~70代の世代を超えて多くの人が共感。そこにノウハウは一切ありません。ただ、この本を読んだ人にはわかることでしょう。執筆に8年かかったとされる『勉強が面白くなる瞬間』から、その驚くべき内容を紹介する。
今回は、速読日本一の経歴をもつ『すごい読書術』の著者・角田和将氏にインタビュー。本を読まない=勉強が苦手というイメージがあるが、速読に取り組む人は、どのように本を読み、学びに励んでいるのか?『勉強が面白くなる瞬間』著者もまた、このままではいけない!と本屋に駆け込んだエピソードがあるが、学ぶ姿勢をどう身につけるかが、勉強にとても大事なことのようだ。(初出:2022年9月10日)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
勉強すること自体が面白い
 角田和将(つのだ・かずまさ)
角田和将(つのだ・かずまさ)高校時代、国語の偏差値はどんなにがんばっても40台。本を読むことが嫌いだったが、借金を返済するため投資の勉強をはじめる。そこで500ページを超える課題図書を読まざるを得ない状況になり、速読をスタート。開始から8か月目に日本速脳速読協会主催の速読甲子園で銀賞(準優勝)、翌月に開催された特別優秀賞決定戦で速読甲子園優勝者を下して優秀賞(1位)を獲得。日本一となり、その後独立。速読を通じて、本を最大限に活かし、時間の量と質を変えることの大切さを教えるため、国内外を飛び回っている。セミナー講演では医師、パイロット、エンジニアなどの専門職から経営者、会社員、主婦と、幅広い層の指導にあたり、95%以上の高い再現性を実現している。大企業から学習塾など、さまざまな分野での研修も実施しており、ビジネスへの活用、合格率アップなどにつながる速読の指導は好評を博している。教室に通う受講生の読書速度向上の平均は3倍以上で、「1日で16冊読めるようになった」「半月で30冊読めるようになった」「半年間で500冊読めるようになった」など、ワンランク上を目指す速読指導も行っている。著書に、『速読日本一が教える 1日10分速読トレーニング』(日本能率協会マネジメントセンター)、『1日が27時間になる! 速読ドリル』(総合法令出版)、『速読日本一が教える すごい読書術』(ダイヤモンド社)がある。
――本を読む人は、頭のいいイメージがあります。本を読むって、どういうことでしょうか?『すごい読書術』では、成果を出す人ほど、本を読んでいるエピソードがありました。
できる人の読書とは、「無知の知を知るためのツール」です。また、自問自答するきっかけを得るもの。
たとえば、上のポジションになると、本人にアドバイスしてくれる人がいなくなる傾向があります。しかってもらえるとか、助言してもらえる人とかが限られてくる。そういうときに、本にしかってもらう、教えてもらうとよく聞きます。特に、50代の方が多いですね。あと、会社経営の人も。
――速読教室に通う人も同じですか?
皆、向上心が高いですね。ただ、職種はばらばら。会社役員もいれば、一般社員や技術職、お医者さん、専業主婦などさまざま。ただ、どの人を見ても総じて意識が高い。
意識が高いにも、2パターンあります。
1つは、背負っているものがある人。2つ目は、勉強すること自体が面白いと感じている人。主に、後者が多い印象です。
たとえば、60代くらいの方で、80代まで生きるにしても、1冊でも多く、小説を読みたいと考え、トレーニングしている人がいました。
「あ~、そうなんだ」という感覚を得られる、知らないことを知るのが楽しいのではないでしょうか。
知らないほうが幸せなこともあるけど、できなかったことができるようになった達成感に惹かれているわけです。
――『勉強が面白くなる瞬間』には、過去の偉人が何千時間を経て得たものをたった数行で学べるすばらしさを伝えていますね。
自分に気づけていないことに気づける。いいことですよね。人と会話する機会がだいぶ減った今、著者と対話しているような感覚になれるのがいいし、あたらしいひらめきも出てきます。
昨今、オンラインベースだからこそ、読書が活きるポイントは変わってきているのかもしれないですね。以前と違って、飲み会もないし、会話する機会が少ない。本が変わりを担っているのかな、と。
本を読む人の気持ちも、本を読まない人の気持ちも、両方の世界を知っている自分からすると、本から学ぶほうが、「時間的にも」「効率的にも」「労力的にも」いちばんいい。
インターネットの情報はフェイクや嘘、あやしげなものが混在。いろいろなトラップがあります。情報を見極めるのが本当に難しい。それを見極めるためにも、本から入ったほうがラクというのもありますね。
本は厳選されている情報なので、信憑性がある。「やばいな、これ」ということにならない。あったとしても、本のカバーや帯を見ればわかりますしね。そういう点からしても、「無知の知を知るためのツール」として、本が活用されるわけです。
(取材・構成/編集部 武井康一郎)
(本原稿は書籍『勉強が面白くなる瞬間 読んだらすぐ勉強したくなる究極の勉強法』をベースにした、インタビュー記事です)