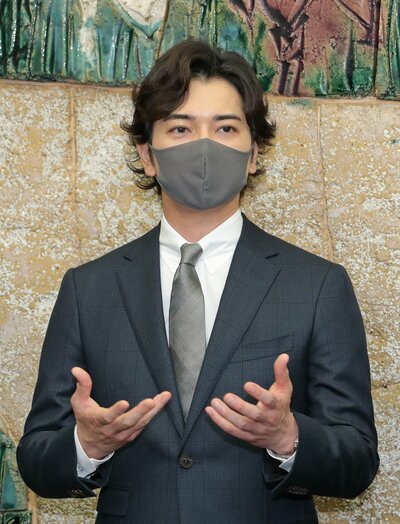 『どうする家康』観光推進協議会を訪れた後、取材に応じる松本潤 Photo:JIJI
『どうする家康』観光推進協議会を訪れた後、取材に応じる松本潤 Photo:JIJI
そして、何よりも予想外だったのは、秀吉のいち早い帰還である。光秀は最初に現れる敵が秀吉だとは考えなかったので、安土城を占領するなど近江でうろうろして、西への固めを後回しにしたことが痛かった。
あまりにも中国大返しが見事だったので、秀吉も加担していたという人もいるが、それはナンセンスだ。
なぜ中国大返しができたかは、そんなに不思議ではない。なにしろ、信長の大軍が援軍として西下してくるはずだったのだから、秀吉は、信長の動きを掌握するため、知らせを待つだけでなく、情報収集伝達ルートを構築していたはずだ。
また、播磨の秀吉や備前の宇喜多の領内を通って来たのだから、兵站(へいたん)を完璧に確保するために、街道を修築したり、食料や馬を用意したり、狭い道に集中しないように脇街道をどう利用するか考えたりと、あらゆる準備ができていた。秀吉は逆方向に帰るのに、それを利用しただけである。
それでは家康はといえば、こちらも無防備にも軽装で、堺見物中だった。本能寺の変についての第一報を聞いたとき、少人数では無事に三河にたどりつけまいと考え、「知恩院に入って腹を切りたい」と言い、これに他の者もいったんは同意したという。
信忠の場合と同じように、雑兵や農民などの手にかかって死ぬ可能性があるのなら、自分で死んだ方がましという価値観は、かなり広く戦国武士にはあったということだ。また、家康は、桶狭間の戦いや大坂夏の陣でも自害すると口走ったといわれるように、ピンチになると弱気になりがちな人である。
しかし、本多忠勝だけが断固、「生き延びることを試みるべし」と諫言し、枚方から京田辺を抜け、信楽の多羅尾、伊賀の柘植を通り伊勢市の白子から乗船して帰国した。一方、堺見物に同行していた穴山梅雪は別の道をとったが、南山城の山中で夜盗の手にかかって無残な最期をとげた。
本能寺の変からは、現代の企業も学ぶべき教訓がある。
日本企業の多くが、トップである会長と社長が同時に死ぬことを想定していない。
だが、一緒に行動していて事故に巻きこまれることもある。かつて、オムロンの立石一族は、創業者が健在なころ、毎年、ハワイで一族の新年会を開いていたが、往復は2機の飛行機に分乗していた。正しい備えだ。
企業に限らず、政治・行政から皇室に至るまで、日本のさまざまな組織は、例外的な異常事態への備えが、あきれるばかりに欠如しているのは、東日本大震災でも明らかになったところだ。
(徳島文理大学教授、評論家 八幡和郎)



