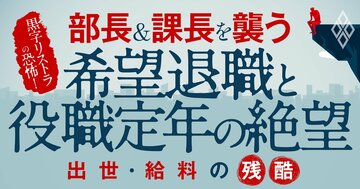スカーフが自由化されたわけではないし、
イスラム体制も崩壊していない
もちろん、政府は「風紀警察」の活動を停止しただけで、公式にスカーフ自由化を宣言したわけではない。そればかりか、デモから1年半以上を経て、いくらか人々のほとぼりが冷めはじめたのをいいことに、ベール不着用の再厳罰化に向けた動きすらある。
とはいえ、スカーフをかぶらない生活に慣れてしまった今、女性たちが再び以前のような強制に従うとは考えにくく、なし崩し的な自由化の波はもはや食い止められない、というのが大方の見方である。
一方、今のところイスラム体制そのものは崩壊していない。つまり、スカーフ強制という一角だけが崩れ落ちて、体制のほうは一応持ちこたえているという状況で、これも私が当時予想した通りの結果になっている(もっともサラさん自身がそれを忘れてしまった現在、私の予言が、みんなから「後出しジャンケン」と思われているのは遺憾だ)。
かくしてスカーフの自由化は、思いのほか早く達成されたわけだが、イラン人たちの心中は複雑だ。
おおむね30代以上の世代は、デモによりスカーフが自由になったことは大きな前進だったと考えている。何しろ革命以降、40年以上にわたり幾度となく繰り返されてきたスカーフへの抵抗が、ようやく実を結んだのだ。
かつては、バスや地下鉄の乗客、タクシーの運転手の中にも、スカーフのかぶり方を注意してくるようなお節介な人がいたが、デモの後はほとんど姿を消した。今そんなことをすれば、「独裁者の手先」「イラン国民の敵」とありったけの罵詈雑言を浴びせられ、その場で袋叩きにあってしまうからだ。
親でさえ、自分の娘にスカーフのことで口出しするのがはばかられるようになった。「スカーフなんか、みんなしてないじゃん!」と言われてしまえば、いくら親でも二の句が継げない。
このようにスカーフの自由化は、政治的領域に留まらず、社会や家庭のなかにも新しい風を吹き込みつつある。それは、「自分のことは自分で決める」という、自主と自立の精神でもある。その意味では、スカーフ自由化はある種の文化的「革命」だったと言っても、あながち誇張ではないだろう。