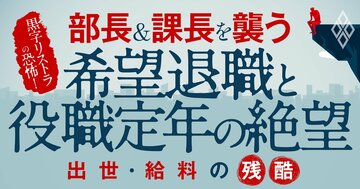灰の下にかくれた熾火
~デモ後のイランを覆う空気
 『イランの地下世界』(若宮總 著、角川新書)
『イランの地下世界』(若宮總 著、角川新書)
しかし、一方で10代、20代の若者たちは、決して現状に満足していない。彼ら彼女らは、スカーフ強制に対する抵抗の余勢を駆ってイスラム体制の本丸にまで攻め込み、カッコつきではない文字どおりの革命を起こすつもりだったのだから。
連日連夜、実弾が飛び交う中を、命も顧みずに行進した結果がスカーフの自由化だけでは、まさに「大山鳴動して鼠一匹」。体制打倒を夢見て散っていった仲間たちに顔向けもできない。
今この世代のあいだに漂っているのは、まごうことなき敗北感であり、安全な場所で模様眺めを決め込んでいた上の世代に対する不信感である。一定の勝利ととらえるか、敗北ととらえるか――。反体制デモの評価は、イラン人のあいだでもまだ定まっていない。
ただ、彼らがデモ後のイランについて話すとき、決まって引き合いに出すペルシア語の慣用句がひとつある。
「灰の下にかくれた熾火(おきび)」
――うわべだけの平静は、長くは続かない。人々の怒りと不満は、いつかまた燃えさかる炎となって噴き出すに違いない。それが、すべてのイラン人の共通認識である。