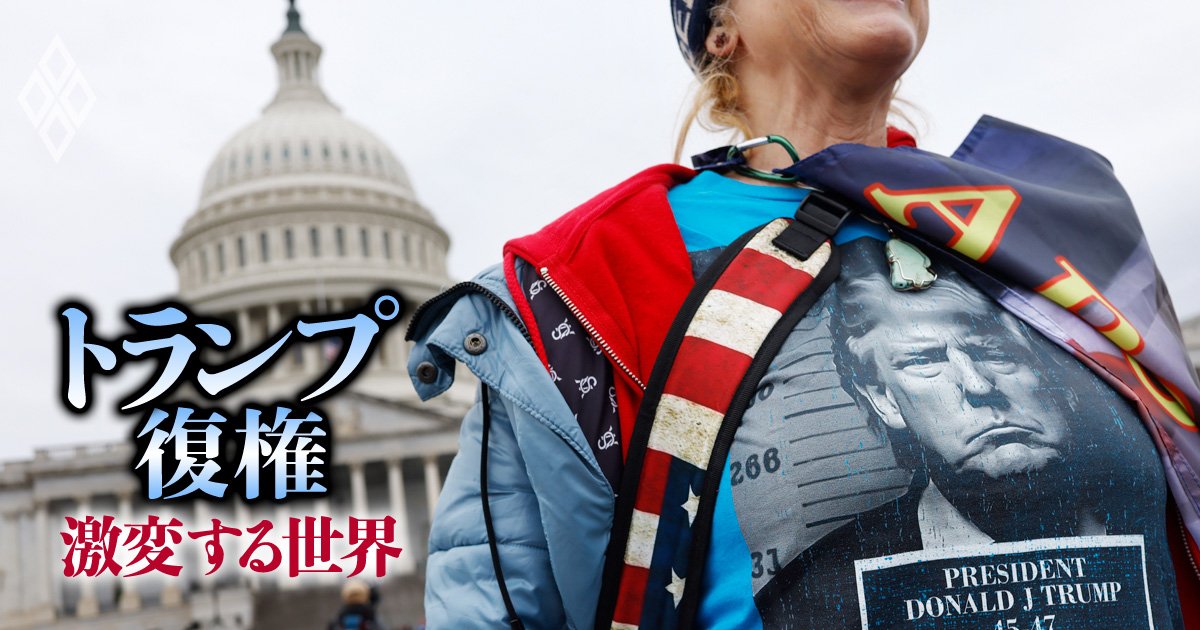謝罪の遅れを取り戻すには?
例えば、プロジェクトの進行が遅れる、顧客対応が後手に回るといった具体的な問題が発生する場合、部下や関係者は「遅延がなければ結果が違ったかもしれない」と考える傾向がある。
このような思考が広がることで、遅延は単なるプロセス上の問題に留まらず、結果に対する責任を問う声を強める要因となる。
今回のフジテレビ経営陣のあまりに不十分な対応と、重なる部分が大きいのではないだろうか。もう1つ、レポートを読んでいて興味深い結果があったので、紹介してみたい。
研究によれば、(謝罪の)意思決定が遅延した場合には謝罪を求める声が最も強くなるものの、謝罪の効果が最も低いことがデータから明らかになっている。
・謝罪の必要性:遅延した意思決定では、参加者がリーダーから謝罪を必要と感じるスコアが平均5.37(7段階評価)と最も高かった。これに対し、適切なタイミングでの意思決定では平均4.64、早急な意思決定では4.99であった。
・謝罪の有効性:謝罪が信頼回復にどの程度効果的であるかを示すスコアは、遅延条件で平均3.78と最低値を記録した。適切条件では4.61、早急条件では4.37であった。
上記のデータは、遅延条件において謝罪が求められる一方で、その謝罪が信頼回復にほとんど寄与しないという矛盾した現象を示している。
時間が経れば減るほどに、謝罪の要求は高まる上に、謝罪の意味がなくなっていくということになる。遅れた決定による信頼の低下は、単なるミスよりも深刻な影響を与えるわけだ。
謝罪の遅れによる信頼低下を謝罪だけで解消することは難しい。謝罪には過去の行為を反省し未来への改善を示す意味があるが、それだけでは直接的な解決には至らない。言葉だけの謝罪では行動の変化が見えず、具体的な改善策や結果を示さなければ信頼を取り戻す効果は限定的なのだ。
遅れを取り戻すには、言葉の「謝罪」以上の行動が必要とされる。