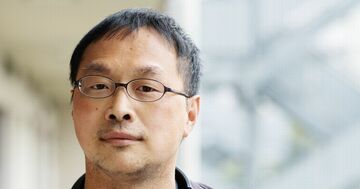誹謗中傷で自殺を考えた…
「カスハラ」が命を脅かす
芸能業界でカスタマーになるのは観客やファン、チケット購入者、出演した映画やテレビ、配信番組などの視聴者が考えられますが、まだ明確に定義はされていません。
しかし芸能従事者の71.6%がインターネット上の誹謗中傷を経験し、それによりストレスを感じた87.8%、精神的被害を受けた58.5%、自殺を考えた人が18.3%もいます(複数回答、82名)。
2023年に特別加入労災保険で精神疾患を労災と認定された音楽家と舞台芸術家がいらしたそうです。決して喜ばしいことではありませんが、認定されたことは何よりと思います。
労災の認定には労基署による詳細な調査があります。しかしながら制度が適用されてわずか2年で既に2件の認定がおりたのは驚きでした。芸能従事者はハラスメントに関する被害が多く重篤な例も少なくありませんので、1人でも多くの方にこの制度を活用していただきたいと願ってやみません。
労災保険を利用するには、事業主が事故防止対策をとることが必要とされています。しかしながら、会社勤めをしていないと、仕事をするにあたって、安全研修を受けるのが習慣にはなっていません。エンタメと安全は一瞬で結びつかないイメージがあるところ、政府も事故防止を推奨する工夫をしたのか、全国安全週間のポスターには著名な芸能従事者が起用されました。
さらに、芸能界に関わる4省庁が連名して通知を出しました。これまで業界全体への安全に関する通知は2通しか出ていないため、非常に画期的なことです。
フリーランスの2割が病気・怪我
芸能界で安全対策が必要な理由
フリーランスの芸能従事者の2割が病気や怪我を経験し、そのうちの1割が休業をしたことが政府の調査でわかったことに触れ、芸能業界でも安全衛生対策が必要だと言っています。
その内容は、制作管理者がガイドラインやチェックリスト等を作成して、計画的に場所や資材や作業の安全衛生対策を検討して予算を確保することです。
具体的には車両、電気設備、大道具、小道具や危険物、撮影機材や録音業者が現場に持ち込んだ資材にも触れ、さらに演技の速度や保護具などにも配慮するよう細やかに言及して安全研修を推奨しています。