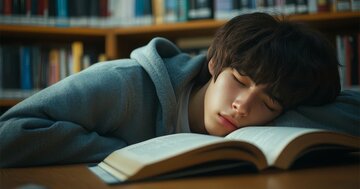この感覚には、統計的な裏づけも、確率論的な裏づけもないのですが、それは関係ありません。あなたはただ、自分にはコントロールできない事象の中に、何らかのパターンを創造しようとしているだけです。
量を操作すれば、結果を変える、つまり運を味方につけることもできるかもしれないということです。
人間は存在しないはずの
「因果関係」を探しがち
これはまた、ランダムな事象の裏にある理論を見つけたいということでもあります。現に人類は、太古の昔から、「星座」という形で、夜空に散らばる星にパターンを見いだしてきました。
もちろん、夜空の星の配置はまったくのランダムですが、人間はそこにパターンを見つけ、自分たちにとってなじみのある文脈の中に組み込もうとするのです。そのような能力は人類の生存にとって必要なものですが、確率を理解するうえではとてつもなくじゃまになるのです。
ギャンブラーの誤謬とは要するに、ただXが起こったという理由だけで、次はきっとYが起こるとか、もうXは起こるはずがないとか、あるいはまたXが起こるはずだなどと考えることです。
たいていの場合、Xが起こることも、Yが起こることも、それぞれが独立した事象であり、お互いに関係はありません。そう考えれば、偽りのパターンに惑わされず、もっと客観的な意思決定ができるでしょう。
人間には物語に影響されやすいという性質があり、何かが起こると、存在しないかもしれない因果関係(あるいは罰や報酬)を探してしまうのです。
意味のないパターンに
意味を見出すのは人間の本能
ランダムな事象の中に因果関係やパターンを見いだそうとする人間の性質は「アポフェニア」と呼ばれています。
雲がウサギに見えたり、インクの染みが何か意味のある形に見えたりするのも、すべてアポフェニアで説明できます。
アポフェニアという言葉は、ドイツ人神経学者のクラウス・コンラッドがつくりました。
コンラッドはこの言葉を、「無意識のうちにつながりを見ること」と定義しています。情報に意味を与えたい、自分がいる環境を理解したいという気持ちは、どうやら人類の進化的欲求から生まれているようです。