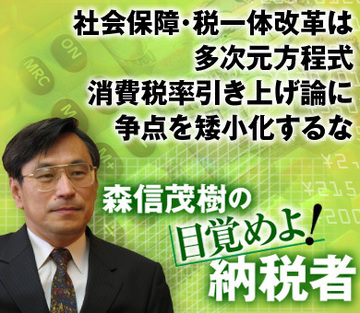森信茂樹
第20回
国民が社会保障・税一体改革を受け入れるためには、既得権益への優遇をなくすことが必要だ。だが、医師優遇税制は会計検査院が指摘したのもかかわらず、財務省・税制調査会そして厚労省はいずれもこれを無視してしまった。
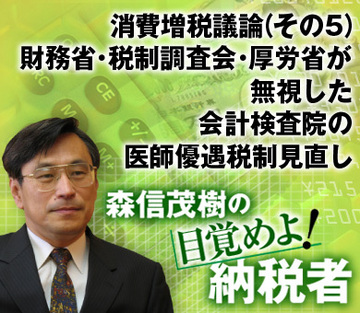
第19回
自民党は消費税の引き上げを民主党の「マニフェスト違反」と非難している。しかし、新たな危機の発生に対して必要な施策を講じることは、政府の重要な責務。本当に問われるべきは、歳出削減マニフェストが全くできていないことだ。
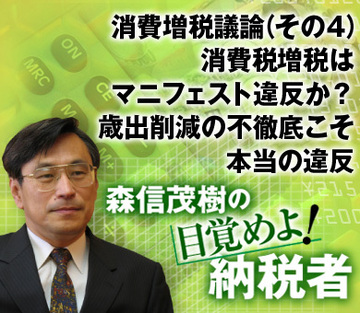
第18回
年末も押し迫って、ようやく社会保障・税一体改革・消費税率の引き上げの素案がまとまった。1997年の消費増税の最大の反省は、税制当局が国民負担増の全体図を知らなかったことにある。一体改革に当たっては、省を超えて全体を統括する真の経済司令塔が必要である。
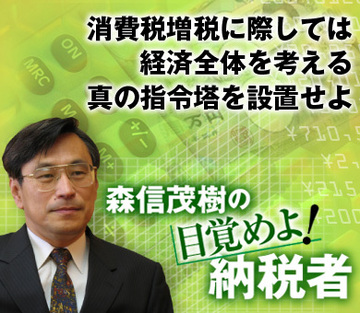
第17回
消費税の最大の欠点は、低所得者の方が負担率が高くなるという「逆進性」の問題である。その対策として軽減税率を採用しているEU諸国では、さまざまな問題が生じている。その欠点を補うには、軽減税率よりも、給付付き税額控除の方が効率的だ。
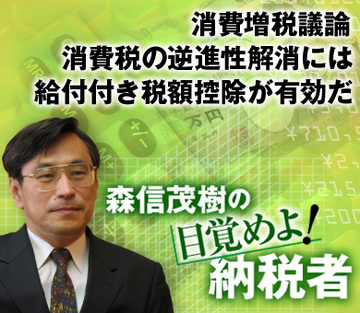
第16回
いよいよ社会保障・税一体改革と消費税の議論が始まる。これらから3回にわたって、その論点を論じてみたい。第1回は、消費税率引き上げの論理はどのようなものか、議論の仕方はどうあるべきかについて考える。
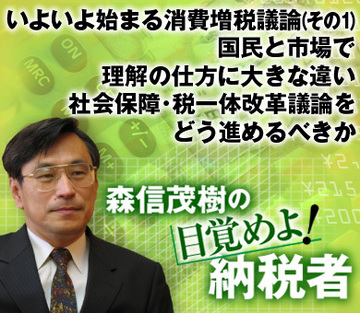
第15回
オリンパスの損失隠しで再び脚光を浴びるタックスヘイブン。最近では相続税対策としての利用する事例が増えている。税負担の公平性や税源の確保に向けて、先進国・税制当局のタックスヘブン諸国に対する攻勢が強まっている。
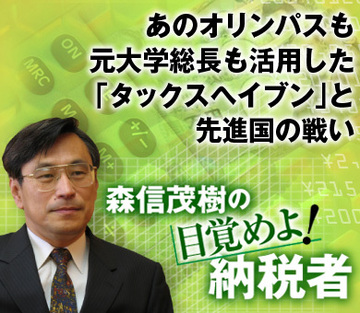
第14回
政権与党内ですら意見の対立するTPP。これを考えるうえでは過去の事例が参照になる。例えば焼酎。内外の税率格差を問題にされ、ウイスキーと同じ税率になったが、業界の必死の努力で輸入ウィスキーを撃破し、今やアルコール飲料の主役の一人になっている。
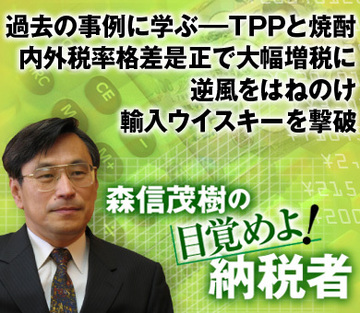
第13回
菅政権下で出された社会保障・税一体改革の「成案」はよくできている。しかし、最大の欠点は「なぜ増税が必要なのか」その理由が国民にさっぱり伝わっていないことだ。一方、自民党も消費税議論を政争の具にしていては、国民からの再評価は得られないだろう。
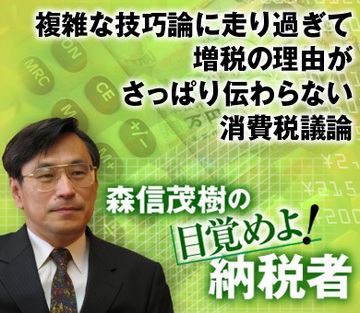
第12回
野田政権が復興増税を決定したことは高く評価される。ただ、増税に対する国民の反対も強まっている。増税実現のためには政府の信頼がカギを握る。信頼回復に向けて「租税特別措置」の事業仕分けを提案したい。
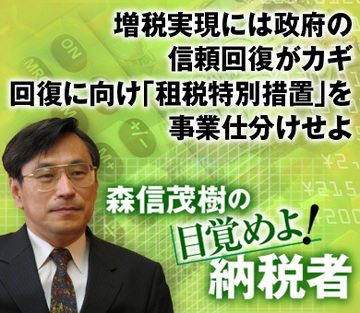
第11回
野田新政権は新たな税制決定システムを立ち上げた。それは自民党時代の長所を取り入れたということのようだが、その仕組みを点検すると、税制改正の背骨となるべき論理が抜け落ちる恐れがある。
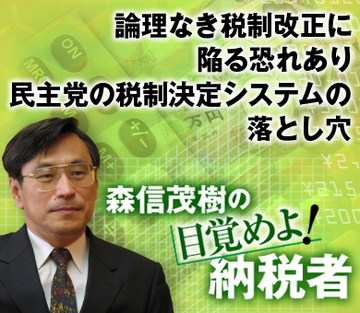
第10回
民主党の代表選挙が目前に迫ってきた。課題はデフレの脱却、新たなエネルギー政策のもとでの経済成長戦略、社会保障・税一体改革、それと震災復興であろう。代表選の候補者たちは、党内融和よりも政界再編につながる骨太で正直な政策論争を戦わせるべきだ。
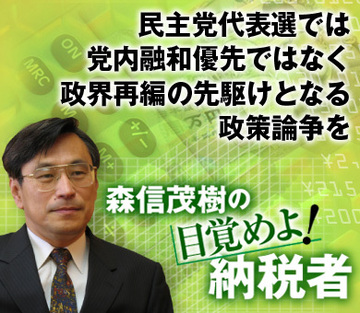
第9回
早晩民主党の代表選挙がおこなわれる。争点は消費税の増税になりそうだ。だが、民主党の有力若手政治家たちは増税路線から距離を置き始めている。苦い選択を先送りする政治家は、消費税導入を成し遂げた、故竹下登総理の立ち居振る舞いに学ぶべきである。
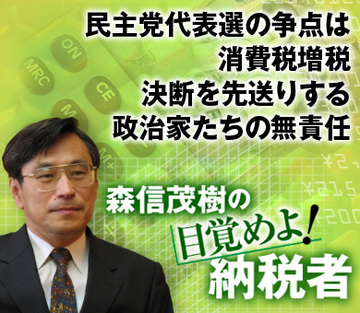
第8回
ある事業者から消費税の表示を、現在の『総額表示』の『外税方式』に戻して欲しいという声が届いた。これは大変難しい問題だが、付加価値税の先輩EUでは『総額表示』1本だ。どちらの表示が望ましいかを考えてみよう。
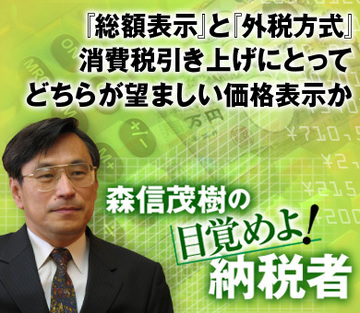
第7回
社会保障・税一体改革における消費税率引き上げの決定が難航している。しかし、今後内閣が代わっても、この基本ラインは変わらないだろう。では、消費税率はいつから、どのように引き上げるべきか。今回はこの問題を考えてみよう。
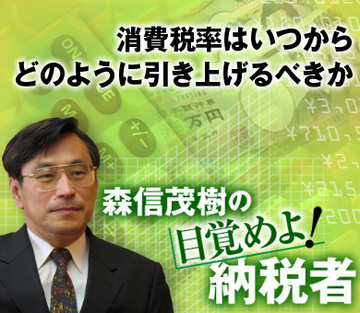
第6回
復興特区の議論が始まった。この機会に地方分権のモデルとなるような特区を構築することは、大きな意義がある。その際、税の分野ではビジネスを呼び込むためには、個人のインセンティブが働きやすい「合同会社」に「パススルー税制」を組み合わせて、法人税をかからない税制を採用すべきだ。
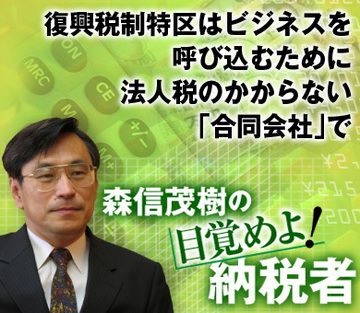
第5回
復興財源論は国債発行派と増税派の二つに大別できる。実はその議論は「国の形」を選ぶということでもある。だが、民主党、自民党にもこの両派がいる。本来ならば復興財源に対する姿勢によって、2大政党に再編成されることで、ようやく政治は安定するだろう。
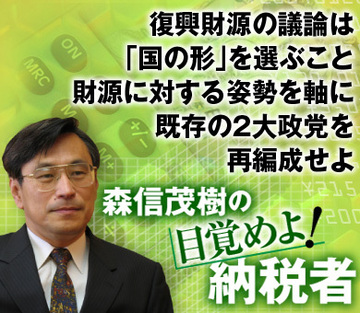
第4回
復興財源調達のために、政府が国債の日銀直接引き受けを検討しているという報道が流れるや長期金利が一時的に上昇した。日銀引受を主張する人たちは財政法を誤解しているか、意図的に曲解している。歴史に学ぶなら、日銀の直接引受はやはり禁じ手である。
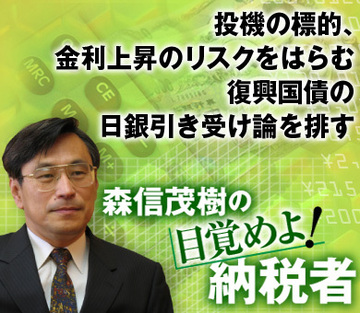
第3回
東日本大震災の被害額は20兆円に迫るともいわれている。復興資金の調達については、いまから検討を始めておく必要がある。その際、国債発行→日銀引き受けという安易な方法は、投機筋に格好の攻撃の材料を与えることになる。そこで財源については、東西ドイツ統合の経験が参考になる。
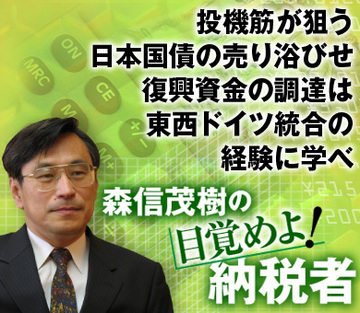
第2回
社会保障と税に活用する番号制度の議論が急速に進んでいる。1980年代半ばにも同様な狙いでグリーン・カードの導入が行われようとしたが、国民の不信を払拭できず廃案になった。今回も拙速に進めればグリーン・カードの二の舞になりかねない。
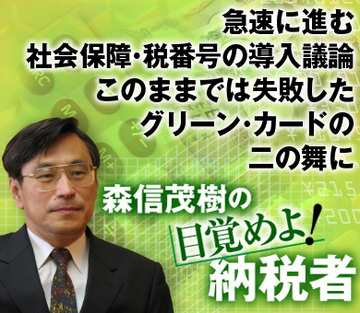
第1回
菅改造内閣の下で、社会保障・税一体改革が始まる。一般には年金・介護・医療の内容を示し、これに対応した消費税率の引き上げを議論することと受け止められている。しかし、議論をそこに矮小化してはならない。我々が議論すべき主要な課題だけでも3つある。