
山田厚史
第121回
26日水曜、NHKが「自民党税調、ビール系税率一本化を見送り」と報じた。「ビールではない、ビールみたいな飲料」で競争する日本の業界は、世界で類を見ない「歪んだ市場」とされてきており、ビール税制の正常化は今年の税制改正の目玉のひとつだった。

第120回
ドイツ銀行の経営危機が話題の折、旧住友銀行OBが実名でイトマン事件を描いた「住友銀行秘史」(講談社)が出版された。どちらも背景に、長期にわたる金融緩和がある。収益競争が銀行経営者を暴走させたのだ。

第119回
もんじゅや日銀で「失敗隠し」が横行している。原子力政策や金融政策という国家の大事な仕事を担う「偉い人」が、なぜこんなに不誠実なのか。日本国は頭から腐りだしている。モラルの連鎖崩壊は止めるのはどうすればいいのか。

第118回
民進党党首選へはメディアの関心も薄く、冷ややかな眼差しを受けて民進党に求心力が働き始めたようだ。経済政策に社会民主主義の色合いが強まったのが今回の特徴で、分配に軸を置く政策へと傾斜している。

第117回
米国ワイオミング州の保養地ジャクソンホールでは世界の金融を仕切る賢者が集まった。「世界の果てまで」お札を撒いて経済を元気にしようという人々の会合だ。彼らに注目が集まるのは、「金融資産を膨らます力」を持っているからだ。金融緩和という魔法の杖である。
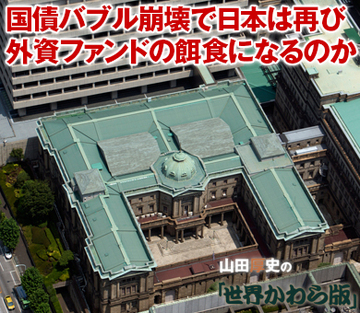
第116回
小池百合子都知事が就任早々の8月9日、NHKとのインタビューで「カジノ推進」を打ち上げた。カジノ推進法案が審議される秋の国会をにらんでのことだろう。だが政府と都の足並みは必ずしも揃っていない。巨大利権を差配するのは誰か、という究極の大問題が不透明なのだ。

第115回
黒田日銀総裁の記者会見に出席し「この人はやっぱり大蔵省の人」とつくづく思った。市場は政策でなんとでもなる、と思っているのが大蔵官僚の特徴だった。財政・税政を握り、権力で経済は動かせるという自負心で彼らは失敗した。

第114回
財政の尻を日銀が面倒見る「財政ファイナンス」が刻一刻と深まっている。そして「ヘリコプターマネー」が取り沙汰されるようになった。空からカネを撒くような、究極の不健全財政。亡国のリスクを孕む奇策が、日本で社会実験される可能性が膨らむ。

第113回
英国のEU離脱、米大統領選など世界政治に異変が起きている。隠然と政治を差配してきたシティやウォール街は民意に晒され、戦が終わった後、世界を覆ったアングロサクソンの金融資本主義に経済弱者が今、反抗しはじめた。

第112回
「舛添祭り」から我々は何を学んだのか。知事と思えないセコさ、政権与党の無責任、水に落ちた犬なら叩ける人たち…。政治家やメディアを嘲笑しても、何も変わらない。ここに描かれたのは、日本の自画像である。

第111回
かつて「権力の守護神」と呼ばれていた財務省だが、今やその威光はない。消費増税先送りの次は、「2020年度プライマリーバランス黒字化」の看板を下ろすことになるだろう。財務官僚に無力感が広がり、「破局願望」さえ漂うようになった。

第110回
2020年東京五輪招致に「裏金疑惑」が浮上した。事件はフランス検察の手の内にある。IOCの倫理規定に違反すれば東京開催は正当性を失うだろう。いったいなぜ、こんなことになったのか。理由は明らかだ。

第109回
安倍首相がプーチン大統領と会談、「新たな発想に基づくアプローチ」で両国の関係改善が促された。歓迎できる方向だが、アメリカやEU諸国がこの動きを歓迎するはずはない。

第108回
ゼロ戦の血統にある三菱自動車、からくり儀右衛門の流れを汲む東芝。「技術と信頼」を看板にした名門企業が存亡に危機に立っている。粉飾決算やデータ偽装という信じがたい不正はなぜ起きたのか。

第107回
「パナマ文書」が世界を震撼させている。先進国はどこも財政難で、真っ先にすべきは税金を払うべき企業や個人が、合法的に逃げる「租税回避」の解消のはずだ。ところが対策は遅々として進まない。それはなぜか。

第106回
首相は「消費増税先送り」へと動き始めたが、日銀の見立ては「景気は緩やかに回復中」だったはずで、ならば消費税見送りという結論にはならない。後世、黒田氏は「中央銀行の規律を崩壊させた総裁」と言われるのではないか。

第105回
TPPが各国の批准を前に、アメリカで失速し始めた。オバマ大統領の任期中の批准は絶望的、大統領候補の指名レースで「TPP賛成」で残っている候補は1人もいない状況だ。何が起きているのか。

第104回
G20では財政を含めた可能な限りの政策が必要とされたが、具体策は各国の宿題になった。財政出動を求める声が噴き出すことは必至で財務省は頭を抱える一方、首相官邸はほくそ笑んでいるという。

第103回
有料老人ホーム「Sアミーユ川崎幸町」を舞台とした連続殺人は、現代の深い闇を投影している。老人の終末、格差社会、若者の閉塞感、社会保障の崩壊。事件は深いところで「市場の混乱」とつながっていないか。

第102回
金融政策が、更なる異次元に踏み込んだ。とうとうマイナス金利。提案した黒田総裁ら正副総裁の3票を除くと審議委員の投票は3対5で反対が多かった。「効かない」「危ない」という疑念が示されたのだろう。
