
佃 義夫
日産と三菱自の軽自動車EV「サクラ」/「ekクロスEV」が今年のカーオブザイヤーの三冠を独占受賞した。軽自動車が独占したのは初めてのケース。日本市場の4割を占める軽自動車カテゴリーにおいて、満を持して投入された“本格バッテリーEV”が高く評価された。

中国EVメーカーのBYDが来年1月から日本市場で乗用車を発売する。競合EVに対し安価な価格設定としたほか、販売力などを重視し2025年度末までに100店舗を超える全国ネットワークを確立させる方針を明らかにした。

来年秋に開催する東京モーターショーが新たに「JAPAN MOBILITY SHOW2023」として生まれ変わる。豊田章男自工会会長の強力なリーダーシップの下、モビリティ産業が旗振り役となって全産業を巻き込む「国民的イベント」へと大きく変革する。

仏ルノーがEVを筆頭に5事業への分割を発表した。同時に、米クアルコムや米グーグルとの連携も明らかにした。注目されていたEV会社への日産、三菱自の出資は見送られた。

ソニーグループとホンダのEV新会社が設立され、10月に記者会見が行われた。設立後初の会見だったが、内容は商品戦略そのものの具体性に欠いたものであった。

経団連が新設した「モビリティ委員会」の初会合が8月22日に行われた。一方で、自動車関連分野の総合団体である日本自動車会議所は、昨年創設した「クルマ・社会・パートナーシップ大賞」の公募を開始、地域活動の発掘を本格化させる。自動車業界でモビリティシフトの動きが活発になっている。

マツダは上級SUV「CX-60」を国内で販売開始した。CX-60は同社が上級車種群と位置付ける「ラージ商品群」の第一弾であり、バブル期以来の「高級車市場」への挑戦となる。

ホンダとLG電池子会社のLGESは、共同で総額6000億円を投じて、米国にEV電池工場を設立する計画を発表した。EV80万台に相当し、25年の量産を目指す。三部社長は就任以来、自前主義からの脱却やEVシフトへの傾斜という独自色を強めている。

日野自動車はエンジン不正について調査報告会見を開き、新たに不正の範囲が拡大したことを発表した。日野自は現在、一部の製品の出荷を停止しており、業績の大幅な悪化は必至だ。

トヨタが16代目となる新型クラウンの発表会を行った。国内高級セダンの代表であるクラウンだが、SUVなどのバリエーション強化に加え、世界展開を目指すことも明らかとなった。これによって国内販売改革にはずみをつける。

日産の株主総会で、仏ルノーとの提携の根幹となる「改定アライアンス基本契約(RAMA)」の内容開示をめぐる問題が話題となった。日産は開示に関する株主提案に反対したものの、初めてRAMAの一部内容を開示した。

マレリのADR申請から3カ月が経過する。KKRを支援企業とし、金融機関に約42%の債権カットを要求する再建案が明らかになるが、一筋縄ではいかなそうだ。

日産、三菱自が共同開発する軽自動車EVが5月発表された。だが、軽EVと同じタイミングで浮上したルノーによるEV事業の新会社化の構想に、業界がざわついている。ルノーはこの新会社に、日産と三菱の参画を要請している。

スズキのインド子会社マルチ・スズキは5月13日、約1800億円を投じて北部ハリヤナ州に新工場を建設することを発表した。3月にはグジャラート州に電気自動車(EV)と車載電池工場の新設も決めており、合計で約3500億円を投じる。

ホンダと米GMが新たな提携を発表した。量販価格帯の新たなEVシリーズを共同開発し、2027年以降に全世界で発売していく。従来のホンダとGMの提携がさらに拡大することになる。
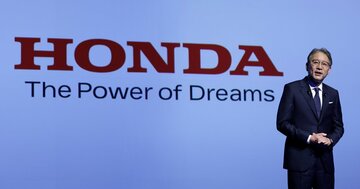
ホンダとソニーグループがEV領域での提携を発表した。ベンチャー企業の走りとして高いブランド力を誇ってきた両社の提携に、大きな注目が寄せられている。

現代自動車が日本に再上陸する。実に13年ぶりの販売だ。ただ、現代自が日本で高いシェアを取れるかというと、それは厳しいとみざるを得ない。

ゴーン元会長の失脚以来、業績不振にあえいでいたルノー・日産・三菱自連合が、新たにEV開発などに約3兆円を投資することを表明した。かつて「リーフ」や「ゾエ」など世界で先駆けてEVを送り出した同連合が、再び世界覇権を狙う。

トヨタが2030年にバッテリーEVを350万台販売するという新戦略を発表した。これまで同社はEV否定派というレッテルを貼られていたが、強気の目標を立てることでそのイメージを払拭したい考えだ。

日産は電動車戦略として2兆円もの投資を行うことを発表した。世界のEVリーダー復権を目指すが、いまだ経営は「病み上がり」の状態。莫大なEV投資計画は画餅に帰す危険性もある。
