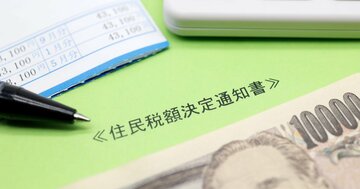井戸美枝
私はファイナンシャルプランナーとして、多くのご家庭のマネープラン作成をお手伝いしています。最近とくに増えているのが、「子どもの大学進学に、どれだけのお金が必要なのか」「奨学金や教育ローンは、どこまで頼っていいのか」といった教育費に関する相談です。

退職金の運用で「大失敗する人たち」に共通する「絶対NGの行動パターン」とは
自分が最期を迎えるときに資産がちょうど0になるように、お金を賢く使い切る生き方が注目されています。しかし、歳を取るほど、老後の生活が不安になり、お金の心配も増すばかりでしょう。定年が見えてきた50歳から老いを迎えるまでに、やりたいことをやり尽くし、悔いのない人生を満喫するにはどうしたらいいでしょうか。

「もし離婚したら、私の年金はどうなる?」――そんな疑問を抱く人が増えている。特に、子育てを終えた女性からの相談は年々増加中。離婚しても経済的に自立できる人が増える一方で、年金分割の仕組みは意外と知られておらず、実際に申請件数は離婚件数のわずか6分の1。「夫の年金は半分もらえる」と誤解しているケースも多い。知らないと損をする年金分割のポイントを、お金のプロが分かりやすく解説する。

2025年4月から子育て支援が大幅拡充する。育休中の「実質10割」給付や時短勤務への新制度、多子世帯の教育費無償化など注目の施策が続々と予定されている。どんな条件で受けられるのか?負担増は本当に「ゼロ」なのか?気になるポイントをお金のプロが分かりやすく解説する。

AIやデジタル技術の進化に伴い、リスキリング(学び直し)の重要性がますます高まっている。特に、政府が2025年までにリスキリング支援に1兆円を投入する計画を掲げる中、教育訓練給付金や新設される教育訓練休暇給付金など、労働者が活用できる支援制度が大幅に拡充中。今回はこれらの最新制度を詳細に解説し、どのようにキャリアアップや転職活動に役立てることができるかを紹介する。

企業型DCに「選択型」を導入する企業が増えている。従業員が給与の一部を企業型DCの掛け金として資産運用することができるため、投資を始めるハードルが下がるほか、税金と社会保険料の負担が軽減できるメリットなどがある。一方で、子どもを持つ予定がある人などは、こうした負担軽減の恩恵が受けられないケースも。メリット・デメリットについてマネーの専門家が解説するとともに試算を公開する。

医療保険に「入らなくていい人」と「入った方がいい人」の明確な違い【人気FPが解説】
公的年金は老後を支える大切なお金だ。まずは自分がもらえる年金をしっかり把握しよう。さらに年を取り、病気やケガで入院した場合、公的医療保険ではまかなえない可能性がある。医療保険のこともよく知っておきたい。本稿は、井戸美枝『好きなことを我慢しないで100万円貯める方法 20代女子のためのお金の基本』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

新NISA「ネット証券」と「銀行」どっちで口座開設すべき?ラインナップで考えたら1択だった!
2024年から始まった新NISA。非課税保有期間が無期限化・投資可能期間が恒久化されたため、さらに柔軟に投資ができるようになった。しかし、始めるにあたっては知っておくべきことも多い。本稿は、井戸美枝『好きなことを我慢しないで100万円貯める方法 20代女子のためのお金の基本』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

「食費や娯楽費を削って節約」はザンネンな努力!では真っ先にカットするべき費用は?【人気FPが解説】
日々変わっていくお金の制度や情報。お金を賢く貯めるには、その時々で必要なお金の知識を勉強してアップデートすることが重要だ。ちょっとしたことでお金が貯まる仕組みづくりを専門家がアドバイスする。本稿は、井戸美枝『好きなことを我慢しないで100万円貯める方法 20代女子のためのお金の基本』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

年金制度であり、老後の資金を積み立てながら税負担が減るという「お得さ」に注目が集まっているiDeCo(個人型確定拠出年金)。しかし、実は誰でもそのお得さを享受できるというわけではありません。iDeCoに加入することで損をしてしまう可能性がある「3つのケース」を解説します。

うつ病は、誰でもかかる可能性がある病の一つです。治療の基盤となるのは、医師の診察、服薬、そして休養です。うつ病は、ゆっくりと改善するケースも多く、通院や服薬などの出費が続くこともあります。加えて、治療中は休職したり、労働時間が減ったりして、収入の減少が気になるかもしれません。そこで知っておきたいのが、公的な支援です。一体どんなものがあるのか詳しく見ていきましょう。

給料から引かれすぎじゃない?20代で知っておきたい「4つの社会保険と自己負担分」
一度は耳にしたことがある「社会保険」という言葉。どんな保険に加入していて、それぞれどんな役割を果たしているか紹介します。
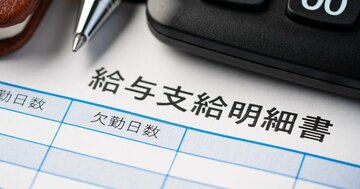
20代はお金を何に使うべき?「稼ぐ力」つける自己投資におすすめの資格とは?
20 代は仕事の基礎能力を高めてキャリアの土台づくりをする時期。資格取得やスキルアップに投資しましょう。

「自分の年収」正しく把握してる?給与明細書で確認すべき“3つのポイント”とは?
給与明細書には「勤怠」「支給」「控除」の3つの項目があり、毎月の給与がどのように計算されたのかを知ることができます。
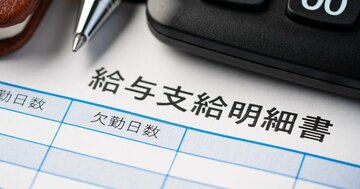
2024年1月から、NISAの非課税期間が無期限となりました。今後、生涯にわたってNISAを運用し、その資産を親族が相続する、そういったケースが増えるかもしれません。そんな中、「故人のNISAはどうなるのか?」という質問も増えています。

2024年が始まりました。本稿では、私たちの暮らしに影響するであろう税制を中心に、2024年度の税制改正をご紹介します。税制改正といえば、昨年「所得減税」の是非が話題になりました。将来性のある有意義な改正となっているか、有権者としてこのあたりもチェックしておきましょう。

今年も残すところあとわずか。今年よく病院へ行った人、ドラッグストアなどで医薬品を買った人に確認してほしいのが、その1年間の合計金額です。要件を満たせば、医療費控除やその特例(セルフメディケーション税制)の対象となり、税負担が軽減されるかもしれません。

2024年に改正される「NISA」が注目を浴びています。筆者はファイナンシャルプランナーとして家計の相談に乗っていますが、「NISA」と「iDeCo」をどう使えば良いか、と質問をいただくことが増えてきました。両制度は「税制優遇」という共通点はあるものの、その仕組みは大きく異なります。今回は、それぞれの制度の特徴やメリット、年齢や働き方に合った使い方のポイントをご紹介します。

お金があれば、幸せになれる――と信じる人も多いでしょう。しかし、実際お金があるからこその苦労や悩み、トラブルなどに多く遭遇しているようです。成功体験ではなく失敗から教訓を得る特集『富裕層の「お金の大失敗」』の#1では、世帯年収1300万円の30代夫婦のマンション購入から学びます。

6月は住民税が変わるタイミングです。会社や自治体から住民税の通知を受け取りましたよね。住民税を確認する際には、必ず「控除」を確認してください。住民税や控除の仕組みを理解していれば、公共サービスの負担を軽減できることもあります。この機会に住民税の仕組みや、チェックすべき「控除」を確認しましょう。